今回は『腎機能別薬剤投与量 POCKET BOOK』をレビューします。
正直、私はこの本がないと仕事ができません。それくらい薬剤師にとって欠かせない一冊だと実感しているので、ぜひ紹介したいと思います。
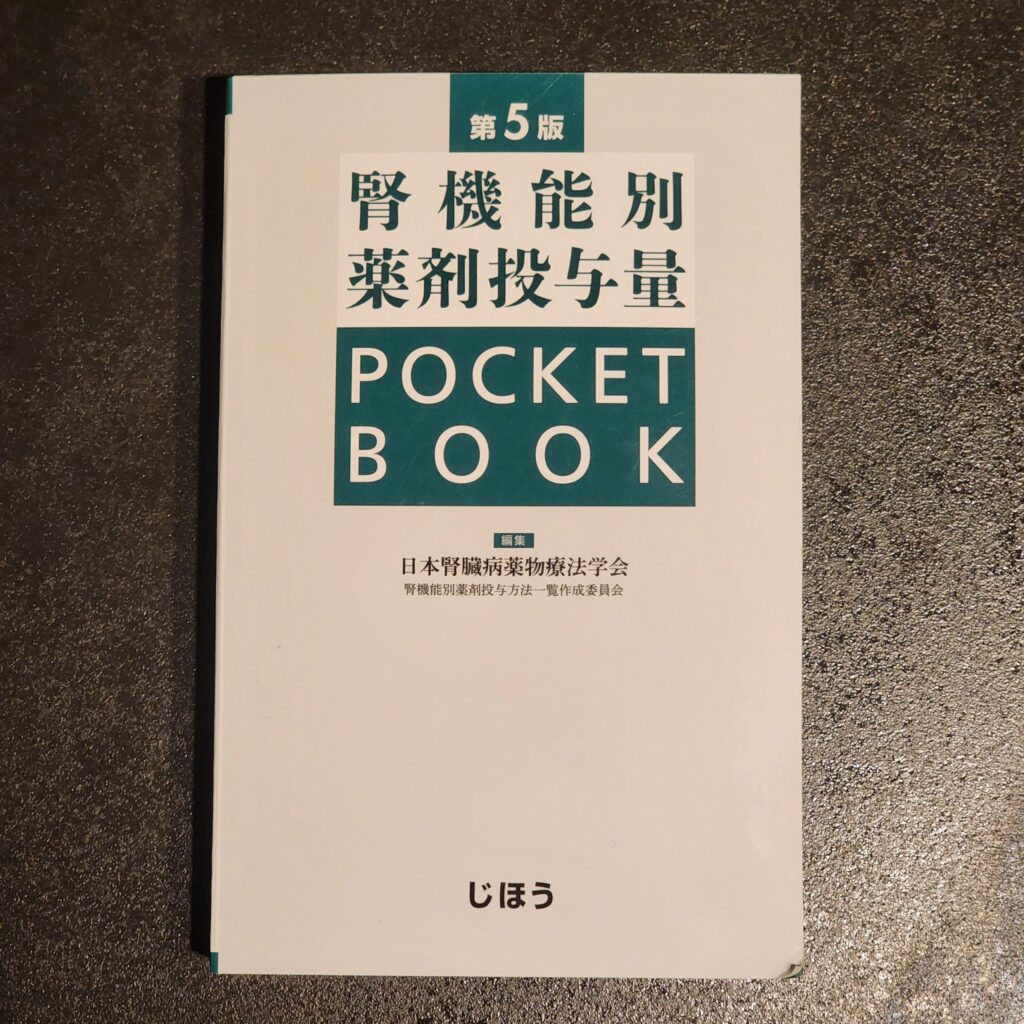
「この患者さん、腎機能低下してるかも?」—— そう思ったこと、ありますか?
高齢者は腎機能が低下しやすい。これは薬剤師なら誰でも知っていることですよね。
でも、忙しいと処方通りに薬を交付することに意識が向き、腎機能のチェックを考える余裕がなくなりがちです。
そもそも、腎機能低下に気づけずにそのまま薬を交付してしまう…。
そんな経験は、誰にでもあるのではないでしょうか?
しかし、腎機能低下に気づかないままの監査は「処方監査」ではなく、単なる「計数監査」にすぎません。
薬の正しい数量を確認するだけでは、薬剤師の本来の役割を果たしているとは言えません。

私は本書を活用し、これまでに多くの減薬提案を行い、薬剤調整支援料の算定にもつなげてきました。
本書を使うことで、腎機能低下を見逃さず、適切な減薬提案ができる薬剤師になれます。
この記事では、
- 『腎機能別薬剤投与量 POCKET BOOK』の使い方
- 腎機能低下に気づくためのポイント
- 減薬提案をスムーズに進めるコツ
を具体的に解説します。
この記事を読めば、「腎機能低下を見逃さない視点」と「すぐに使える投与量調整の知識」の両方を手に入れられます。さらに、薬剤調整支援料を積極的に取るスキルも身につきます。

腎機能を意識するだけで、薬剤師としてのレベルは大きく上がります。そして、それを強力にサポートするのが『腎機能別薬剤投与量 POCKET BOOK』です。
しかし、「この患者さん、腎機能どうなんだろう?」と疑う視点がなければ、どれだけ優れたツールを持っていても使いこなせません。
この本なしでは仕事にならないと実感する理由と、この本を使いこなすための考え方を、ぜひこの記事で確認してください。
| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 必要な情報にすぐアクセスできる構成。目次や索引が整理されており、慣れるとサッと調べられます。ポケットサイズで携帯性も抜群。病院回診や往診同行時に即確認できる心強い1冊。 | |
| 実務での活かしやすさ | 腎機能低下患者の処方チェックや減薬提案に有用。ただし、薬剤師本人が腎機能を意識していないと活用できないため星4。 | |
| 自己学習への向き | 総論で腎機能の基本知識は学べるが、腎機能の勉強には別の本がオススメです。本書は現場で調べる用の実務ツールです。 | |
| 読みやすさ | コンパクトな情報量だが文字は小さめでやや見づらいかもしれません。レイアウトは整理されており、慣れれば検索しやすいです。 | |
| コスパ | 税込4,180円。使用頻度・信頼性・重要性から価格以上の価値があります。複数薬局を回る派遣薬剤師は個人での所持が必須です。 |
『腎機能別薬剤投与量POCETBOOK』とはどのような本なのか?
腎機能低下患者の投与量を確認する実務書
『腎機能別薬剤投与量POCKET BOOK』は、腎機能の程度に応じて、薬剤の適正な投与量を素早く確認できる実務向けの参考書です。
本書は、腎機能(クレアチニンクリアランスやeGFR)に応じた投与量を一覧で確認できるため、業務のスピードを落とさずに適正投与量を判断できます。
また、本書は腎機能について基礎から学ぶための解説書ではなく、実務で「この薬の適正投与量をすぐに知りたい」といった場面で活用するための本です。
どのような情報が載っているのか?
- 2024年9月に発売された最新の第5版では2000を超える薬品の情報
- 調剤薬局でも院内薬局でも一般的に使用されるほとんどの医薬品
- 添付文書には具体的な減量すべき用量が記載されていない薬の腎機能別推奨量
- 内服はもちろん、注射剤や貼付剤などの情報
- 腎機能低下で減量が必要な薬はもちろん、減量が必要ない薬も網羅的に掲載
本書は見開きで構成されており、左ページに常用量、右ページに腎機能低下の数値別の投与量が記載されています。また、透析患者における適正な投与量も記載されており、腎機能に応じた投薬調整を即座に判断できる作りになっています。
詳しいイメージについては、 こちら からご確認ください。(試し読みページ URL:https://li-lookthru.herokuapp.com/embed/67205fdb0918dd00188123f1#book/67205fdb0918dd00188123f1/page/1)

つまり、めちゃくちゃ見やすい構成になっています。
他の書籍との違い・強み【腎機能低下への投与量特化】
本書は、腎機能別の投与量調整に特化した唯一無二の書籍です。
一般的な医薬品集(『今日の治療薬』『治療薬マニュアル』など)にも腎機能に関する情報は記載されていますが、それらはあくまで薬剤の全般的なデータの一部に過ぎません。
一方、本書は腎機能低下時の用量調整のみで構成されており、必要な情報に素早くアクセスできるという点が大きな違いです。
さらに、本書はポケットサイズでコンパクトな作りになっているため、持ち運びに便利です。
調剤室での業務中はもちろん、病棟や往診同行の際にもすぐに取り出して確認できるため、特に病院薬剤師や訪問診療など調剤室の外で働く薬剤師にとって、使いやすいです。
腎機能別の投与量をここまで詳しくまとめた書籍は他にありません。
腎機能を考慮した適正な処方監査や減薬提案を行うために、必携の一冊といえるでしょう。
この本が役立つシチュエーション
本書は、薬局、病院、訪問診療のあらゆる場面で活用できる実務向けの一冊です。腎機能を考慮した処方監査を行う上で、日々の業務で頼りになる存在となります。
薬局での監査業務
薬局での処方監査では、腎機能低下を考慮した投与量の確認が欠かせません。特に高齢者では、クレアチニンクリアランスごとの用量調整が必要になる場面が多く、本書を活用することで迅速かつ正確に判断できます。
薬剤師の業務の大半は処方監査に関わるため、日常的に本書を参照する機会は多くなります。「この患者さん、本当にこの用量で大丈夫か?」と考える習慣を持つことで、疑義照会や減薬提案の精度が向上します。
病院での回診・往診同行
病院や訪問診療では、医師から「この薬、腎排泄か?」「腎機能低下時の投与量は?」と質問されることがあります。本書があれば、その場で即座に適正投与量を確認し、スムーズに対応できます。
処方決定が即時に行われる場面では、素早く投与量を判断できることが求められます。ポケットサイズの本書なら、回診や往診同行時にも携帯しやすく、実務での活用頻度が高い一冊です。
トレーシングレポートの作成【薬剤調整支援料が算定できる】
トレーシングレポートを活用した減薬提案にも、本書の情報が役立ちます。
腎機能低下が疑われる患者の処方を見直し、適正な投与量を提案する際に、本書のデータを根拠として示すことで、医師への伝達がスムーズになります。
特に薬剤調整支援料の算定を行いたい薬剤師にとって、適切な処方提案を裏付けるツールとして非常に有用です。
腎機能を意識した処方監査を習慣づけることで、より安全で根拠のある薬物療法を実践できます。
本書の使い方
使いこなすための基本的な考え方【腎機能低下を疑うことが前提】
本書を活用するには、まず腎機能を意識する習慣を持つことが大前提です。腎機能に留意する意識がなければ、「この患者さん、本当にこの用量で大丈夫か?」と疑うこともなく、本書を手に取る機会すら生まれません。つまり、処方監査や服薬指導の際に腎機能を考慮する習慣がなければ、本書を活かすことはできません。
極端かもしれませんが、私は80歳以上の高齢者は「全員」軽度腎機能低下があると思って、処方監査を行なっています。加齢による腎機能の低下は避けられません。健康な高齢者であっても腎排泄型薬剤の蓄積リスクは高まります。この前提で監査を行うことで、「この用量で問題ないか?」と考える機会が増え、処方の適正を見直す習慣が自然と身につきます。
また、普段の患者との会話の中で、「最近、採血しましたか?」「健康診断は受けていますか?」と質問する癖をつけることも大切です。これは腎機能を意識するためだけでなく、実際の採血データを直接確認するためでもあります。採血結果があれば、クレアチニンやeGFRを把握でき、より正確な処方監査が可能になります。患者自身が検査結果を持っていない場合でも、「健診結果をお薬手帳に挟んでおくといいですよ」と伝えることで、次回以降の確認がスムーズになります。
腎機能低下を意識し、採血データを活用することで、監査の精度が向上し、疑義照会や減薬提案をより適切に行えるようになります。本書は、その意識を持った薬剤師が、実際の投与量をスムーズに判断するための強力なツールです。まずは、日々の業務で「この患者さんの腎機能はどうだろう?」と考える習慣を身につけ、その判断をサポートするものとして本書を活用していきましょう。
腎機能低下を疑う基準【80歳以上と医師からの指摘】
・80歳以上
・医師からの腎機能の注意喚起
一つ前の見出しで80歳以上は全員腎機能が低下していると考えていると言いました。
「高齢者≒腎機能低下」は薬剤師全員が知っていることですが、高齢者というのが自分の中で少し曖昧で意識しづらいです。監査の時に自分の意識に引っ掛かりにくい。
「80歳以上は腎機能低下」と考えるようにしてからは、基準が明確になったので、腎機能により留意できるようになりました。
ただし、この考え方で注意する点は、実際に80歳以上全員が腎機能低下しているわけではないことです。
この基準はあくまで「腎機能を意識するためのトリガー」であり、実際の投与量調整の判断は具体的な検査データが必要です。すでに腎機能の低下を聞き取りしている場合や明らかに腎機能低下を疑えるような状況以外で、80歳以上だからという理由だけで疑義照会することはありません。
また、腎機能低下を判断するために患者に直接聞き取ることも重要です。その際の聞き取り方に工夫が必要です。
「腎機能が落ちていますか?」や「ご自身の腎機能をご存知ですか?」といった聞き方では、患者が自分の状態を正しく認識していない場合に正確な情報が得られないことがあります。そのため、「腎機能が落ちていると医師から言われたことはありますか?」と尋ねる方が、患者にとって答えやすく、正確な情報を得やすいと考えています。
一歩進んだ使い方【併用薬から腎機能低下を疑う】
本書を使って 腎機能に留意しながら業務を続けていると、腎機能に注意が必要な薬が自然と頭に入ってくるようになります。
処方監査の際に、「この薬は腎機能低下時に減量が必要だったな」と気づけるようになると、お薬手帳の内容から腎機能を推測することもできるようになります。
今回は、 実際の症例をもとに、併用薬から腎機能低下を推測し、適切な減量提案につなげたケースを紹介します。
84歳男性の患者が、皮膚科の処方箋を持参しました。
▶ 処方内容(皮膚科)
• フロモックス100mg 3錠分3 毎食後 5日分
• ゲンタシン軟膏 1日2回塗布
この時点では、特に腎機能を意識する処方ではありません。
しかし、お薬手帳を確認すると…
▶ 併用薬(かかりつけ医の処方)
• アムロジピン 5mg 分1 朝食後
• アトルバスタチン 10mg 分1 朝食後
• エゼチミブ 10mg 分1 朝食後
• ファモチジン 10mg 分1 朝食後(通常の1/4量)
• フロセミド 20mg 分1 朝食後(ループ利尿薬)
💡 ここでポイントとなるのが、ファモチジンの用量です。
ファモチジンの通常用量は 40mg/日ですが、この患者は 10mg/日で服用されていました。
さらに フロセミド(ループ利尿薬) も処方されていることから、 「腎機能低下の可能性があるのでは?」 と疑いました。

医師から腎機能が落ちていると言われたことはありますか?

かかりつけ医から腎機能が落ちているから胃薬は少なめにしていると言われたことがある。
この聞き取りをもとに、皮膚科の医師に疑義照会を行いました。

詳細な腎機能のデータは不明ですが、
・かかりつけ医から腎機能低下の指摘がある
・併用薬であるファモチジンの用量からCCr30mL/min以下の高度腎機能低下の可能性がある
・フロモックスは60>CCr≧15で100mg 2錠 分2 朝夕食後に減量が推奨される
上記のことから、フロモックスの減量をご検討ください。
その結果

フロモックス100mg 2錠 分2 朝夕食後 5日分 に変更してください。
腎機能のデータがなくても、処方内容や併用薬、患者さんからの情報で、適切な減量提案ができました。
フロモックスの添付文書には具体的な減量すべき用量の記載はありません。
本書には具体的な数値が書かれています。
本書がなければ、腎機能低下を疑えても、具体的な用量を医師に丸投げすることになるので、やはり本書は有用です。
腎機能低下時に調整が必要な薬の一例
処方監査の際、以下のような腎排泄型の薬剤を確認することで、腎機能低下を推測できることがあります。
・ H2ブロッカー(ファモチジンなど)
・ メトホルミン(ビグアナイド系糖尿病薬)
・ 抗生剤(ニューキノロン系・ペニシリン系・セフェム系)
・ アテノロール(β遮断薬)
・ アロプリノール(尿酸生成抑制薬)
・ 帯状疱疹の薬(アシクロビル、バラシクロビルなど)
・ DOAC(直接経口抗凝固薬:ダビガトラン、エドキサバンなど)
・ ジゴキシン(強心配糖体)
このような薬剤が常用量よりも少なく設定されている場合、腎機能低下の可能性を考慮し、適正な処方かどうかを確認することが重要です。
本書を活用し続けると、直感的に気付けるようになる
最初から本書をスムーズに活用するのは難しいかもしれません。でも、腎機能を意識する習慣を身につけることで、徐々に直感的に気付けるようになります。そのためには、次のステップを意識するのが効果的です。
1️⃣ まずは「腎機能に留意する」と心に誓う!
いや、それができれば苦労はしないよ!というツッコミが聞こえてきそうですが…最初は「腎機能に留意する」というトリガーを自分自身に設定しないと、本書を手に取ることができません。
最初は意識的に考えないと難しいですが、続けるうちに自然とチェックするクセがつきます。
2️⃣ 腎機能低下を疑う基準を自分の中に作る
80歳以上または医師から腎機能低下の指摘を受けたことがある患者は、必ず腎機能を確認するクセをつけます。
3️⃣ 腎機能低下を疑ったら、本書で調べる
腎機能低下が考えられる患者を見つけたら、本書で適正投与量を確認します。検索に慣れることで、本書を使うスピードも上がります。
4️⃣ 「この薬、減量が必要かも?」と気付いたら、積極的に疑義照会やトレーシングレポートで医師に情報提供
実際に疑義照会やトレーシングレポートを作成してみることで、腎機能低下時の用量調整を学ぶ機会が増えます。最初は不安かもしれませんが、減量提案の経験を積むことで、医師への伝え方もスムーズになります。
5️⃣ 1回でも減量が成功すると、それが強烈な成功体験になる
疑義照会やレポートを通じて減量が実現すると、「やっぱり腎機能を意識するのって大事なんだ!」と実感できます。この成功体験が次のモチベーションになり、自然と腎機能を意識できるようになります。
6️⃣ 気付けば腎機能を考慮するのが当たり前になっている
こうした経験を積み重ねることで、腎機能低下のリスクに直感的に気付けるようになります。本書を活用しながら処方監査を続けることで、適正な用量設計ができる薬剤師へと成長していきます。
最初は意識的に取り組む必要がありますが、繰り返し実践することで自然と腎機能をチェックする視点が身につきます。本書を活用しながら、この流れを習慣化していきましょう!
本書を活用したトレーシングレポートの実例
処方医にトレーシングレポートを提出し、服用薬剤調整支援料を算定した症例を紹介します。
症例1 採血結果を確認できたケース
・87歳女性
・数年に渡ってアシノン錠(ニザチジン)150mg 2錠分2で服用されている
・腎機能に疑った時点で採血結果は不明
処方監査の際に高齢のため腎機能低下の可能性を疑いました。

胃薬をずっと飲まれていますが、胃の調子はいかがですか?
調子が良ければ服用の中止も検討できますか?

この薬を飲んでいれば調子がいいですが、飲むのをやめるとまた胃の調子が悪くなります。
服用状況、効果に問題はなさそうです。

最近、採血はしましたか?
採血をした際に先生から腎機能が低下していると言われたことはないですか?

この前、別の病院で採血をしました。その時も特に腎機能の指摘はなかったと思います。

採血結果ぜひ見たい!

採血結果はお持ちですか?〇〇さんが服用している胃薬は腎機能によって減量が必要な薬です。腎機能は年齢とともに少しずつ働きが落ちるので、歳相応の腎機能だったとしても、減量が必要な場合があるんです。
次回来局時、患者さんが採血結果を持参してくれたため、数値を確認しました。
クレアチニンクリアランスの計算には体重が必要なので、患者に体重の聞き取りをしましたが、体重計に乗る習慣がなく、わからないとのことでした。
・SCr 0.91(基準値:0.4-1.0mg/dL)
・BUN 26.0(基準値:7-20mg/dL)
・体重不明(小柄なため、40kgと仮定)
→計算すると、CCr27.5でした。高度腎機能低下の値です。
この数値からアシノンの減量が必要と判断し、トレーシングレポートを提出しました。
ちなみにずっと服用されており、緊急性はないと判断し、疑義照会はしていません。
【提出したトレーシングレポート(全文)】
処方薬 アシノン錠150mg 2錠分2 朝夕食後
87歳と高齢の患者で、腎機能低下が疑われるため、ご報告させていただきます。
他院での採血でSCr 0.91、BUN 26.0と確認いたしました。採血日〇/〇
体重を測ることがないようで、正確な体重は不明ですが、40kgと仮定するとCCr 27.5となり、高度腎機能低下の可能性があります。
小柄な高齢女性のため、筋肉量も少なく、実際の腎機能は見た目のCCrよりも悪い可能性もあると考えます。
アシノンは60>CCr≧15の患者では150mg/日への減量が推奨されております。
患者より胃の調子は悪くないと伺っており、高齢者へのH2ブロッカーは認知機能低下リスク、せん妄リスクを高めるとの報告もあります。
アシノンの用量について、ご確認をお願いいたします。
このトレーシングレポートを提出した次の処方で、アシノンが150mg 1錠分1朝食後に減量となりました。
症例2 採血結果が確認できなかったケース
・79歳女性
・数年に渡って、ガスターD20mg2錠分2朝夕食後で服用されている
・併用薬
アジルサルタン20mg 1錠 分1 朝食後
ロスバスタチン5mg1錠 分1 朝食後
ミヤBM 3錠 分3 毎食後
ケース1と同様、高齢でH2ブロッカーを長期的に継続している患者さんです。

胃薬をずっと服用されていますが、胃の調子はどうですか?採血をされた際に、腎機能について医師から指摘があったことはありますか?

胃の調子は悪くない。腎機能についてはよくわからないわ。検査結果も捨てちゃってる。
薬を減らせるなら減らしたいわよね。
「胃の状態は悪くない」「薬を減らせるなら減らしたい」と患者の意向を確認したため、ガスターの減量を提案しました。
【提出したトレーシングレポート(全文)】
ガスターの減量をご検討いただきたく、ご報告させていただきます。
ガスターはCCr60以下では、20mg/日が推奨量となります。
採血結果などが不明のままでの報告で大変恐縮ですが、78歳と高齢のため、軽度腎機能低下の可能性もあるかと考えました。
体重50kgでは、SCr 0.7程度でもCCr50程度となり、軽度腎機能低下に該当します。
また、患者さまより「胃の症状は全くない」「薬を減らしたい」との希望がありました。
ガスターの減量をご検討いただけないかと思います。
【提案事項】
ガスターD20mg 2錠 分2→1錠 分1への減量をご検討ください。
先生が腎機能に留意されていた場合、大変失礼な提案になることをご容赦ください。
このトレーシングレポートを提出した次の処方で、ガスターが20mg 1錠 分1 朝食後に変更となりました。
検査値がない状況での提案のため、患者さんの希望などを記載することで、根拠に欠けたとしても、納得感のある提案になると思います。
また、最後の文章は、処方医が腎機能低下を把握した上で常用量を処方されている可能性に配慮しています。
薬剤師として減量の提案をする際、医師がすでに腎機能を考慮し、治療方針として現行の用量を維持している場合もあるため、注意が必要です。
そのため、最後の文書で「決めつけではなく、あくまで確認の提案である」というニュアンスを含んでいます。
薬剤師の視点から減量の可能性を提案することは重要ですが、処方の最終判断は医師に委ねられます。こうした表現を入れることで、医師との関係性を損なわず、柔らかく減量提案ができるというメリットもあります。
症例3 併用薬の用量から減量を提案したケース
・81歳男性
・ジゴキシンKY錠0.25mg 1錠分1 朝食後
・プラザキサカプセル110mg 2Cap分2 朝夕食後
・その他の併用薬 イルベサルタン、バイアスピリン、アムロジピン、トリアゾラム
ジゴキシンもプラザキサも腎機能低下がある場合は減量が必要です。
プラザキサは常用量よりも少なめで処方されていますが、ジゴキシンは常用量で処方されています。
プラザキサの減量が腎機能を考慮したものだった場合にジゴキシンも減量した方がいいのでは?とトレーシングレポートを提出しました。
| 薬剤 | 常用量 | 腎機能低下時推奨量(条件) |
|---|---|---|
| ジゴキシン | 0.25 mg/日 | 0.125 mg/日以下 (15 ≦ CCr < 60 mL/min) |
| プラザキサ | 150 mg 1回2カプセル、1日2回 | 110 mg 1回2カプセル、1日2回 (30 ≦ CCr < 60 mL/min、30未満は禁忌) |
- ジゴキシンの常用量:0.25mg/日
- 腎機能低下時の推奨量:0.125mg/日以下
- プラザキサの常用量:150mg 1回2カプセル、1日2回(合計300mg/日)
- 腎機能低下時の推奨量:110mg 1回2カプセル、1日2回(合計220mg/日)
- ※CCr 30〜50mL/min の場合
【提出したトレーシングレポート(全文)】
【報告】
高齢の方であり、腎機能低下の可能性があるため、ご報告させていただきます。
・ジゴキシンKY錠0.25mg 1錠分1 朝食後
・プラザキサカプセル110mg 2Cap分2 朝夕食後
ジゴキシンは50≧CCr >15で、維持量として1日0.125mgが推奨量とされています。
プラザキサは50≧CCr >30で、維持量として1回110mg1日2回が推奨量とされています。
プラザキサは常用量よりも少ない用量ですが、ジゴキシンは常用量で継続されています。
現状、ジギタリス中毒の症状である、悪心、振戦、徐脈などは見られていません。
腎機能を考慮し、プラザキサを減量されているのであれば、ジゴキシンも減量が必要かと思い、ご報告させていただきました。
正確な腎機能が不明のままでの報告で申し訳ありません。先生がすでに腎機能にご留意されていた場合、大変失礼な報告になること、ご容赦ください。よろしくお願い致します。
このケースではその後も処方変更はありませんでしたが、減量の提案を文書で行ったので服用薬剤調整支援料を算定しました。
『腎機能別薬剤投与量POCKET BOOK』を現場で使っている私の感想【気になる点なし】
処方監査のスピードが格段に上がった
本書を活用するようになってから、処方監査のスピードが格段に上がりました。
以前は腎機能に応じた用量調整を確認するのに毎回添付文書を開いていましたが、今では本書を開くだけで必要な情報がすぐに見つかるため、業務の負担が大幅に軽減されました。
トレーシングレポートでの減量提案の件数が増えた
また、トレーシングレポートで減量提案をする機会も増えました。
これまで「体調変わりありません」とだけ聞き取りをしていたDo処方でも、漫然と投与されている腎機能に注意が必要な薬に気付けるようになったからです。
ただ、これは単に本のおかげというよりも、本を使い続けることで自分自身の腎機能に対する注意力が向上した結果だと感じています。
本書を活用することで、処方監査の精度が上がり、薬剤師としてのスキルが向上している実感があります。
正直、本書の利用することのデメリットはありません
忖度なく、本書はメリットしかありません。
持っているだけで業務の精度とスピードが向上するので、薬剤師なら全員が手元に置いておくべき本です。
薬局には必ず1冊置いておくべき、フリーランスや派遣薬剤師は全員買うべき1冊です。
『腎機能別薬剤投与量 POCKET BOOK』をオススメできる人
本書は、腎機能を考慮した処方監査をスムーズに行いたい薬剤師にとって、非常に役立つ一冊です。特に、以下のような方には強くオススメします。
腎機能低下を考慮した処方監査の質・スピードを上げたい方
添付文書を開かずに、すぐに適正用量を確認できるため、監査業務の効率が大幅に向上します。
複数の薬局を掛け持ちする薬剤師
派遣・パートなどで勤務先が変わる場合でも、腎機能に注意が必要な薬の情報を手元に持っておくことで、どの職場でも安定した監査ができます。
トレーシングレポートで薬剤調整支援料を算定したい方
高齢者のDo処方に潜む漫然投与の薬を見つけやすくなり、医師への減量提案の根拠として活用できます。
今まで腎機能を意識していなかった方
処方監査の際に腎機能を考慮する習慣がなかった方でも、本書を手にすることで「この患者さんの腎機能は大丈夫か?」と意識するきっかけになります。
病院で回診・往診同行をする方
医師から「この薬、腎機能大丈夫?」と聞かれたときに、すぐに本書を開いて確認できるため、即時対応が求められる場面で活躍します。
本書を使いこなすことで、処方監査の精度が上がり、薬剤師としてのスキルアップにもつながります。
腎機能を考慮した適正な投薬を行うために、ぜひ活用してみてください!
著者紹介
本書は、日本腎臓病薬物療法学会が編集した信頼性の高い書籍です。
日本腎臓病薬物療法学会は腎疾患時の薬物療法に関する学習・研究を行う学会です。『腎機能別薬剤投与POCKET BOOK』以外にも『腎臓病薬物療法ガイドブック』や『腎臓病薬物療法トレーニングブック』などの書籍を監修しています。
まとめ【腎機能低下を見逃さないための1冊】

『腎機能ポケットブック』は、腎機能低下患者の投与量調整をすぐに確認できる実務書です。
添付文書だけでは判断が難しい場面でも、必要な情報を一冊に集約。
病院・薬局・在宅など、どんな現場でも頼りになる“携帯用バイブル”です。
【本書はどのような本なのか】
・腎機能低下患者の投与量を確認する実務書
・調剤薬局でも院内薬局でも一般的に使用されるほとんどの医薬品が掲載されている
・添付文書に減量後の用量が記載されていない薬の推奨量も掲載されている
・減量が必要ない薬も網羅的に掲載されている
【本書の使い方】
・【基本】腎機能低下がある患者を見逃さない
・80歳以上の患者は腎機能低下患者として扱う
・医師から腎機能の注意喚起がないかを窓口で確認する
・併用薬から腎機能低下を疑うことも可能
【オススメできる人】
・腎機能低下を考慮した処方監査の質・スピードを上げたい薬剤師
・複数の薬局を掛け持ちする薬剤師
・トレーシングレポートで薬剤調整支援料を算定したい薬剤師
・今まで腎機能を意識していなかった薬剤師
・病院で回診・往診同行をする薬剤師
腎機能低下は、高齢患者や多剤併用患者では特に注意が必要です。
本書を活用すれば、処方監査や減薬提案の精度が高まり、現場での判断スピードも向上します。

手元に1冊置いておけば、日々の業務で「腎機能を見逃す」リスクを大幅に減らせます。ぜひ、本書を手に取ってください!
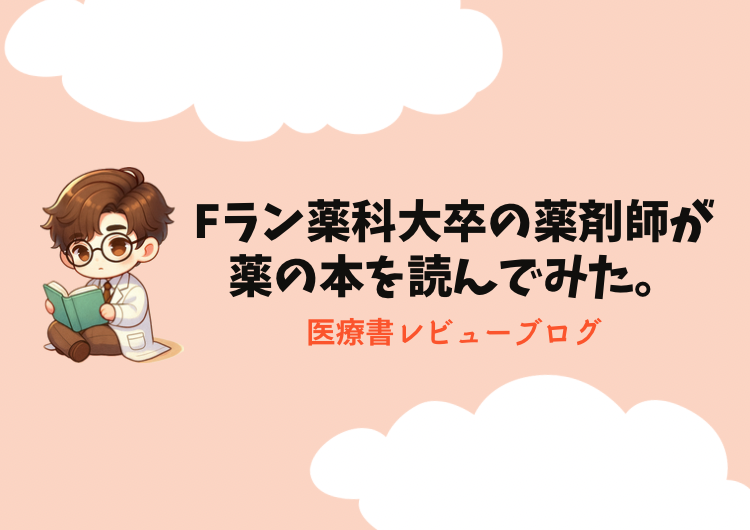
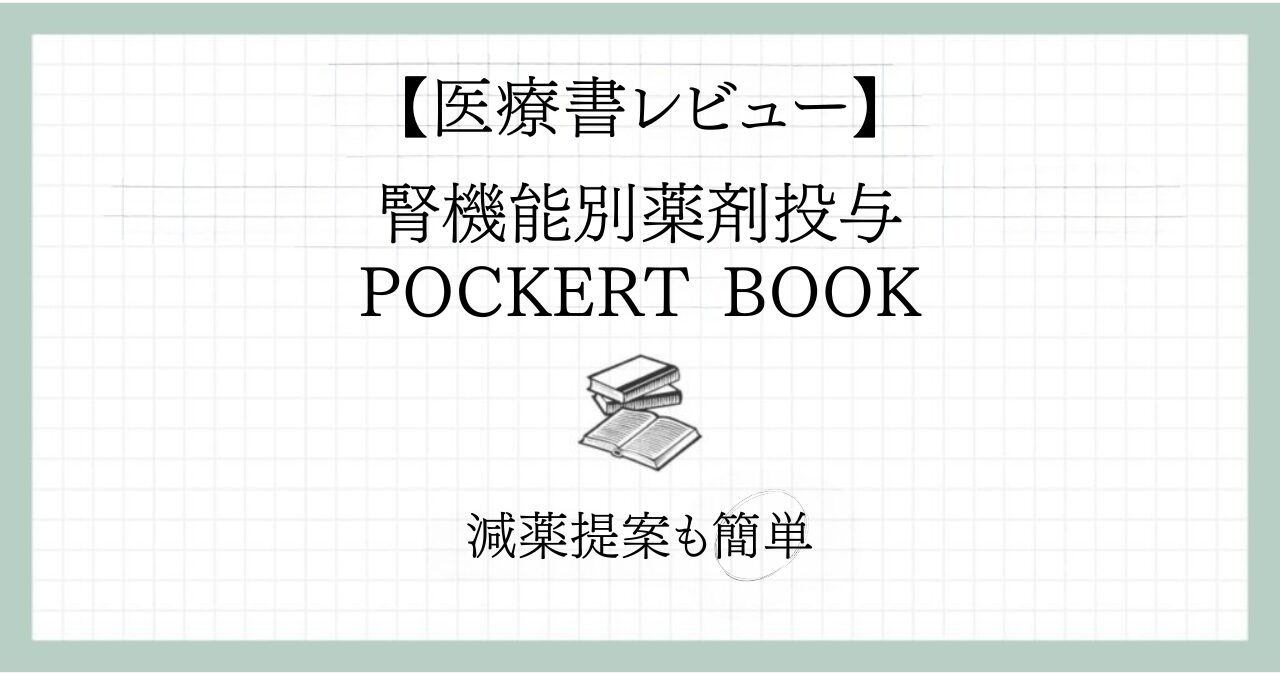


コメント