授乳婦の服薬に関して、どこまで学ぶべきか——
薬剤師として現場に立つ中で、そんなふうに迷うことはありませんか?

「添付文書に授乳中の記載がない」

「ネットの情報があいまい」
結局どう判断すればいいのか悩む場面は多く、本で体系的に学びたいと感じる人も少なくないはずです。
今回は、そんな授乳婦の薬物治療に特化した書籍『授乳婦と薬 第2版』を紹介します。
ただしこの本、正直に言えば“誰にでもオススメできる1冊”ではありません。

読んでみて感じたのは、「徹底的に学びたい」という人にだけ届く、専門性の高い1冊だということ。
ちなみに、妊婦と授乳婦それぞれの薬の安全性をまとめた定番の医薬品集に『薬物治療コンサルテーション 妊娠と授乳 改訂第4版』という書籍があります。

『妊娠と授乳』は、私が「最初にオススメするならこの1冊」と考えている本であり、実際に日々の業務でも愛用しています。
この記事では、本書の特徴や実際の使いやすさ、『妊娠と授乳』との違いを解説しながら、「どんな人に向いているのか」を具体的に紹介していきます。
まず1冊目に手に取るなら別の本を、でも“もっと深く学びたい”と思ったときに選択肢になるかもしれない。
そんな位置づけの本として、本記事を参考にしていただければ幸いです。
| 項目 | 星評価 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価・ オススメ度 | 対象がかなり限定されます。一般的な薬剤師は、授乳婦だけでなく妊婦の薬物治療にも対応する場面が多いですが、本書は妊婦への記載が一切なく、実務上の汎用性は低めです | |
| 実務での 活かしやすさ | 現場で即活用できるツール・工夫が授乳婦に限定すれば、即時性が高く、パッと調べて根拠まで示せる便利な構成。授乳婦からの質問に答えるには非常に使いやすいです。 | |
| 自己学習 への向き | 総論は30ページほどしかなく、内容もかなり専門的で難解です。「これから授乳婦の薬物治療を学ぼう」という初学者には、他にオススメできる本があります。 | |
| 読みやすさ | (総論) (各論) | 総論の文章は専門性が高く、やや堅めの印象。読むのに時間がかかりました。ただしボリューム自体は少ないので、少しずつ読めば最後までたどり着けるはずです。 一方で本書のメインである各論は視認性が高く、構成にも一貫性があり、慣れれば非常に使いやすいと感じました。 |
| コスパ | 税込6,380円。価格は高いです。授乳婦対応を本気で極めたい人には価値がありますが、「ちょっと勉強してみようかな」という軽い気持ちでの購入はやめましょう(苦笑)。 |
『授乳婦と薬 第2版』はどのような本なのか
知識を深めるというより、辞書のように調べて使う本

『授乳婦と薬 第2版』を手に取ってまず感じたのは、「これは読んで学ぶ本というより、現場で使う本だな」という印象でした。
授乳婦の患者さんに薬を投与する際、「この薬って母乳にどのくらい移行するのかな?」とその場で確認したいことは少なくありません。
本書は、そんなときに使える“辞書のような本”です。
特に各論の構成は統一されていて、知りたい情報にすぐアクセスできるよう工夫されています。
また、成分ごとに「添付文書の記載」や「薬物動態」だけでなく、「乳児の曝露量」や「評価コメント」も掲載されています。
判断の根拠をその場で探せるのは大きな利点です。

一方で、自己学習にはあまり向いていないと感じました。
総論にあたる30ページほどのパートは、内容がかなり専門的で、情報も非常に細かいです。
一般的な薬局や病院で働く薬剤師が、そこまで深く授乳婦関連について学ぶ必要があるかといえば、疑問が残ります。
あくまで“調べて使う”ことに特化した構成だと思います。
総論は約30ページ。内容はかなり専門的
『授乳婦と薬 第2版』の総論パートは、全体でおよそ30ページ。
母乳育児の意義から、母乳中への薬物移行、乳児への影響など、5つの章に分かれてかなり詳しく解説されています。
図表も多く視覚的にはわかりやすいのですが、文章そのものは漢字が多く、日本語もかなり堅い印象。
正直に言えば、読み進めるのに少し苦労しました。
たとえば、「定常状態の母体血中薬物濃度」というタイトルで以下のような記載があります。
薬物の血中半減期が比較的長く、母体血中薬物濃度も母乳中薬物濃度も定常状態で安定するため、授乳する時間帯を変えても薬物の母乳移行量がゼロに近づくことはない薬物もある。
薬物(未変化体)と活性代謝物に薬物動態の違いがある場合があるため、それぞれの薬物動態の推移が薬物の母乳移行量に及ぼす影響を評価する必要がある。
(引用:『授乳婦と薬 第2版』一般社団法人 東京都病院薬剤師会 編集、株式会社じほう、2023年、p.20)
専門書なので仕方ない部分もありますが、このような文がズラーっと並んでいます。

私の読解力の低さは一旦置いといて、かなり気合を入れないと読めませんでした。
さらに、上記の続きで、具体例としてリスペリドンの未変化体・活性代謝物の血中濃度の数字が文章として紹介されています。
リスペリドン1mgを経口投与した際の未変化体のTmaxは1.25±0.55時間、活性代謝物のTmaxは2.85±1.76時間、未変化体のCmaxは5.36±2.74 ng/mL、活性代謝物のCmaxは5.10±1.42 ng/mL、未変化体のT1/2は3.01±1.36時間、活性代謝物のT1/2は21.88±4.54時間と報告されている。
本剤を反復投与した際の7日目の未変化体のTmaxは1.1±0.4時間、活性代謝物のTmaxは3.7±2.2時間、未変化体のCmaxは6.94±3.79 ng/mL、活性代謝物のCmaxは9.23±2.86 ng/mL、未変化体のT1/2は4.7±6.0時間、活性代謝物のT1/2は25.1±5.1時間と報告されている。
(引用:『授乳婦と薬 第2版』一般社団法人 東京都病院薬剤師会 編集、株式会社じほう、2023年、第2版、p.20)

読めますか?(苦笑)
情報としては非常に貴重なものですが、とにかく読むのが大変です。
とはいえ、総論パートは全体で約30ページ。
文章は堅いですが、分量としてはそこまで多くありません。
ゆっくり調べながら読んでも、3〜4時間ほどで読み切れるボリュームです。
内容に興味があれば、少しずつ読み進めてみるのもアリかもしれません。
各論は195成分を収録。慣れれば現場で頼れる構成
各論パートには、195成分の医薬品が収録されています。
そして、どの薬も同じ構成で整理されているため、使い方に慣れればとても便利です。
現場でパッと確認したいときにも対応しやすい印象でした。
まず冒頭に、「母乳移行性情報」と「乳児への有害事象情報」が掲載されており、この薬が授乳婦に使えるのかが一目でわかるようになっています。
母乳移行性情報は、おおまかに以下の5段階に分類されています。
• 移行しない
• RID10以下(RID=乳児相対曝露量:母体が摂取した薬のうち、乳児が母乳経由で摂取した割合)
• 情報がないもの
• RID10以上
• ヒト哺乳児に対して明らかな有害事象を有する薬
乳児への有害事象情報は、「報告あり/なし」の2パターンで記載されており、確認に時間がかからず、即時性に優れた構成です。
その後に続く項目も一定の順番で並んでおり、必要な情報にスムーズにアクセスできます。
• 添付文書情報
• 薬物動態
• ヒト母乳への移行に関する情報と乳児への影響
• RID(RID=乳児相対曝露量:母体が摂取した薬のうち、乳児が母乳経由で摂取した割合)
• 情報の評価
• 参考文献
根拠に基づいて評価が記載されているため、なぜ「投与可」なのか、あるいは「慎重に投与すべき」なのか、理由までしっかり確認できる点が非常に好印象でした。
“授乳婦のみ”に特化。妊婦の薬物治療には一切触れていない

本書の大きな特徴のひとつは、内容が「授乳婦」に完全に特化している点です。
妊婦に対する薬物治療に関する記載は、一切ありません。
授乳中に使えるかどうかを確認したいという場面には対応できますが、妊娠中に投与可能かどうかを調べたいときには使えません。
ただ、普通の薬局や病院で働く薬剤師が、「授乳婦の対応はするけど、妊婦の情報は必要ない」という状況はほとんどありません。
授乳婦への対応が必要な薬局では、妊婦への対応も必要になるのが普通です。
産婦人科・婦人科・小児科の処方を受けていれば、妊婦と授乳婦、両方の情報が求められるのは当然のことだと思います。
そう考えると、妊婦と授乳婦の両方をカバーできる書籍のほうが、実務では圧倒的に使い勝手がよいと感じました。
私自身、現場では『妊娠と授乳 改訂第4版』を使っており、授乳婦の情報も含めて、そちらで十分対応できています。

正直なところ、本書『授乳婦と薬 第2版』が必要になる場面はかなり限定的だと感じました。
【『授乳婦と薬 第2版』の感想】メリット・気になった点
ここからは、実際に本書を読んで感じたことを、率直にお伝えします。
よかった点、気になった点の両方がありますが、一言でまとめるなら「使いどころを見極めて選ぶべき本」だと思いました。
特に各論の構成は非常によくできていて、慣れれば現場でも活用できそうです。
一方で、「この本を必要とする人って、どんな人だろう?」と読んでいて少し悩んだのも正直なところでした。
以下に、メリットと気になった点をそれぞれ整理してご紹介します。
各論の構成に慣れれば使いやすく、根拠もすぐ示せる
本書で一番よかった点は、やはり各論の構成です。
どの薬についても、見出しの順番や掲載されている情報が統一されており、使い方に慣れれば、必要な情報にすぐアクセスできます。
「母乳移行性情報」や「乳児への有害事象情報」が冒頭にあることで、この薬が授乳婦に使えるかどうかが、ひと目で判断できます。
分類もシンプルで、即時性に優れた構成だと感じました。
さらに「薬物動態」や「母乳への移行量」、「RID (乳児相対曝露量:母体が摂取した薬のうち、乳児が母乳経由で摂取した割合)」などの数値が示され、その評価や参考文献までセットで掲載されています。
つまり、「なぜその結論に至ったのか?」まで確認できる構成です。
授乳婦に薬を投与する場面では、明確な裏付けがあると、説明に説得力が増します。
調べものとして使うには、かなり信頼できる1冊だと思いました。
(気になった点)オススメできる人がかなり限定的
読んでいて一番気になったのは、「妊婦の薬物治療に一切触れられていない」という点です。
現場で授乳婦に対応する薬剤師の多くは、同時に妊婦への対応も求められます。
そのため、授乳婦の情報“だけ”を知りたいというニーズは、実際にはほとんどないように思いました。
「妊婦の情報は不要で、授乳婦の情報だけ詳しく知りたい人」——
そう言われて、具体的に誰が当てはまるのか?と考えると、正直あまりイメージが湧きません。
あえて挙げるなら、母子保健に特化した職場(保健所や子育て支援センターなど)で、出産後の母親と関わる機会が多い方には需要があるかもしれません。
それでも、そういった現場でも妊婦と接する機会は少なくないと思います。
そう考えると、「使う人がかなり限られる本だな」と感じました。
授乳婦の薬物治療を極めたい人には心強い1冊
授乳婦の薬物治療を深く学べる本ではありますが、実際の現場でここまでの知識が求められることは、ほとんどありません。
正直なところ、本書の総論に書かれているような専門的な内容は、日常業務では出番がないことがほとんどです。

現場対応であれば、『妊娠と授乳 改訂第4版』があれば十分ですし、それで困った経験は一度もありません。
本書を「授乳婦の薬物治療を極めたい人に」と言うこともできますが、それは聞こえのいい表現であって、実際には“ほぼ趣味”の領域だと感じました。
一般的な薬剤師が実務の中で本書の総論の知識を活用する機会はかなり少ないでしょう。
『授乳婦と薬 第2版』をオススメできる人

本書は、すべての薬剤師にとって必須の1冊というわけではありません。
むしろ「この本を必要とする人は、かなり限られる」というのが正直な印象でした。
そこで今回は、どのような立場・目的を持つ方であれば、本書をオススメできるのか整理してみました。
母乳育児支援に深く関わる職種の方(保健所・子育て支援センターなど)
産後のお母さんと日常的に関わる仕事をしている方には、本書の情報が役立つかもしれません。
たとえば、保健所や子育て支援センターなど、授乳期の相談を受ける機会が多い現場では、より詳しい情報が必要になるケースもあると思います。
授乳婦の薬物治療に強い関心がある人
授乳婦への薬物投与について、自分の中でしっかり根拠をもって判断したい。
あるいは、母乳移行や乳児への影響について深く学びたい。
そうした“こだわりを持って掘り下げたい人”にとっては、本書は頼もしい1冊になるかもしれません。
基本的には『妊娠と授乳』で十分と感じる薬剤師が大半
ただし、多くの薬剤師にとっては、妊婦と授乳婦をまとめて確認できる『妊娠と授乳 改訂第4版』があれば十分だと感じると思います。
現場対応を目的とするなら、そちらのほうが汎用性が高く、使いやすいと実感しています。
著者紹介
本書は、一般社団法人 東京都病院薬剤師会が編集を担当しています。
執筆陣には、産婦人科医、小児科医、薬剤師、保健医療の研究者などが名を連ねており、医療・育児支援の現場に深く関わる専門家たちによって作られた一冊です。
母乳育児支援や薬物動態評価に実績のあるメンバーが担当しており、信頼性の高い内容に仕上がっています。
【まとめ】目的が明確な人以外にはあまりオススメしません

最後に、本書『授乳婦と薬 第2版』についてのポイントを整理します。
授乳婦の薬物治療について学べる貴重な1冊ではありますが、本気で深く学びたいという強い気持ちがある方以外には、正直あまりオススメしません。
とはいえ、情報の信頼性や構成のわかりやすさなど、評価できる点も多くあります。
本書の位置づけを確認したい方は、ぜひ以下の内容をご参考ください。
【本書はどのような本なのか】
・授乳婦への薬物投与に特化した現場で辞書的に使う本
・全体約400ページのうち、総論は約30ページ、残りは195成分の各論で構成
・妊婦に関する記載は一切なく、授乳婦のみが対象
【私が本書に感じたこと】
・各論は根拠が明確で使いやすく、即時対応に向いている
・総論は専門性が高く、自己学習にはやや不向き
・実務に必要な情報は『妊娠と授乳 改訂第4版』で十分
【オススメできる人】
・授乳婦の薬物治療に強い関心があり、より深く学びたい人
・保健所や子育て支援センターなどで母乳育児支援に関わる人
・一般的な薬局/病院で働く薬剤師には、あまり必要性を感じない内容
授乳婦対応に関する知識を広げたい気持ちは、薬剤師としてとても大切な姿勢です。
でも、それをどの本で学ぶかは“目的と相性”が重要だと思います。
本書は、明確な目的がある方や強い興味を持っている方向けの専門書です。

「まず授乳婦対応について学びたい」

「よくある質問に答えられるようになりたい」

という段階であれば、『妊娠と授乳 改訂4版』からのスタートを強くオススメします。
→『妊娠と授乳 改訂4版』のレビュー記事は以下のリンクからどうぞ
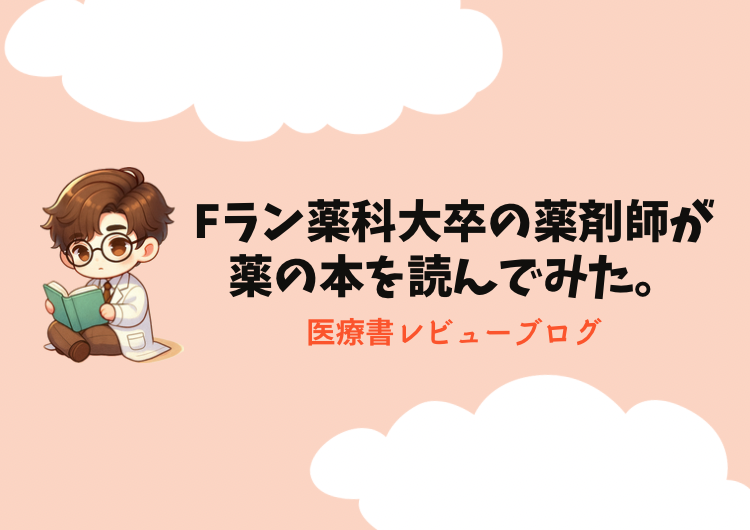
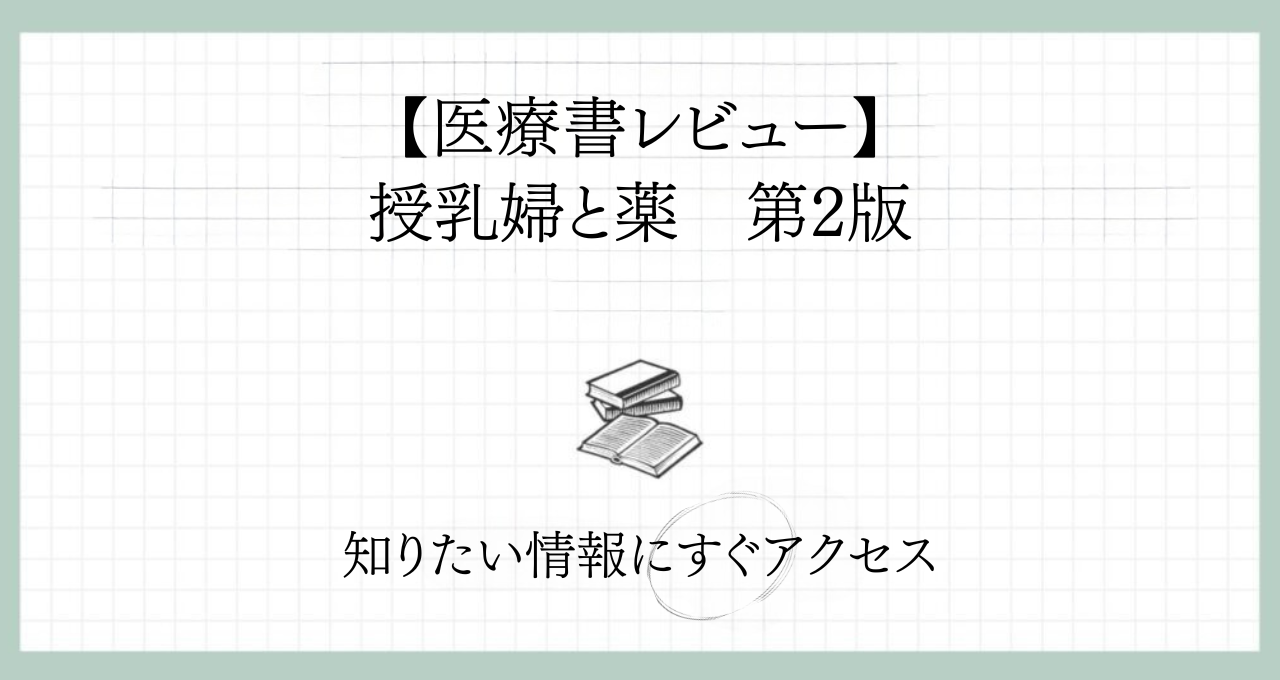



コメント