
小児科の本、どれを選べばいいか分からない・・・。
せっかく買うなら、現場で使えるものが欲しい・・・。

医療書って高いし、失敗したくない…
そんな思いを抱えながらも、“何か勉強したい”という気持ちを持つ薬剤師の方に向けた、医療書比較シリーズです。
本記事では、小児科領域に絞って、4冊の医療書を比較し、「誰に」「どの本が」オススメかを読者別にランキング形式で紹介します。
評価しているのは調剤薬局・病院での実務経験があり、現在は管理薬剤師として働くFラン薬剤師のしん。
「この本を現場でどう活かせるか」という視点から丁寧に読み込み、それぞれの本の特徴や違いを整理しました。
小児科の知識を深めたいすべての薬剤師へ。
この記事を読むことで、あなたに合った1冊がきっと見つかります。
【薬剤師向け】レビュー本の紹介【勉強にも現場にも】

それでは、小児科領域に関する医療書4冊について、それぞれの特徴や活かし方を見ていきましょう。
『極める!小児の服薬指導 改訂版』
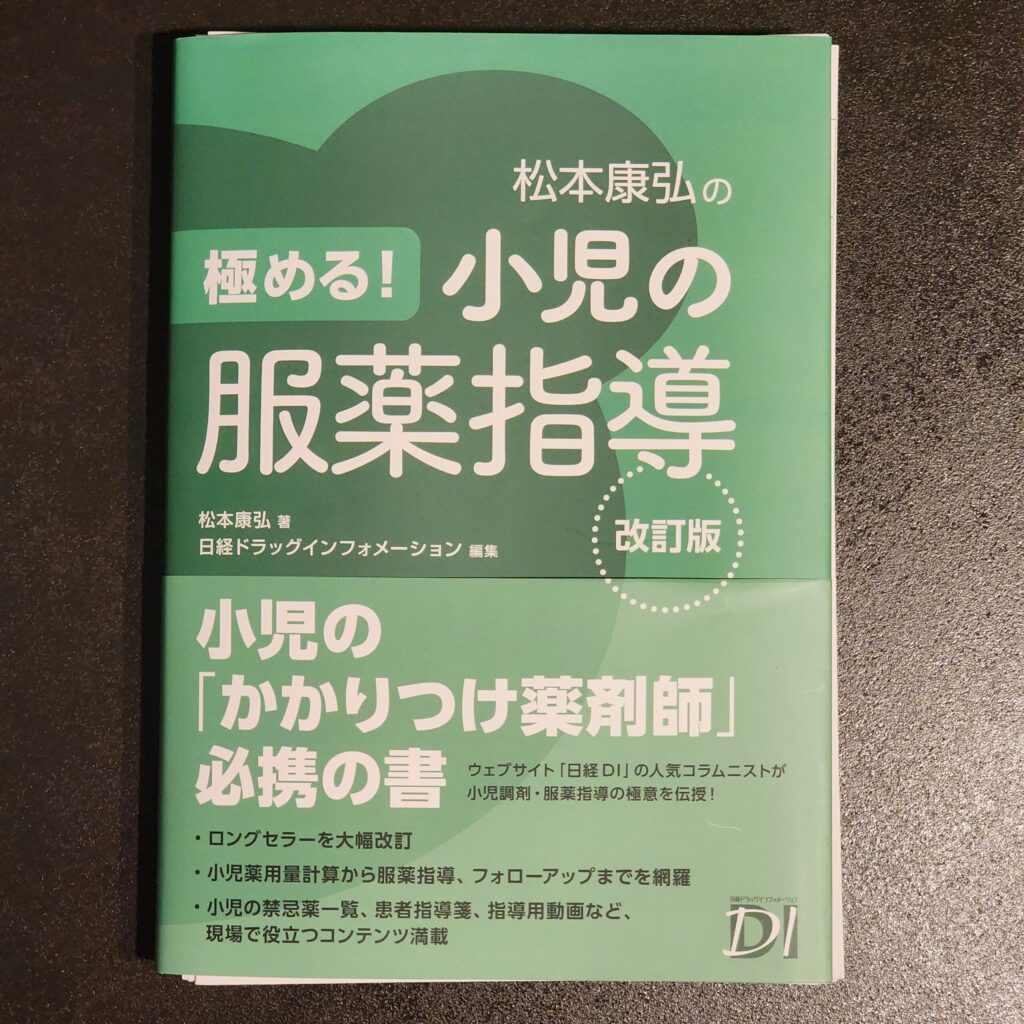
『極める!小児の服薬指導 改訂版』は、著者の豊富な現場経験と試行錯誤の末に生まれた工夫が詰まった1冊です。
何よりも、著者の「子どもや保護者に本気で向き合う」という熱量に圧倒されます。
現場で役立つ実践的な視点が随所に散りばめられており、読むたびに新たな気づきが得られる内容です。
→ 詳しく知りたい方は、下記のレビュー記事をご覧ください。

| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 全薬剤師にオススメできる、実践的な名著 | |
| 実務での活かしやすさ | 現場で即活用できるツール・工夫が満載 | |
| 自己学習への向き | 対応の幅を広げる学び直しに最適な1冊 | |
| 読みやすさ | 丁寧だがボリューム多め、じっくり読みたい本 | |
| コスパ | 税込6,930円。高価だが内容充実、薬局の経費で買えると嬉しい |
自己学習にも現場対応にも使える構成
読み進め型で知識を体系的に学べる。
一覧表やダウンロード可能な指導せんなど、実践で使えるツールが充実。
著者の現場経験と創意工夫が詰まった1冊
感染症ボード、プレパレーション、粉薬の味をまとめた一覧表など、著者の創意工夫が満載。
感染症ボード:保育園や学校単位で流行状況を可視化した著者オリジナルの掲示ボード。流行状況に合わせて医薬品の在庫管理にも活用している。
プレパレーション:フェルト模型や絵本などを使って、治療や服薬の意味を子どもにわかりやすく伝え、不安や恐怖を軽減する取り組み。安心して服薬に臨めるよう支援する工夫。
実務での活用例が豊富
問診票の改善、患者用指導せんの運用、説明の標準化など、すぐに実践できる内容が多数。
管理薬剤師や中堅薬剤師にもオススメ
服薬支援の見直しや、薬局内マニュアルの整備に役立つ視点が多く盛り込まれている。
小児対応に関わる薬剤師すべてに有用
未経験者の入門書としても、経験者の学びなおしとしても活用可能。どんな薬剤師にもオススメできる1冊。
『小児科これだけ』
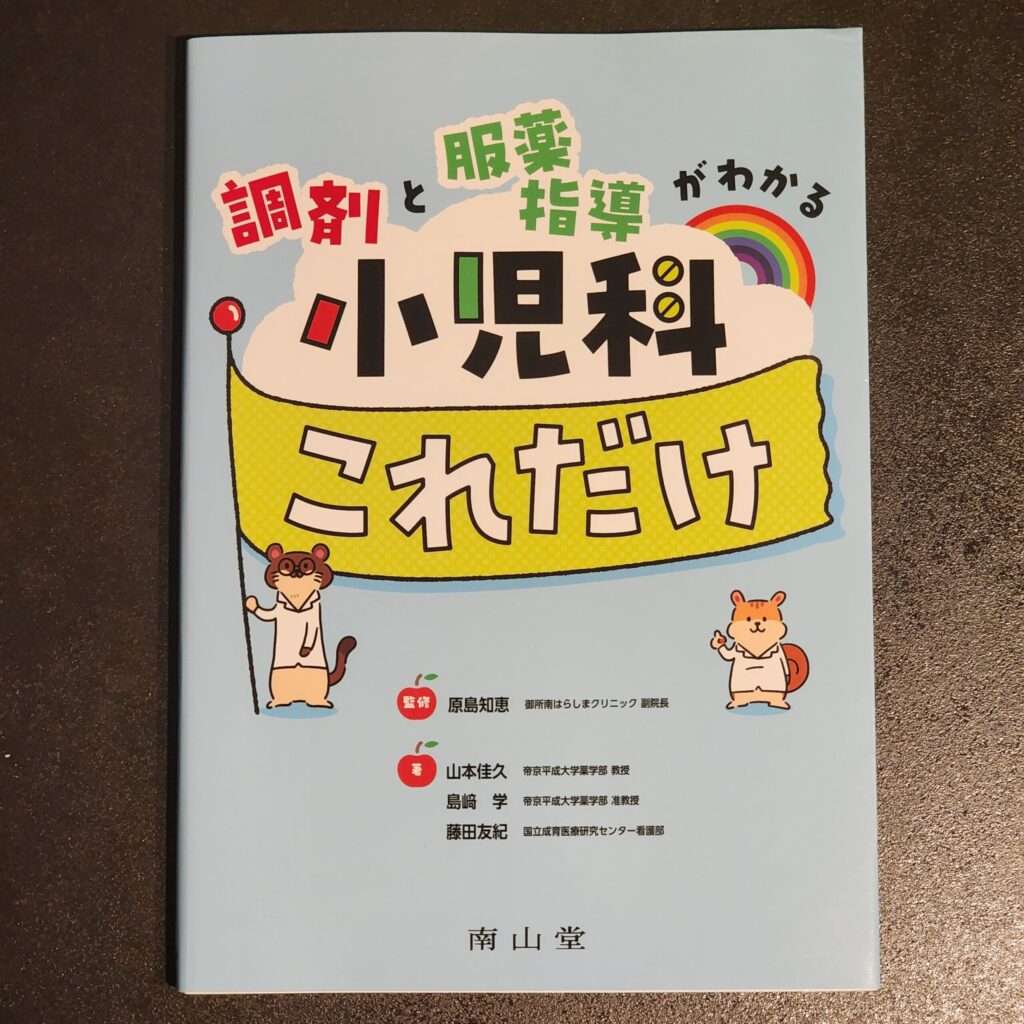
『小児科これだけ』は、小児科の処方せんの見方から、調剤・投薬までの基本をわかりやすく解説してくれる1冊。これまで小児の処方に触れたことがない方や、経験が浅く不安を感じている方でも、基礎から安心して学べる構成になっています。
小児の調剤に苦手意識がある方、自信をつけたい方にオススメの自己学習向け参考書です。
→ 詳しく知りたい方は、こちらのレビュー記事をご覧ください。
| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 初学者には有用。ただし対象が限られる印象 | |
| 実務での活かしやすさ | 薬局常備というより、あくまで参考用・学習用として活用 | |
| 自己学習への向き | 小児科の学習を始めたい薬剤師にぴったりの入門書 | |
| 読みやすさ | わかりやすい文章と適度なボリュームでスラスラ読める | |
| コスパ | 税込2,970円。医療書としてはそれほど高額ではありません。内容は人によって物足りなさを感じることがあるかもしれません |
小児科処方の自己学習に最適な入門書
小児科に苦手意識がある薬剤師や新人に向いており、広く浅く学べる構成。
剤型別・疾患別に整理され、復習しやすい
散剤やシロップ、坐薬などの剤型ごとのポイントや、疾患ごとの服薬指導が簡潔にまとまっている。
早見表や家庭向けチラシの整備に活用できる
水剤の含有量や漢方薬の小児量、苦味のある薬一覧など、現場の整備に応用可能。
経験者よりも初心者にメリットが大きい
すでに現場で小児対応をしている薬剤師にとっては既知の内容が多く、物足りなさを感じる可能性がある。
『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』


小児科の薬、どうやって選ばれているんだろう?

処方の背景まで理解して、医師と連携できる薬剤師になりたい
そう感じたことのある薬剤師の方にこそ手に取ってほしいのが、『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』です。
本書はもともと小児のプライマリケア(初期診療)を担う医師向けに書かれた1冊ですが、薬剤師にとっても、処方の意図や診断背景への理解を深める手がかりになります。
その一方で、内容はかなり専門的です。薬剤師にとっては職能外の領域も多く含まれるため、万人向けというよりは、処方の背景まで深く学びたい上級者向けの1冊です。
→ 詳しく知りたい方は、下記のレビュー記事をご覧ください。
| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 活用できる人にとっては強力だが、対象者は限定的 | |
| 実務での活かしやすさ | 一部情報は現場で使えるが即時活用は難しい | |
| 自己学習への向き | 通読には不向きで、読むには前提知識が必要 | |
| 読みやすさ | 図表は見やすいが、専門用語が多く読解は困難 | |
| コスパ | 税込5,940円。内容と価格が見合うかは活用意欲次第 |

診断から処方までの流れを医師視点で学べる
小児科医がどう診断し、薬を選ぶかの思考プロセスが詳しく解説されている。
「ホームケアのアドバイス」やコラムが薬剤師にも有用
保護者への説明にそのまま使える言い回しや視点が詰まっている。
読み進めるには前提知識が必要で難易度は高い
診療フローチャートや医学用語が多く、調べながら読む姿勢が求められる。
即時活用には不向きだが、復習や知識整理に役立つ
服薬指導後に処方の背景を確認するツールとして活用できる。
医師の考え方を理解したい薬剤師にオススメ
診断や処方の裏にあるロジックを知りたい人にとっては大きな学びになる。
『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』
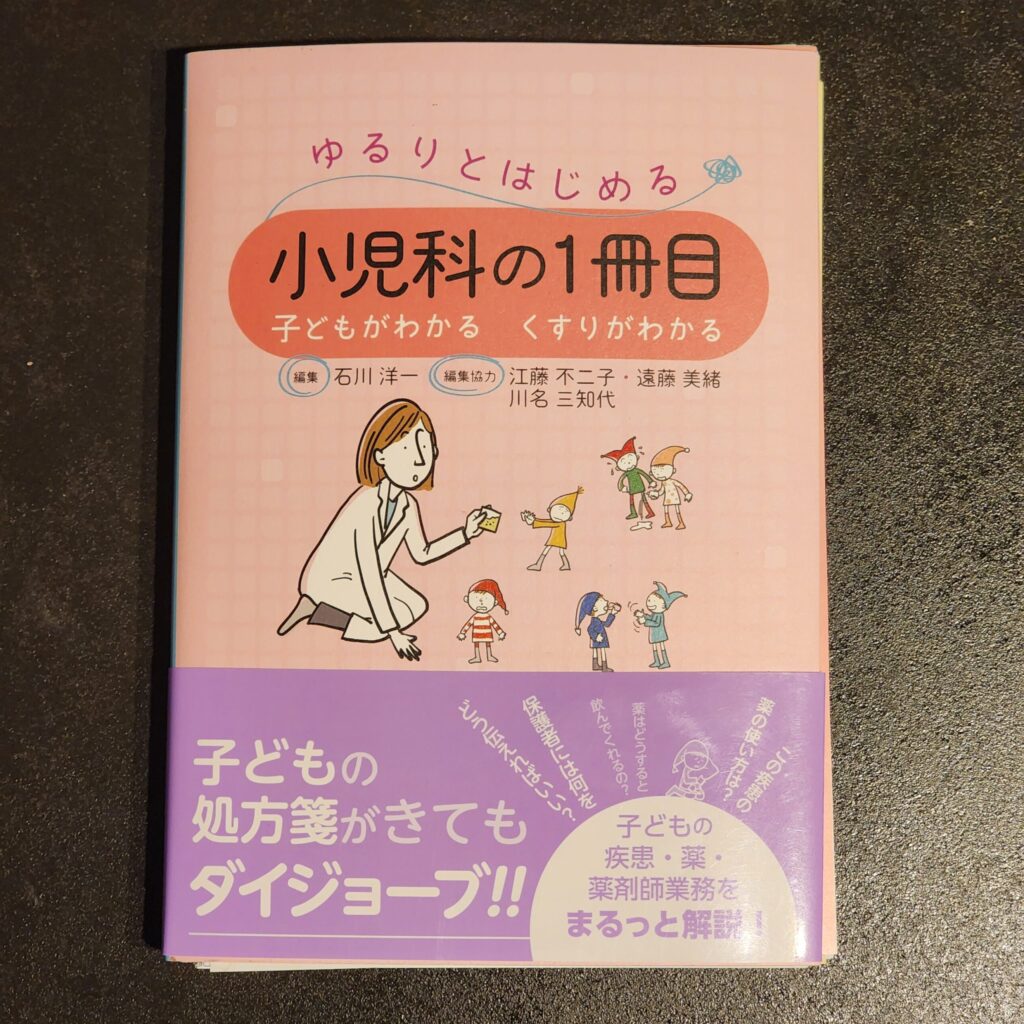
『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』は、小児対応に不安を抱える薬剤師に向けて書かれた、小児対応の実践書です。
“よくある病気を軸”に、病態や治療の背景、服薬指導の工夫、トレーシングレポートの視点までを網羅し、薬剤師が「その場でどう動くか」を具体的に学べる構成になっています。

難しい内容も噛み砕いて解説されており、初学者にも読みやすいです。また、全ページを通読しなくても、自分の立場や業務に合わせて必要なところから学べる柔軟さがあります。
小児に苦手意識がある方や、服薬指導の引き出しを増やしたい方に、まさに最初の1冊としてオススメできる本です。
→ 詳しく知りたい方は、下記のレビュー記事をご覧ください。
| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 小児対応に関わるすべての薬剤師にオススメできる、実践的かつ柔軟な構成の1冊。 | |
| 実務での活かしやすさ | 保護者対応やトレーシングレポートなど、現場でそのまま活用できる情報が充実。 | |
| 自己学習への向き | ボリュームは多いが、症例ベースで学びやすい構成。時間をかけてじっくり学びたい方向け。 | |
| 読みやすさ | 基本的には読みやすいが、章によって文体や言い回しにややバラつきあり。 | |
| コスパ | 税込4,950円でも納得の内容。繰り返し使える知識が詰まった1冊。 |
小児外来の対応力を高められる構成
病態や処方の背景、保護者対応、フォローアップまで、薬剤師の実務に直結する視点を疾患別に解説。
用量表と薬の特徴を分けた早見表が使いやすい
「用量だけ」「特徴も知りたい」それぞれの場面に応じて情報を引きやすいレイアウト。
服薬支援や保護者への説明の工夫が豊富
動画や具体例が充実しており、服薬指導の“引き出し”を増やすのに役立つ。
小児在宅や予防接種・誤飲などにも対応
頻度は少なくても、備えておきたいテーマも幅広くカバー。薬局に1冊置いておくと安心。
現場でも学習でも使える柔軟な実用書
気になる疾患から拾い読みでき、即時性と学習性の両面を兼ね備えている。全ページを読む必要はなし。
【総まとめ】現場で役立つ小児科本、実務・学習・コスパで比較
【小児科本4冊の評価比較表】
| 書籍タイトル | 総合評価・オススメ度 | 実務での活かしやすさ | 自己学習への向き | 読みやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|
| 極める!小児の服薬指導 改訂版 | |||||
| 調剤と服薬指導がわかる 小児科これだけ | |||||
| 小児の薬の選び方・使い方 | |||||
| ゆるりとはじめる 小児科の1冊目 |

勉強意欲の高い薬剤師のあなたに、ひとつだけ伝えたいことがあります。
「もっと学びたい」気持ちを活かすには、“どこで働くか”もとても大切です。
▶︎ 学び続けたい薬剤師のための“転職の考え方”はこちら
総合評価
『極める!小児の服薬指導 改訂版』 と 『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』 の2冊が頭ひとつ抜けてオススメです。どちらも小児科対応に本気で向き合いたい薬剤師にぴったりの内容です。
実務での活かしやすさ
『極める!小児の服薬指導 改訂版』 が薬局全体の効率化まで視野に入れた内容で、管理薬剤師向け。
一方で 『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』 は、自分の服薬指導や対応力を見直したい個人の薬剤師向けにぴったりです。
自己学習への活かしやすさ
『極める!小児の服薬指導 改訂版』 が最適。「こんな薬剤師がいるのか」とモチベーションが上がる内容です。
『調剤と服薬指導がわかる 小児科これだけ』 も基本疾患を体系的に学びやすく、基礎を固めたい方に向いています。
読みやすさ
『調剤と服薬指導がわかる 小児科これだけ』 が最も手頃で、休日に1日で読み切れるボリューム感。
『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』 は上級者向け
医師とディスカッションする際の準備に役立ちます。
【読者別】オススメランキング

小児科の参考書といっても、読む人の立場や経験によって、役立つポイントは変わります。
ここでは、読者別にオススメの本をランキング形式で紹介します。
自分に合った1冊を見つける参考にしてください。
※ランキングタイトルはAmazonのリンクになっています。
新人・復職者向け
第1位:『調剤と服薬指導がわかる 小児科これだけ』

薬剤師になってからあまり勉強をしていない方、どのように勉強を始めたらいいか分からない方の入門書として最適です。
わかりやすい文章と基礎的な内容が魅力で、小児の調剤に不安がある方にぴったり。
実務経験が浅い方でも、外来でよく見かける小児疾患について幅広く学ぶことができます。
第2位:『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』
『極める!小児の服薬指導』も優れた書籍ですが、新人や復職者の方には、必要なところだけをつまみ読みできる『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』をオススメします。
外来で出会った疾患を優先的に復習できる構成で、疾患を軸にした解説が実務に直結。
読みやすさと柔軟な使い方が、新人さんや復職者の方の勉強スタイルに合うのではないかと感じました。
管理薬剤師向け
第1位:『極める!小児の服薬指導 改訂版』
服薬指導にそのまま使える患者用指導せんや一覧表など、薬局全体の業務効率化に活かせる工夫が詰まっています。

筆者の本気度が伝わってくる内容で、管理薬剤師としてのモチベーションも上がります。
個人の学びとしても気づきが多く、視野を広げてくれる1冊です。
第2位:『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』
服薬指導にそのまま使える動画、小児用量の早見表、処方の見方や保護者対応のポイントなど、実務に直結する情報が豊富にまとまっています。
現場での「これどうしよう…」にすぐ答えてくれる内容が多く、スタッフ全体の対応力を底上げするのにも役立ちます。
保険薬局・ドラッグストアの薬剤師向け
第1位:『極める!小児の服薬指導 改訂版』

著者が保険薬局で勤務する薬剤師だからこそ、現場に即した小児対応が具体的に書かれています。
服薬指導や電話対応など、日常業務でそのまま活かせる内容が多く、外来で小児の処方せんを扱う薬剤師にとっては実践的なヒントが満載です。
第2位:『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』
『極める!小児の服薬指導 改訂版』と同様に、外来での小児対応に役立つ内容が豊富です。
疾患別に「その場でどう動くか」を考える構成が、実際の処方にすぐ結びつけやすく、忙しい薬局でも手に取りやすい1冊です。
また、予防接種や誤飲、小児在宅など、日常ではあまり遭遇しないテーマについても丁寧に解説されており、対応機会は少なくても“いざという時に備えておける”安心感があります。
薬局に1冊あると心強いと思います。
病院薬剤師向け
第1位:『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』
基本的な小児科領域の知識に加えて、てんかんや発達障害、在宅医療など、やや専門性の高いテーマも扱われており、幅広い症例に触れることができます。
病院から在宅へ移行する際の視点も含まれており、退院支援や地域連携を意識した薬剤師にとっても参考になる内容です。
第2位:『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』
医師との連携頻度が高い病院薬剤師にとって、診療方針の背景を理解するための一助となる1冊です。

内容は高度ですが、使いこなせば医師との“共通言語”を持つ強みになります。専門性を深めたい薬剤師にこそチャレンジしてほしい本です。
小児の在宅医療に関わる薬剤師向け
第1位:『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』
小児在宅に特化した章があり、薬剤師がどのように関わり、考えて動くべきかを具体的な事例をもとに学べます。
在宅はマニュアル通りに進まないからこそ、本書で紹介される柔軟な対応や考え方が非常に参考になります。
経験が浅い薬剤師でも、「もし自分が関わるならどう動くか」を想像しやすく、在宅の第一歩を踏み出す後押しになる1冊です。
トレーシングレポートを書きたい薬剤師向け
第1位:『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』
7件の具体的なトレーシングレポートが掲載されており、疾患や視点の異なる実例をもとに「どのようなことを、どのように医師へ伝えるか」が学べます。

内容だけでなく、報告の切り口や文面の組み立て方も参考になり、「何を書けばいいか分からない」と悩んでいる薬剤師にとって、最初の一歩を後押ししてくれる構成です。
第2位:『極める!小児の服薬指導 改訂版』
服薬支援の中で、トレーシングレポートにつながる視点が豊富に散りばめられています。個々のエピソードから、どういった情報が医師にとって有益かを考える力が養われます。
『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』に比べるとトレーシングレポートの例は少ないですが、実例も掲載されており、日々の業務の中で“報告につなげられる気づき”を増やすきっかけになる1冊です。
まとめ【薬剤師のあなたに合う1冊は?】

本記事では、小児科に関する4冊の参考書を徹底的に比較・紹介してきました。

それぞれに異なる特徴と強みがあり、「どれが正解か」ではなく、「どんな順番で、どんな目的で読むか」が重要になります。
たとえば、まずは基礎から学びたい方には『小児科これだけ』がぴったりですし、現場での対応力を一気に高めたい方には『極める!小児の服薬指導 改訂版』や『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』がオススメです。
また、処方の背景や医師の意図を深く理解したい方には、『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』が新たな視点を与えてくれるはずです。

大切なのは、自分の立場や悩みに合わせて、今の自分に合った1冊から読み始めてみること。
その1冊が実務の中で「ちょっと変えてみようかな」と思えるヒントをくれるはずです。
ぜひ、気になった本を手に取り、小児対応に向き合う一歩を踏み出してみてください。

知識を活かせるかどうかは、“自分次第”ではなく“環境次第”かもしれません。
もし今の職場に違和感があるなら、一度こちらの記事も読んでみてください。
▶︎ 学び続けたい薬剤師のための“転職の考え方”はこちら
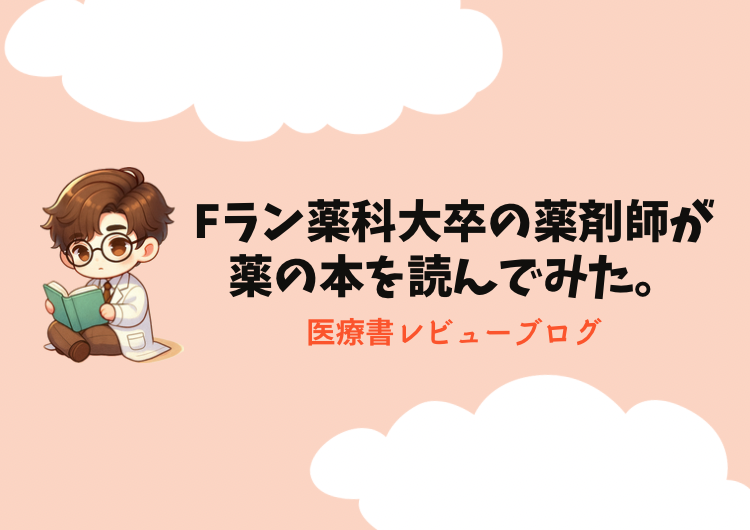
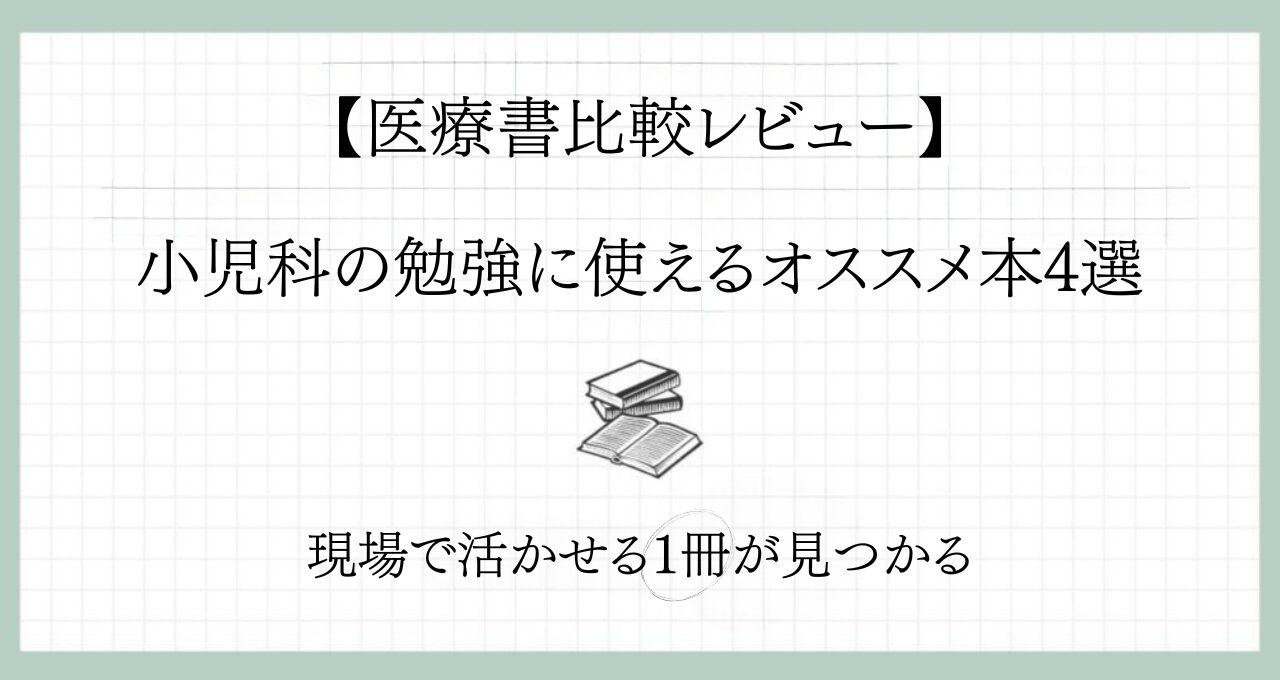



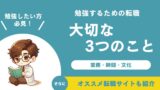
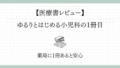

コメント