
先生から特に説明がなく、薬だけ出されました
保護者からそんな声を聞いたことはありませんか?
薬剤師として何か伝えたいけれど、診断内容が分からず説明に悩んでしまう——そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。

今回は『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』をレビューします。

本書は、小児科の初期診療に携わる医師が、症状や疾患に応じて診断を進め、適切な治療薬を選択するための実践的なガイドブックです。
薬剤師は診断を行うことはできません。しかし、医師がどのように診断し、どのように治療方針を決めているか——その流れを知ることで、服薬指導に説得力を持たせられる場面もあります。
本書には、患者や保護者への説明にそのまま使える表現やアドバイスが含まれています。また、医師が実際の診療現場でどのように患者と向き合っているかがわかるようなコラムもあり、薬剤師にとっても参考になる点が多いです。

なお、本書の内容は医師を対象にしています。
薬剤師の立場からレビューすることで、著者の意図とは異なる視点や解釈が含まれてしまうかもしれません。
その点につきましては、あらかじめご容赦いただければ幸いです。
この記事では、本書の構成や特徴を薬剤師目線で整理し、「どのような場面で役立てられるか」「読むことでどんな力が身につくか」を考察していきます。
読者の皆さまが、ご自身の実務にどう活かせそうかを考えるヒントになれば嬉しいです。
| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 本書を薬剤師の学びに活かせる人は限られる印象です。ただし、調剤室に置き、日々の業務で使うことを習慣化できれば、とんでもないスピードで成長できると思います。使いこなせるようになれば非常に強力な武器になります。 | |
| 実務での活かしやすさ | 「ホームケアのアドバイス」や「小児科医からひとこと」など、患者への説明にすぐ使える情報も含まれています。辞書的に使う本なので、むしろ実務の中でこそ活かされる構成です。 | |
| 自己学習への向き | 全文を読んで内容を覚えるのは難易度が高すぎますし、そもそも薬剤師の職能外の記述が大半を占めます。薬剤師の自己学習用の書籍としてはあまり向いていません。 | |
| 読みやすさ | 図表や構成は整っており、視覚的には読みやすい印象です。ただし専門用語が多く、調べながらでないと読み進めるのは難しいです。調べながら読むのが必須なので、周辺知識も広がる良い教材になるかもしれません。 | |
| コスパ | 税込5,940円。個人で購入するにはやや高めの価格設定です。内容が高度なため、購入しても読みこなせず、そのまま手に取られないままになってしまう薬剤師も多いかもしれません。コストに見合うかは、その人次第で大きく左右される1冊です。 |

『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』はどのような本なのか【診断・処方をサポートする医師向けの実用書】

本書は、小児の症状に対してどのように診断を進め、どの治療薬を選ぶかを整理した、医師向けの実用書です。
診療フローチャートや処方例が豊富で、初期対応に悩む小児科医の判断を支える構成になっています。
薬剤師が読むには職能外の内容も多いですが、処方の背景を知るヒントとして活用できる場面もあります。
小児科の初期治療に携わる医師の選択肢を整理した実践的な1冊
本書は、小児科の診療現場において「どのように診断を進め、どの薬を選ぶか」を明確に整理した、医師向けの実践書です。
構成は大きく「総論」と「各論」に分かれており、総論では小児科医としての基本姿勢や処方の考え方、薬の剤形や相互作用といった基礎知識がまとめられています。一方、各論では「症状別」と「疾患別」に分かれ、それぞれの項目について診断に必要な情報、診療フローチャート、治療薬の選択肢、保護者への説明内容までが丁寧に記載されています。
診療現場を想定した具体的な処方例も多数掲載されています。「どこまでが外来対応で、どこからが入院・専門医へのコンサルトを要するか」といった線引きも明記されており、診療の判断に迷う場面での参考になります。

どの層の医師にとって特に有用かは薬剤師の私には判断しかねますが、初期対応の整理や判断の確認に役立つ実用的な構成だと感じました。
診断できない薬剤師にとっては、読めるパートが限られる
薬剤師は診断ができない立場であるため、本書に記載されている「症状から診断へのアプローチ」や「治療方針の決定」に関する内容は、直接的な実務には活かしづらい部分もあります。
特に、各論におけるフローチャートや診察・検査所見の読み取りに関する記述は、医師の診療プロセスを想定して書かれており、薬剤師がそのまま実務に取り入れることは難しいと感じました。
ただし、患者から疾患名を聞き取ったあとにその疾患の知識を深めたり、処方された薬の背景を学びたい場合には、参考になるパートもあります。とくに「ホームケアのアドバイス」や「小児科医からひとこと」といったコラム部分は、薬剤師が服薬指導や患者対応で参考にできる場面があります。
すべてを通読しようとすると難易度の高さを感じますが、「一部を拾い読みしながら、必要に応じて活用する」というスタンスであれば、薬剤師にとっても一定の価値がある1冊です。
『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』を薬剤師が活用するには【現場で“繰り返し引いて学ぶ”】
本書は、診断や治療方針の選択といった医師向けの内容を中心に構成されており、薬剤師がすべてを読みこなすには高いハードルがあります。
しかし、読める範囲が限られているからこそ、本書を日々の業務で繰り返し使いながら少しずつ身につけていく——そんな地道な積み重ねが、薬剤師としての“引き出し”や“視点”を確実に広げてくれます。
本書を使いこなせる薬剤師は、確実に現場での対応力に差が出てくるはずです。

ここからは、薬剤師が本書をどのように日常業務に取り入れていけるかをご紹介します。
投薬指導後に確認・復習するツールとして活用
診断や治療薬の選択に関する情報が中心の本書は、服薬指導中に活用するイメージがあまり湧きません。服薬指導中の即時活用には不向きな内容です。
患者にとって必要なのは「どのような薬なのか」や「薬の使い方」、「生活上の注意点」などです。「処方医の意図」や「なぜこの薬が選ばれたのか」といった情報を、薬剤師が説明することは本質的ではありません。薬剤師が重視すべきは、患者にとって実用的な情報の提供です。

そのため、本書を開くタイミングとして現実的なのは、投薬指導が終わった後の復習や補足知識の確認の際が適していると感じました。
患者から聞き取った病名や症状をもとに、「この疾患にはどのように診断するのか」「他に治療選択肢があるのか」を確認したり、医師の考え方を自分なりに整理する時間に使うのが効果的です。
その場での即応力というよりは、日々の業務で知識をつけていくための学習ツールとして、力を発揮する1冊です。
「ホームケアのアドバイス」「小児科医からひとこと」が服薬指導に役立つ
本書の中でも、薬剤師にとって特に有用なのが「ホームケアのアドバイス」と「小児科医からひとこと」のパートです。
「ホームケアのアドバイス」では、それぞれの疾患・症状について、患児や保護者が自宅でどのように過ごせばよいかが示されています。具体的な生活上の注意点やケアの方法が簡潔にまとめられています。

文言もそのままで伝えやすく、服薬指導の際に説明内容として非常に使いやすいと感じました。
前の項目で「服薬指導中に本書を活用するのは現実的ではない」と述べましたが、すべての場面で使えないわけではありません。
例えば、患者から病名を聞き取った際に「医師からの説明があまりなかった」といった声があれば、一度指導を中断し、調剤室で本書を開いてアドバイス内容を確認するのは十分に現実的です。

限られた時間の中でも、本書を活用できる場面は確かに存在し、服薬指導の質を高められます。
一読して学ぶというより、「使って身につける」タイプの本
私は本書を最初から最後まで通して読みました。
ですが、読み終えた直後に「この本には何が書いてあったっけ?」と振り返っても、ほとんど思い出せませんでした。一読して覚えられる本ではありません。
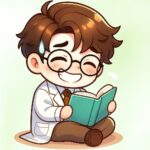
おそらく、私の理解力や記憶力の問題もあるとは思います。
ただ、正直なところ、この本を一読してしっかり内容を定着できる薬剤師がどれだけいるのか——
そう感じてしまうほど、内容は専門的で、情報量も多く、読解にもエネルギーを要する1冊です。
だからこそ、本書は「読み切って覚える本」ではなく、現場で何度も繰り返し使う中で、少しずつ身につけていくタイプの本だと思います。
勤務する薬局によって、出会う疾患にも偏りがあります。
繰り返し本書を開く疾患や、日常でよく出会う疾患については、自然と知識が定着していく。
そんな積み上げ型の学びに適した1冊です。
『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』を薬剤師が読んだ感想と気になった点
本書はあくまで医師向けに書かれた専門書であり、薬剤師が読みこなすには難しさを感じる部分も多くあります。

そのうえで、薬剤師の立場から見たときに「これは参考になった」と思える点もあれば、「ここは読みにくい」と感じた点もありました。
ここでは、あくまで薬剤師として本書を実際に読んだ立場から、良かった点と気になった点を整理してご紹介します。
【薬剤師視点】『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』の良い点
医師がどのように薬を選んでいるかの“考え方”を知るヒントになる
病院薬剤師であれば、医師と直接やり取りをする機会があり、処方意図や治療方針について質問できる場面もあるかもしれません。

一方で、保険薬局やドラッグストアに勤務する薬剤師は医師と接する機会がほとんどなく、処方の背景を知ることは難しいです。
本書には、医師が症状や診断に応じて、どのように治療薬を選んでいくのかが具体的に記載されており、処方の裏にある“思考の流れ”を学ぶヒントが詰まっています。
処方意図を勝手に推測することはできませんが、「こういう考え方があるのか」と知っておくことで、処方せんに対する理解や服薬指導の説得力が変わってくると思います。
処方意図を完全に理解することはできなくても、その考え方を学ぶのは薬剤師としての幅を広げることができると感じます。
見やすいレイアウト・シンプルな構成
本書は「症状別」と「疾患別」に分かれており、目的に応じて検索しやすい点も実務において助かります。

図表も多く視覚的に整理されているため、内容の専門性に対して、引きやすく・調べやすい1冊だと感じました。
また、どの疾患・症状についても「疾患の概要→診断アプローチ→処方例→ホームケアのアドバイス」という流れで統一されており、構成が非常にシンプルです。
ページごとに構成が変わることがなく、読み慣れるほどに情報が探しやすくなります。
代表的な薬剤については簡易的な用量記載があり、小児用量の確認にも活用できる。
本書には、薬効別に小児用量をまとめた一覧表が掲載されており、代表的な薬剤については体重あたりの用量などが簡潔に記載されています。
収載されている薬剤は限定的ですが、よく使う薬が押さえられており、日常的な小児用量の確認には十分活用できる内容です。

ただし、情報はあくまで簡潔にまとめられており、本書だけですべての小児用量をカバーするのは難しいと感じました。
網羅的に用量を確認したい場合には、『実践 小児薬用量ガイド』(じほう)や『新 小児薬用量』(診断と治療社)といった、小児用量に特化した書籍の併用が適しています。
本書の位置づけとしては、診療の流れを理解する中で、代表的な薬の用量をざっくり確認するための参考資料という印象です。
【薬剤師視点】『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』の気になった点
専門用語が多く、前提知識も求められる。調べながらでないと読み進められない
以下は、本書「夜尿」の章に掲載されている記述の一部です。
<夜尿アラーム療法>
・夜間睡眠中、膀胱充満時に覚醒させることにより、患児の未熟な排尿反射抑制神経回路を強化する条件付け療法と考えられている。
・夜尿アラーム療法の治癒率は約70%で、再発率は約15%程度であるが、治療脱落率は薬物療法より10~30%高い。
・夜尿が1週間に3回以上で、患児および親・保護者が治療に対して積極的である場合が適応になる。効果を認めるまで数カ月以上かかるケースが多いことをあらかじめ伝えておく。
(引用:『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』南山堂、2020年、p.168)
<夜尿アラーム療法の実際>
国際小児尿禁制学会(International Childrens Continence Society:ICCS)の診療ガイドラインによれば、夜尿アラームの警報音が鳴ったときに親・保護者は患児を完全に覚醒させてトイレで排尿させ、再度アラームセンサーを装着させることを勧めている。しかし、親・保護者にとっては睡眠不足になり、その結果として治療から脱落してしまう原因となる。筆者らの検討では、夜尿アラームが鳴った際に覚醒させなくても覚醒した場合と比較して治療効果は遜色ないため、「夜尿アラームが鳴っても起こさなくてよい」と指導している。
(引用:『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』南山堂、2020年、p.169)
ここまでが、本書に記載されている夜尿アラーム療法に関する記述です。
正直、これを読んだだけで内容を理解し、夜尿アラームを使用しているお子さんの保護者に適切なアドバイスができる薬剤師が、どれだけいるでしょうか?

「膀胱充満時に覚醒させる」ってことは、膀胱の状態を感知して尿量を測れるようなセンサーがあるのかな?

アラームが鳴っても起こさなくていい、覚醒した時と治療効果が遜色ないって…じゃあ、何のためのアラームなんだ?
私の読解力が低いのは一旦置いといて…夜尿アラーム療法について調べてみました。
夜尿アラーム療法とは夜尿症の子どもに対して行われる習慣づけの治療法です。
患児の下着やパジャマに小型のセンサーを取り付け、おしっこが出始めた瞬間にアラーム音が鳴る仕組みになっています。
このアラームによって脳を刺激し、「夜中に尿意を感じたら起きる」という反射を体に覚えさせていく、いわば条件反射のトレーニングです。
つまり、おねしょをした瞬間にアラームが鳴るセンサーを装着し、その刺激で「起きる練習」を毎晩繰り返すことで、次第に“尿意で自然に目が覚める”ようにしていく——それがこの療法の仕組みです。
…ですが、私の中にはまだ疑問が残ります。

そんなセンサーがなくても、おねしょをすればその刺激で起きるでしょ。気持ち悪いもん。
でも、実際にはおしっこをしても全く目が覚めない子どもたちが多くいるそうです。
濡れていることにすら気づかずに朝までぐっすり眠っている——これが夜尿症の特徴のひとつだと知りました。
そこで登場するのが夜尿アラーム。
おねしょが始まったタイミングでアラームが鳴ることで、「あ、出ちゃった!」という“気づき”を毎晩のように経験し、体に「おしっこが出そうなときは目を覚ます」という習慣を身につけさせることが、この療法の目的です。
つまり、ただ濡れるのを待つだけでは足りず、強い刺激(アラーム音)で脳にしっかり知らせることが大切なのです。
そして再び、本書の説明に戻ります。
筆者らの検討では、夜尿アラームが鳴った際に覚醒させなくても覚醒した場合と比較して治療効果は遜色ないため、「夜尿アラームが鳴っても起こさなくてよい」と指導している。
(引用:『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』南山堂、2020年、p.169)
もともと夜尿アラーム療法では「アラームが鳴ったら起こしてトイレに行かせる」が基本でした。
これは、“排尿”と“起床”を結びつけることで、排尿コントロールの発達を促すためです。
ところが最近では、「覚醒させなくても脳が音に反応していれば効果は変わらない」という報告が増えてきています。
つまり、アラームの目的は“起こすこと”ではなく、“排尿のタイミングで脳を刺激すること”。
音による刺激が脳に届いていれば、意識が完全に覚醒しなくても治療効果は期待できるのです。
小児科の医師であれば、こうした知識が前提にあるため、本書の記述を読んだだけでも十分に理解できるのだと思います。

でも、私のように夜尿アラームについての前提知識がない薬剤師にとっては、本書の文章を読むだけでは理解が難しく、調べながらでないと読み進めることができません。
ただ私は今回、この点を“気になった点”として挙げましたが、見方を変えればある意味メリットだとも思っています。
知らない用語に出会い、つまずき、調べることで、結果的に知識の幅が広がる——能動的な姿勢こそが、学びの本質だと思います。
わからないことに出会ったときに立ち止まらず、自分から知識を取りにいく。
その積み重ねが、薬剤師としての成長につながるはずです。
執筆者が多く、単元によって文章の読みやすさや文体にばらつきがある
本書は多くの小児科医が執筆に関わっており、その専門性の高さが魅力の一つです。
一方で、執筆者ごとに文章のスタイルや語り口に違いがあり、章によって読みやすさにばらつきを感じました。

ある章ではスムーズに読み進められたのに、別の章では言い回しが硬く感じたり、情報が整理されていなかったりして、読みにくさを感じる場面もありました。
とはいえ、「この単元は全く意味がわからない」というほどではありません。
ただ、専門用語が多く使われている章では、読み進めるのに苦労する場面もあります。
診断や治療選択に関する記載が中心で、薬剤師の職能外の情報が多い
本書は、小児科医が診断を確定し、治療薬を選ぶためのプロセスに重点を置いた実用書です。
症状の聞き取り方、診察所見の確認、検査、治療の進め方など、医師の判断を支える情報が豊富に掲載されています。
薬剤師は診断を行えないため、内容の多くは職能の範囲外にあたります。
そのため、「すぐに現場で使える情報」を期待すると、ギャップを感じるかもしれません。
一方で、医師の処方意図を想像する力を養うには、有益な1冊です。

この本を通じて、薬剤師としての視野が広がると感じました。
ただし、あくまで医師向けの本です。前提を理解せずに購入すると、「思っていた内容と違った」と感じる可能性があります。
医師の考え方を学びたい薬剤師にこそ、読んでほしい本だと思います。
服薬支援や調剤業務に直結する情報は少ない

繰り返しになりますが、本書は医師向けの実用書です。薬剤師の調剤業務や服薬支援に直接役立つ情報は多くありません。
一部、患者対応に活かせる記述もありますが、基本的には処方の背景を“間接的に学ぶ”ための内容です。
調剤業務の参考には『小児科これだけ』、服薬支援の実践には『極める!小児の服薬指導』が特に役立ちます。
いずれも当ブログで紹介していますので、あわせてご覧ください。
この前提を理解した上で購入すれば、視野を広げる貴重な学びになります。

前提を意識して購入してほしい1冊です。
『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』をオススメできる人
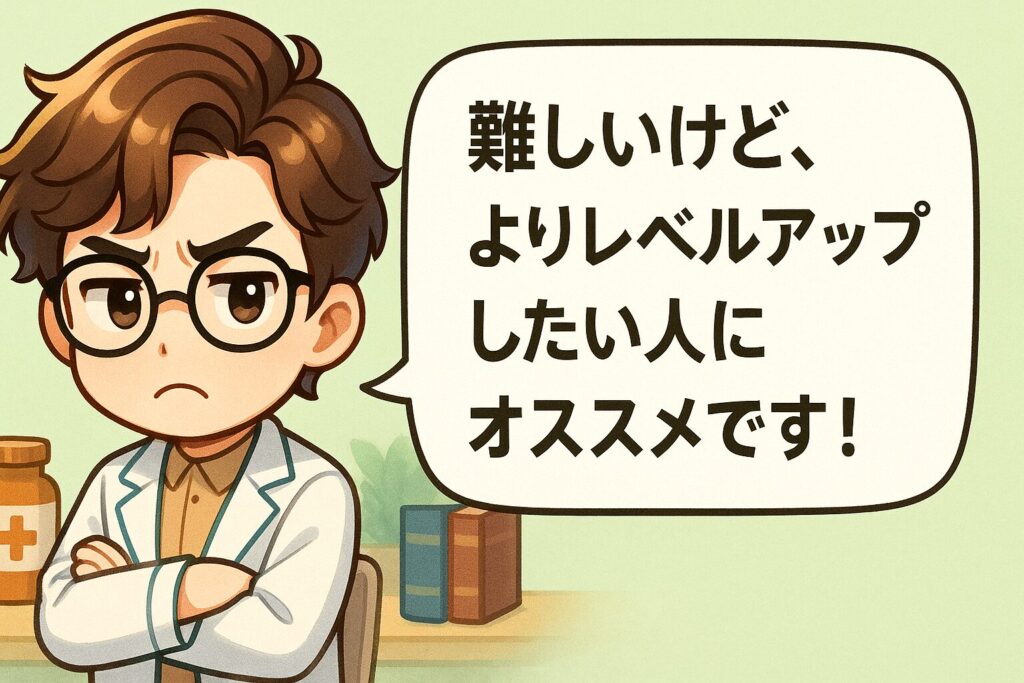
処方の背景を理解し、患者対応の幅を広げたい薬剤師
薬の使い方だけでなく、「なぜこの薬が選ばれたのか」という背景まで理解したい薬剤師には、本書は大きな学びを与えてくれます。
診断や治療選択に関する情報が豊富に掲載されており、処方意図を想像する力や、疾患ごとの基本的な診断の考え方を知れます。
結果として、患者からの質問にもより柔軟に対応できるようになり、服薬指導の質や説得力が向上します。
勉強意欲が高く、医師との連携や服薬支援のレベルを上げたい薬剤師

正直なところ、本書は薬剤師に強くオススメできる本ではありません。
診断や治療方針の決定など、薬剤師の職能を超える内容が大部分を占めており、通読するには専門知識と根気が必要です。
それでも、勉強意欲が高く、医師との連携や服薬支援の質を高めたいと考えている薬剤師にとっては、得られるものも多い1冊です。
診断から処方までの流れを知ることで、医師の考え方に対する理解が深まり、現場での対応力や視野の広がりにつながると思います。
本書は、薬剤師が“そのまま活用する”ための本ではありません。

あくまで医師向けの本であることを前提としつつ、薬剤師として参考にできる部分を見つけていくという読み方が適していると感じました。
著者紹介
本書は、全国の小児科医25名が執筆を担当し、それぞれの専門領域に基づいた内容がまとめられています。
編集は以下の4名の医師が担当しています。
【横田俊平先生(横浜市立大学名誉教授/東京福祉大学社会福祉学部教授)】
横浜市立大学医学部小児科教授を歴任。日本小児リウマチ学会理事長などを務める。初版から編集に携わっており、本書の総監修を担う。
専門:小児リウマチ学、小児感染症学、小児アレルギー学、免疫学など
【田原卓浩先生(たはらクリニック院長)】
大学病院・国立病院勤務を経て、2003年に小児科クリニックを開業。日本小児科医会副会長、山口県小児科医会会長を歴任。
専門:地域総合小児医療
【加藤英治先生(福井県済生会病院顧問)】
福井県済生会病院で小児科医長、副院長などを歴任。
専門:小児科総合診療、小児腎臓
【井上信明先生(国立国際医療研究センター 国際医療協力局)】
国内外で小児救急・感染症の研修・診療に従事。東京都立小児総合医療センター救命救急科医長を経て現職。
専門:小児救急、国際保健
まとめ【内容が高度で、上級者向け】
『小児の薬の選び方・使い方 改訂5版』は、薬剤師にとって「すぐ使える本」ではありません。そして難しい。
しかし、だからこそ得られる学びがあります。診断や治療の背景を知ることは、薬剤師の職能の幅を広げることに繋がります。
最後に、本書で得られる学びと、どんな薬剤師にオススメなのかを整理します。
【本書で学べること】
・小児科医が診断から治療薬を選ぶまでの思考プロセス
・症状・疾患別の診断アプローチと処方の流れ
・「ホームケアのアドバイス」や「小児科医からひとこと」による現場での伝え方
・代表的な小児薬の簡易用量(薬効別一覧表)
【薬剤師として本書を活かすには】
・疾患を聞き取った時に、その疾患について本書で調べる習慣をつくる
・日常業務の中で学んでいくという意識づけに活用する
・難しい内容に出会ったら、調べながら読み進めること自体を学びに変える
【オススメできる薬剤師】
・処方の背景を理解し、薬剤師業務の質を高めたい方
・勉強意欲が高く、診断のプロセスに関心がある薬剤師

医師向けの本であることを前提に、「あくまで参考書として使う」という姿勢で向き合えば、薬剤師としての視野を広げてくれる1冊です。
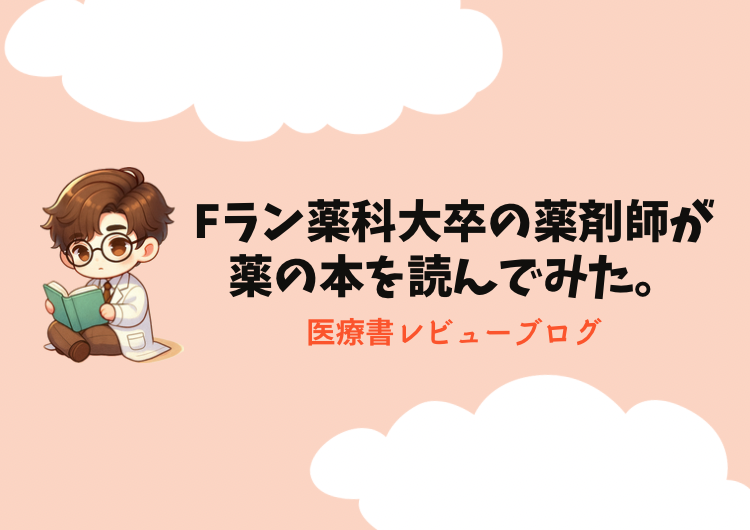
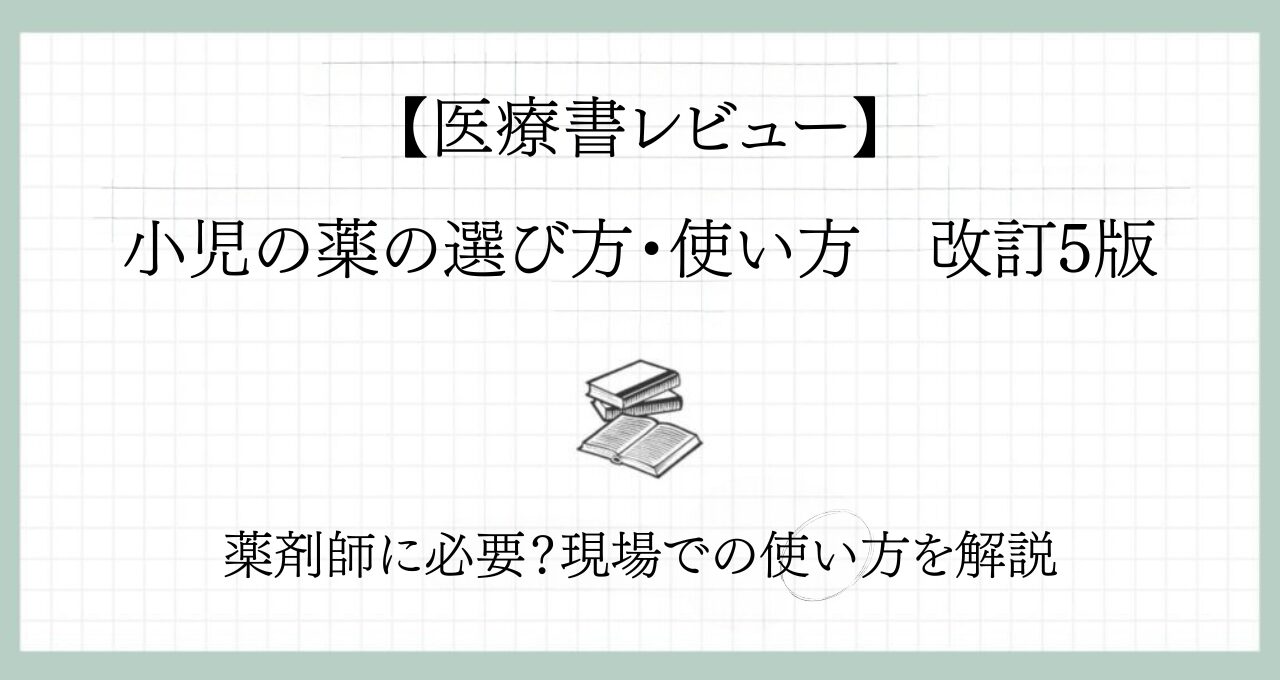



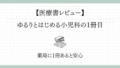
コメント