あなたは循環器領域の勉強をしていますか?

「循環器の薬ならけっこう自信がある」

「門前が循環器クリニックだから、抗血栓薬や心不全治療薬は毎日のように扱っている」

「循環器病棟を担当していて、自分でもガイドラインや専門書を読み込んでいる」
そんなふうに、日頃から循環器の薬や病態に触れ、自己学習にも前向きな薬剤師の方にこそオススメしたい1冊があります。
それが、今回ご紹介する『循環器薬ドリル』です。
本書は、循環器を専門とする医師が研修医向けに執筆した症例ベースの問題・解説集。
臨床現場さながらのリアルな症例が多数収録されており、薬の知識だけでは解けない問いが並びます。
「病態・治療戦略・検査値をどう読むか」といった、実践的な視点が求められる内容です。
このレビューでは、現役薬剤師として本書を読み切った私の感想に加え、実際にこの本の知識を活かして書いたトレーシングレポートの実例も紹介します。
循環器にある程度自信のある方には、新たな視点と知識のアップデートを。

そして、私のように循環器領域に自信がないという方にも、「調べながら読み進めれば、十分ついていける」内容なので、ぜひチャレンジしてほしいです。
| 項目 | 星評価 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 医師向けの問題・解説集ですが、薬剤師でも読める内容です。上級者向けであることは間違いなく、薬剤師全体にオススメできる本ではありません。ただし、循環器領域を本気で学びたい方にとっては、間違いなく良書です。 | |
| 実務での 活かしやすさ | 自己学習用の問題・解説集であり、業務中に本書を開くような使い方は想定しづらいです。一部の内容はトレーシングレポートの根拠にできますが、基本的には現場向きというより自己学習用です。 | |
| 自己学習 への向き | 専門用語や略語が多く、薬剤師の職能範囲を超える内容も含まれます。調べながら読むことが前提となるため、通勤中にさらっと読むのは難しく、自宅など腰を据えて学べる環境でこそ力を発揮します。 | |
| 読みやすさ | 文章構成や日本語は丁寧ですが、内容の専門性が高く、スラスラ読める本ではありません。わからない部分を調べながら読み進める必要があるため、低めの評価です。 | |
| コスパ | 税込4,950円。医療書としては標準〜やや高めの価格帯です。内容の濃さを考えれば納得できる価格ではありますが、オススメできる層が限られるため、コスパの面では控えめな評価としました。 |
『循環器薬ドリル』とはどのような本なのか
研修医向けの循環器領域の問題・解説集【自己学習用】
『循環器薬ドリル』は、循環器でよく使われる薬剤について、「なぜこの薬を使うのか?」を症例ベースで学べる問題・解説集です。
薬の特徴をただ解説するのではなく、「この患者にはなぜこの薬を使うのか?」という処方意図や選択の背景を考える構成になっていて、読み進める中で自然と臨床的な思考が鍛えられていきます。

本書はもともと医学生や研修医を対象としていますが、薬剤師にとっても「処方の裏にある考え方」を読み解く練習になる1冊です。
「この症例ならどの薬が選ばれるか」「別の薬だと何が問題か」を自分の頭で考えながら読み進めることで、薬を比較検討する力や、提案につなげる視点が養われます。
単なる正解を覚えるための問題集ではなく、「この患者背景・この検査値・この訴えから、どう薬を選ぶべきか?」を繰り返し考える構成になっています。

薬の使い分けを“感覚ではなくロジックで理解したい”人にはうってつけの1冊です。
基礎編と実践編、2つの構成で段階的に学べる
『循環器薬ドリル』は、「基礎編」と「実践編」の2部構成です。
基礎編では、まず薬剤分類ごとに概説があり、その後に症例ベースの問題と解説という構成になっています。
抗血栓薬・降圧薬・心不全治療薬・脂質異常症治療薬などの主要な薬剤が分類ごとにまとめられており、薬ごとの特徴や使い分けをQ&A形式で学べます。
一方の実践編は、一人の患者を時系列で追いながら、初診・処置・再診といった場面ごとに判断を求められる問題が並びます。
登場するのは薬だけではありません。薬物療法を続けるか、それとも手術や他の介入を選択すべきかといった“治療方針そのもの”を問う設問もあり、治療全体を考える視点が養われます。

基礎編・実践編のいずれも、単なる知識の確認ではなく、「どのように考えて治療が選ばれているのか」を理解することに重点が置かれています。
読み進めるなかで、薬の知識はもちろん、処方の背景を理解する力や、医師の思考プロセスを想像する力が自然と磨かれていきます。
病態→薬ではなく、薬→病態という構成なので薬剤師にも学びが多い
本書は、病態や診断名を軸に章立てされているのではなく、薬剤の分類ごとに章が構成されています。
抗血小板薬、降圧薬、心不全治療薬、脂質異常症治療薬など、まず“薬”を起点に話が展開されていく構成になっているのが特徴です。

つまり、「病名や診断から薬を検討する」のではなく、「この薬はどんな症例で、どういう理由で選ばれるのか?」という視点で学んでいく流れになっています。
この構成は、まさに薬を扱う薬剤師にとって非常に相性が良いと感じました。
普段の業務で「この薬、なんで選ばれているんだろう?」と疑問に思うことがある方にとって、本書は薬剤の選択背景や臨床上の判断基準を体系的に学ぶ手がかりになります。
また、薬の分類ごとに症例が並んでいるため、読みたいところ・関心のある領域から読み始めやすい点も、薬剤師にとって取り組みやすい構成です。

薬をきっかけに処方意図や治療選択を考えていくスタイルは、薬剤師の強みを活かしながら読み進められる点で、非常に相性が良いと感じました。
【トレーシングレポートの実例】本書の現場での使い方
過去に、DAPT(アスピリン+クロピドグレル)の長期継続が続いていた患者に対して、減薬提案のトレーシングレポートを提出したことがあります。
その提案が受け入れられ、実際に減薬につながりました。
しかし本書を読んだことで、あのときもっと根拠を明確に示せていれば、より説得力のあるレポートが書けていたと感じました。

今回は、当時提出したトレーシングレポートの原文とあわせて、「今だったらこう書く」という修正案を紹介します。
薬剤師の実務において、本書がどのように活かせるかを具体的にイメージしてもらえればと思います。
提出したトレーシングレポートの実例
以下は、実際に私が提出したトレーシングレポートです。
DAPT(アスピリン+クロピドグレル)を漫然と継続していた患者さんに対し、減薬提案を行ったもので、医師に受け入れられ、処方内容の見直しにつながったケースです。
【実際に提出したトレーシングレポート】
報告日○年○月○日
○○クリニック ○○先生 御机下
患者名 〇〇様
〇〇薬局 のしん
この情報を伝えることに対して、患者の同意を得ています。
【報告内容】
処方薬:バイアスピリン100mg、プラビックス75mg
抗血小板薬2剤を長期にわたって併用しております。薬局の聞き取りでは10年くらい前に冠動脈ステント留置術を行ったと伺っております。DAPT療法は明確な基準はありませんが、基本的に12ヶ月までとされています。(安定狭心症で12ヶ月出血イベントがなかった患者に限り30ヶ月継続とのエビデンスもあるようです。)
現状、出血傾向はありませんが、再度、抗血小板薬2剤併用の必要性をご検討いただきたく、ご連絡させていただきました。よろしくお願い致します。
このレポートは、当時某製薬メーカーのホームページに掲載されていた「DAPT療法の推奨期間」に関する情報を参考に作成しました。
(「DAPT療法 期間」などで検索すると、今でも上位に表示される内容です。)
本書を読んだ今なら、こう書きます
以前のトレーシングレポートでも、DAPT(抗血小板薬2剤併用療法)の長期継続について指摘し、実際に減薬へとつなげることができました。
伝えたいことは簡潔にまとめられていたと思う一方で、文献やガイドラインの記載がなく、説得力に欠ける部分もあったと感じています。
本書『循環器薬ドリル』には、DAPTの継続期間や高出血リスク(HBR)の基準が具体的に紹介されており、トレーシングレポート作成時の強力な根拠となる情報が載っています。
その内容をもとに、当時の症例に対して今だったらどう書くかを意識してレポートを修正してみました。
以下が、その修正版です。
報告日:〇年○月○日
○○クリニック ○○先生 御机下
患者名:○○様
○○薬局 のしん
この情報をお伝えすることについて、患者様より同意を得ております。
【患者情報】
年齢:83歳
体重:38kg
腎機能:CCr 34 mL/min(中等度腎機能低下)
服用中の薬剤:バイアスピリン100mg1錠、プラビックス75mg1錠、ビソプロロール2.5mg2錠、アムロジピン5mg1錠 各分1朝食後
エンレスト200mg2錠分2朝夕食後
【報告内容】
現在、DAPT(抗血小板薬2剤併用療法)が継続されていますが、その妥当性について再検討いただきたく、ご報告いたします。
併せて、バイアスピリンの中止(クロピドグレル単剤への移行)をご提案いたします。
【理由・根拠】
薬局での聞き取りにより、約10年前に冠動脈ステント留置術を受けたとの情報を得ています。
DAPTは当薬局にて2年前から交付を継続しており、それ以前は他院にて処方されていたようですが、詳細は不明です。
患者様は以下の点から、日本循環器学会が定める日本版HBR(高出血リスク)基準に該当します。
• 低体重(38kg)→ HBR主要項目
• 心不全の既往 → HBR主要項目
• 高齢(83歳)、腎機能低下(CCr 34) → HBR副次項目
※主要項目1つ以上、副次項目2つ以上を満たしており、高出血リスク症例と判断されます。
(日本循環器学会『JCS 2020年ガイドラインフォーカスアップデート版 冠動脈疾患における抗血栓療法』)
HBR症例におけるDAPTの推奨期間は1〜3ヶ月程度とされ、その後は抗血小板薬単剤(SAPT)への移行が望ましいと考えられます。
また、HBRに該当しない場合でも、DAPTの基本的な継続期間は原則12ヶ月程度とされています。本症例のように長期にわたり継続している場合は、治療方針の見直しを検討する余地があると考えます。
(『循環器薬ドリル』池田隆徳 監修、阿古潤哉 編集、羊土社、2022年)
さらに、心房細動の既往はなく、DOACなどの抗凝固薬の適応はありません。
以上を踏まえ、DAPTの中止(具体的にはアスピリンの中止)とクロピドグレル単剤への移行についてご検討いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
改訂版のトレーシングレポートを作成する際に意識したポイントは以下のとおりです。
・まず最初に「結論」を提示
→「何を提案したいのか」を冒頭で伝わるようにしました。
・ガイドラインや書籍の情報を具体的に引用
→ 文献や出典を明示することで、説得力と信頼性を高めることを意識しました。
・HBR(高出血リスク)という評価軸を活用
→ 判断の基準を示すことで、主観ではなくエビデンスに基づいた提案であることが伝わるようにしました。
漫然と継続しているDAPTの減薬提案をしよう
循環器の専門医であれば、DAPT(抗血小板薬2剤併用療法)の継続期間や出血リスクを踏まえ、適切に管理されている印象があります。

しかし一方で、循環器以外のクリニックでは「状態が安定しているから」といった理由で、DAPTがそのまま漫然と継続されている処方も、少ないですが存在していると思います。
抗血小板薬の2剤併用療法には、継続期間に一定の基準やエビデンスがあります。
とくに高齢・低体重・腎機能低下といった出血リスクが高い症例(HBR)では、早期にSAPTへ切り替える方が望ましいとされており、定期的な見直しが求められます。

処方薬の適正化は薬剤師の職能の発揮しどころです。
文献やガイドラインに基づいたトレーシングレポートを通じて、処方内容の最適化を医師と一緒に考えていく。それが私たちの役割だと思います。
本書『循環器薬ドリル』には、DAPTの情報や、出血リスクを評価するHBRの考え方がわかりやすくまとめられています。
日々の服薬指導や疑義照会の中で、「このDAPT、本当に必要?」と感じる場面があれば、本書を根拠に自信をもって提案できるようになるはずです。
『循環器薬ドリル』を読んだ感想(良かった点・気になった点)
調べながら読む必要はあるが、多くの薬剤師にも学びがある内容だと感じた

『循環器薬ドリル』を読んでまず感じたのは、「薬剤師にも得るものが非常に多い」ということでした。
本書は医師向けに書かれているため、専門用語や略語、診断に関する判断基準がたくさん出てきます。正直、読みながら何度も調べものをすることになりましたが、その調べる過程そのものが学びにつながっていると感じました。
薬剤師として日々の業務で見慣れている薬が、どういう臨床状況で、どのような背景のもとに選ばれているのか。
「処方の奥にある判断の根拠」を症例ベースで学べる構成になっているため、単なる知識の確認では得られない深い理解が得られます。
調べながらでないと読み進められない面倒さはありますが、それを乗り越えた先には、「この薬が使われている理由がわかるようになった」という実感が残ります。

薬剤師が“処方を読み解く力”を養いたいときにぴったりの1冊だと感じました。
(気になった点)あくまで医師向けの本

とはいえ、「やっぱりこれは医師向けの本なんだな」ということも何度も感じました。
症例の捉え方や設問の視点は、診断や治療方針を自ら判断する立場の医師向けに作られており、薬剤師向けの内容とは言えません。
薬剤師でも十分読み込める内容ではありますが、初学者にとってはややハードルが高いと感じました。

循環器領域に苦手意識がある方や、これから勉強を始めようという薬剤師の方に「まず最初の1冊」としてオススメする本ではありません。
逆に言えば、ある程度基礎的な知識が身についていて、「もう少し処方の背景まで深く理解したい」と思っている方には、非常に有意義な本です。
循環器の勉強を進める中で、3冊目・4冊目として手に取る位置づけがちょうど良いと感じました。
序盤で読むのを諦めないでほしい

正直に言うと、私はこの本の最初の数ページで「これは読み切れないかもしれない…」と思いました。
専門用語や略語が多く、登場する症例も「胸痛で救急搬送された患者」や「外来受診後、そのまま緊急カテーテル検査となった症例」など、薬局で日常的に関わるケースとはやや距離のある印象。
臨床の現場で実際に医師がどう判断しているかという内容で、想像以上に難しいと感じました。
本書を開いて最初に登場するのは抗血栓薬です。私は抗血栓薬の章を読んだ時点で“この本は読み切れないかもしれない”と心が折れかけました。
本書で1番最初に登場する症例問題の一部を引用します。
【症例1】
健康診断での心電図上、洞調律であるが、下壁誘導で異常Q波を認めていた。多くの冠動脈疾患リスクファクターを有しており、心電図異常の精査目的に冠動脈造影検査を施行した。結果、右冠動脈の末梢領域に慢性完全閉塞を認めていた。心エコー上、壁運動は良好で明らかな心内血栓も認めなかった。また心不全症状も呈しておらず、胸部症状も認めないことから、内服加療の方針となった。
Q1 追加投与が検討される抗血栓薬はどれか。
a. ワルファリン b. アスピリン c. ダビガトラン d. アピキサバン
(引用:『循環器薬ドリル』池田隆徳 監修、阿古潤哉 編集、羊土社、2022年、p.18)

問題文読めね〜💦ムズすぎ!!
と、いきなりこの問題を見たとき、「自分には無理かも」と感じたのが本音です。
ちなみに正解はbのアスピリン。慢性冠動脈疾患に対するエビデンスが豊富で、症例背景からも適応とされます。
他の選択肢は抗凝固薬であり、心内血栓や心房細動の所見がないこのケースでは選ばれません。
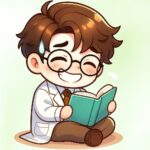
解説を読めば「なるほど」と納得できるのですが、問題を初見で読んだときに読み切れる自信は全くなかったです。
ただ、読み進めるうちに「この問題はわかる!」と感じられるものも増えてきて、少しずつペースが上がっていきました。
たとえば、利尿薬の章ではフロセミドによる“低カリウム”を問う問題や、逆にスピロノラクトンが“カリウム保持性”であることを確認する問題など、薬剤師にとって比較的なじみのある内容も出てきます。
全体を通して難易度は高めですが、調べながら読み進めれば、だんだん難易度にも慣れてきます。

もし冒頭で「無理かも…」と思っても、まずは読みやすそうなところから手をつけてみてほしいです。
完璧に理解するを目指さずに、「今の自分にわかる範囲」で読み進めるのがオススメです。
『循環器薬ドリル』をオススメできる人
病院薬剤師
本書は、病院で勤務する薬剤師にオススメです。
循環器病棟を担当している薬剤師であれば、日々の処方意図の理解や、医師とのコミュニケーションの精度を高めるうえで非常に役立つ内容が詰まっています。

一方で、循環器以外の病棟を担当している薬剤師にとっても、本書はオススメです。
循環器の専門医は循環器関連の薬に非常に詳しいため、薬剤師に質問がくるのはむしろ“循環器以外の薬”に関する内容が多いです。
そのため、循環器病棟以外を担当している薬剤師の方が、心不全や抗血小板薬の使い分けなどについて医師から質問される機会があるというケースも少なくありません。
そうした場面で医師と対等にやり取りするためには、薬を起点とした体系的な循環器の知識を持っておくことが不可欠です。
本書は、まさにそうした知識を補強するための心強い一冊になると感じました。
すでに循環器領域の本を何冊か読んでいる方
本書は、医師向けに書かれた症例ベースの問題・解説集であり、出てくる略語や専門用語も医師向けの前提で構成されています。

そのため、循環器の勉強をこれから始めようという薬剤師には、オススメできません。
「循環器領域の勉強は初めて」という方には、薬剤師向けでもっと適した参考書があります。
その一方で、すでに循環器領域の書籍を何冊か読み進めてきた方には、本書は“次のステップ”として非常に適した1冊です。
特に、薬を起点として「なぜこの薬が選ばれているのか?」という思考の積み重ねが求められる構成なので、基礎知識をもとに実践力を高めたい方にとっては、現場感のある知識の“定着”につながる本だと感じました。
漫然投与のDAPTの減薬提案をしたい薬剤師
薬局で働いていると、バイアスピリンとプラビックスの2剤併用(DAPT)が、いつの間にか“漫然と継続”されているケースに出会うことがあります。
特に、循環器専門医ではなく内科クリニックなどで継続されている処方では、再評価の機会が少ないまま数年以上続いていることも。
本書では、DAPTの推奨期間に関する具体的な基準や、出血リスク(HBR)の評価方法が簡潔に解説されています。
薬剤師としてその知識を持っておくことで、「このままの治療で本当にいいのか?」と根拠をもって疑問を投げかけることが可能になります。

処方薬の適正使用に貢献できる薬剤師を目指したい方にとって、本書は大きなヒントを与えてくれるはずです。
監修者・編集者紹介
本書『循環器薬ドリル』の監修は、池田隆徳 先生(東邦大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授)が担当されています。
循環器内科・不整脈・薬物治療学の専門家で、国内外の学会でも多くの要職を歴任されています。
編集は、阿古潤哉 先生(北里大学医学部 循環器内科学 教授)です。
循環器疾患全般からインターベンション治療まで幅広く経験され、現在も臨床の第一線で活躍されています。
【まとめ】知識の穴が見える、循環器の実践問題集

循環器の勉強を本気で深めたい薬剤師にとって、本書は“立ちはだかる壁”にも“学びの道しるべ”にもなります。
読みごたえはありますが、挑戦する価値は十分です。
【どのような本なのか?】
• 症例ベースで考える循環器薬のドリル形式
• 医師向けに書かれており、内容はかなり専門的
• 治療方針の考え方や薬剤選択の根拠まで言語化されている
【読んで感じたこと】
• 自分の知識の浅さに気づかされる(心が折れかけました)
• 読みやすく工夫されているが、気合いが必要
• 読み切れた人は「のしんに勝った」と思ってほしい
【オススメできる人】
• 病院薬剤師
• すでに循環器領域の本を何冊か読んで勉強している方
• DAPTの減薬提案をしたい薬剤師
正直、万人にオススメできる本ではありません。
ですが、読み終えたときに得られる達成感と視野の広がりは、他の本ではなかなか味わえません。

「循環器薬を武器にしたい」——そんな薬剤師にこそ、ぜひ手に取ってほしい1冊です。
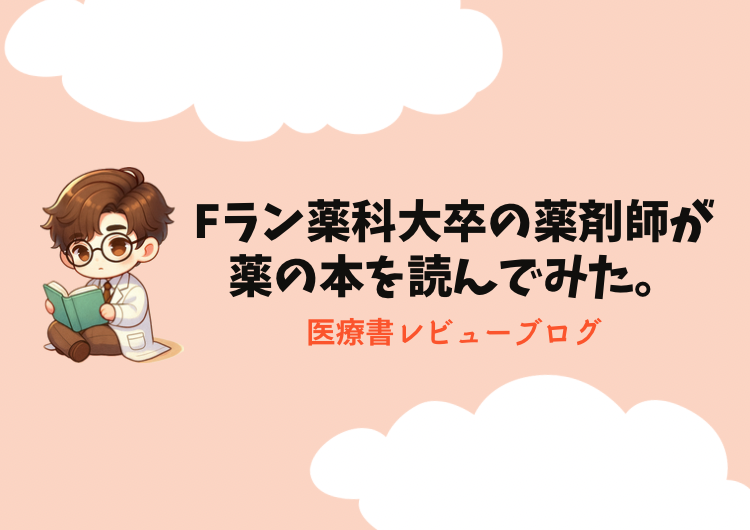
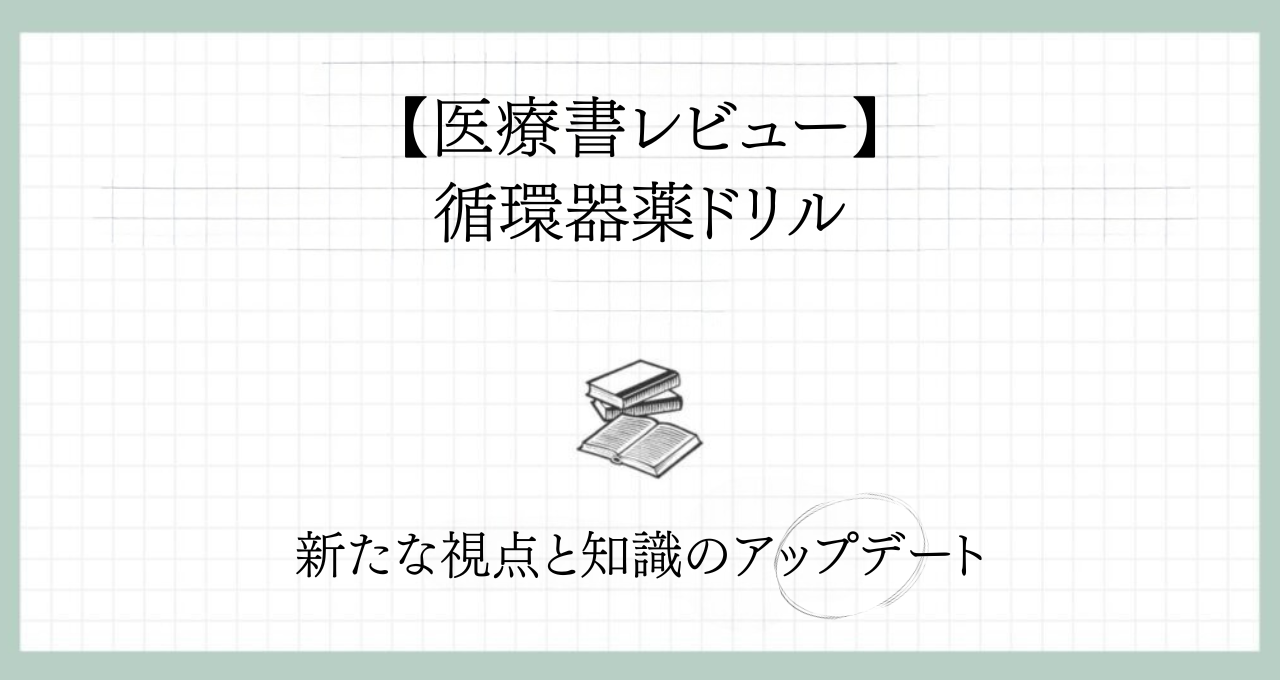


コメント