このブログを訪れてくださるあなたは、きっと「薬剤師としてもっと学びたい」「自己研鑽したい」という強い意志を持った方だと思います。

こんなエンタメ性ゼロの真面目すぎる自己研鑽ブログを読んでる時点で、あなたも私と同類です(笑)
インターネット検索やAIに頼れば、答え(っぽいもの)はすぐに手に入る時代。
そんな中で、あえて書籍を手に取り、能動的に学ぼうとする姿勢は、これからの薬剤師に絶対必要です。
なぜなら、AI時代でも必要とされる薬剤師は、“自分の頭で考えられる人”だからです。
でも、どれだけ意欲があっても、その力を発揮できるかどうかは「環境」に大きく左右されます。
私自身、かつては通勤に片道1時間半。
勉強したいのに、疲れすぎてまったく勉強できない日々を2年近く送りました。
激務のストレスで不眠も経験しました。寝たいのに眠れずに、徹夜で出勤したこともあります。
そんな私でも、転職を機に「自分で勉強できる薬剤師」に変われました。

今では、年間50冊以上の医療書を読んで、自己学習を継続しています。
そして今、このブログを読んでくれているあなたにも、もっと力を発揮できる職場があるのでは?と感じています。
この記事では、私の転職経験をもとに、
・転職をきっかけに、勉強できる薬剤師になれた話
・勉強を習慣づけられる職場の探し方【3つの視点】
・転職サイトを上手に使うコツ
について、具体的にお話ししていきます。

今の職場にちょっとでも「モヤッ」としてるなら、読んで損はありません!
その職場、本当にあなたに合っていますか?
── 薬剤師は「医療職」のはずが、いつの間にか“ただの作業員”になっていませんか?
あなたは今、本当に薬剤師として働いていますか?
「薬剤師」という肩書きはある。
でもその働き方、本当に“医療行為”を提供できているでしょうか?
・調剤では、処方せんに書かれた薬を「いかに速く」「いかに正確に」揃えるかが最優先
・監査では計数の正確さばかりに気を取られ、処方の妥当性を考える余白がない
・患者さんからは「薬の話は先生としている、もういいです」「早くして」と急かされる
・気づけば、“誰でもできる仕事”の中に埋もれていく自分

あなたの周りに“マックジョブ”的な働き方をしている薬剤師いませんか?何よりも怖いのは…あなたはそんな働き方をしていませんよね…?
※マックジョブとは?
誰でもできる、思考がいらない、単純でマニュアル化された労働のこと。
代表例はファストフード店の店員など。
「やりがい」や「専門性」が感じづらく、スキルが身につかない働き方を指す言葉です。
本来、薬剤師は薬のスペシャリストとして、患者さんに医療行為を提供する専門職です。
でも実際は「処方せんをいかに効率よくさばくか」「患者さんをお待たせしないか」「薬歴を簡潔に書いて、残業時間を減らすか」が求められる職場も多いと思います。

それはもう、“医療”ではなく、“サービス業”じゃないでしょうか?
成長したい気持ちに、今の職場が応えてくれますか?
あなたがどれだけ意欲的でも、職場に「成長を後押しする空気」がなければ、やはり限界があります。
たとえば──
・社内研修や勉強会、症例検討などがなく、職場自体に「勉強する」という文化がない。
・そもそも社員が少なく、周りは家庭優先のママさんパート薬剤師ばかり。
・さらに管理薬剤師になると、売上ノルマ(処方せん枚数)、経費削減(残業時間の削減)、シフト管理など、薬剤師本来の業務とは離れた負担も増えていく。
そんな環境の中では、自然と“勉強しない空気”が当たり前になります。
「もっと患者さんのために薬の知識を活かしたい」
「もっと薬剤師の職能を発揮したい」
つまり、「学びを重ねて得た知識を、患者さんや処方医に還元し、医療の質の向上に貢献したい」
──そう思っても、日々の業務で時間もエネルギーも奪われていく。
あなたの“成長したい気持ち”に、今の職場は本当に応えてくれていますか?
【体験談】環境を変えたことで「勉強できる自分」になれた話
通勤時間が勉強の最大の敵だった
当時の私は、都内の病院に勤務していました。
でも、家は郊外。通勤は片道1時間半、朝6時過ぎには家を出ていました。
乗り込むのは、乗車率200%の超満員電車。
スマホすら満足に触れず、ましてや本を開くなんてとても無理。
ひたすら揺られ、押し込まれ、ぐったりして出勤する毎日でした。
仕事を終えて帰宅するのは、夜の8〜9時。
そこからお風呂に入って、夕食をとって、気づけばもう寝る時間。
「明日も6時台には家を出ないと…」

そんな生活では、とても勉強に手をつける余裕なんてありませんでした。
職場環境はよく、薬局長や先輩薬剤師も優しく、業務自体に不満はありませんでした。
──ただ、「勉強ができない」のです。
医師からの質問、病棟で出会う症例、どれも知らないことだらけ。
「調べなきゃ」と思っているのに、疲れ果てた体では机に向かう気力が残っていませんでした。
不眠も経験しました。身体は疲れているはずなのに、ベッドに入っても頭の中は不安と焦りがグルグルと反芻(はんすう)して眠れない。徹夜で出勤したこともあります。

勉強したいのに、できない。
どんどん自分がダメになっていくような感覚があって、焦りと無力感だけが積もっていきました。
人間関係に不満はなかった。でも、転職を決意した理由
転職を決意するまでには、相当な時間がかかりました。
というのも、職場の人間関係にはまったく不満がなかったからです。
院内薬局長にはとてもよくしていただきましたし、後述しますが、病院の前に勤めていた調剤薬局の薬局長や先輩方にも、本当にお世話になっていました。

業務内容も、薬剤師として成長できるやりがいのあるものでした。
それでも悩んでいたのは、「通勤時間」だけ。
結婚して子どももいた私には、簡単に引っ越すという選択肢は取れませんでした。
生活スタイルや家庭とのバランスを考えると、どうしても「通勤時間の長さ」が足かせになっていたんです。
気づけば、自分の時間がどんどん失われていく感覚。
日々のタスクに追われるばかりで、「自分の人生を生きている」という実感すら持てなくなっていました。
それでも「このままではいけない」という思いが、少しずつ、少しずつ積み重なり、やがて決意に変わりました。
転職で「時間」と「余裕」を手に入れた
転職活動は、転職サイトに登録し、担当エージェントとの面談を何度か重ねながら進めました。
最終的に選んだのは、自宅から自転車で15分の職場です。
今はあの頃の「片道1時間半」の通勤時間が、本当に無駄だったと実感しています。
朝の6時過ぎに家を出て、満員電車に揺られていた生活は終わり、今は子どもを見送ってから余裕を持って出勤できるようになりました。

帰宅後も時間に追われることなく、気持ちにゆとりを持って1日を終えられます。
転職によって、時間と心に余裕が生まれました。
本を開く気力がなかった日々とは違い、「この本、明日も続きを読みたい」と自然と思えるようになったのは、何よりの変化だと感じています。
もちろん、子育てという制約がゼロになったわけではありません。
それでも、「勉強して、成長できている実感」がある。
薬剤師としての自分を、少しずつでも前に進められているという実感があります。
もしあのとき、通勤時間や環境に目をつぶって我慢を続けていたら—— 勉強したいという気持ちすら、どこかに置き忘れていたかもしれません。
環境が変われば、努力も続けられるようになる
「努力できるかどうかは、結局は自分次第」
よく聞く言葉ですが、私はそうは思いません。
たしかに意思は大切です。でも、意思だけに頼って努力を継続するのは現実的ではないと私は感じています。
この記事を読んでいる方の中には、

電車の中の方が集中できる

家だと誘惑が多くてダメなんです
そんな声を持つ方もいるかもしれません。
実際、通勤時間が逆に“自己研鑽のトリガー”になって、学習習慣を維持できている人もいる。
それは本当にすばらしいことですし、否定するつもりもまったくありません。
でも──
私はダメでした。
どんなに「この1時間半を有効活用しよう」と思っても、朝はぎゅうぎゅうの満員電車。帰りの電車は座って帰ってこれましたが、疲れ果てていて、ページを開く気力も出ない。
やっと帰宅しても、夕飯を食べてお風呂に入って…
もう寝ないと、翌朝また5時台起き。そんな毎日。
だから私は、環境を変えることを選びました。
通勤時間が長くても、「私はその時間に勉強できているから大丈夫」という方も、きっといると思います。
それ自体は本当に素晴らしいことです。
ただ私は、正直こうも思ってしまいます。

家で勉強できないのなら、通勤時間を短くして、その分の時間を職場や近所のカフェで勉強した方が、効率よくないですか?
──そう感じてしまうほど、私にとって通勤時間は不要なものでした。
自分が集中できる場所を確保する。自分の努力が“自然と続く環境”を選ぶ。
それは甘えではなく、「仕組み」であり「戦略」なんだと、今でははっきり言えます。
「石の上にも三年」「この職場で結果を出せないなら、どこへ行っても通用しない」「転職は逃げだ、甘えだ」──
そんな言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。

でも私は、転職が逃げや甘えだとは思いません。
人にはそれぞれ、価値観やライフステージがあります。
自分にとってより良い環境を探すことは、前向きな選択です。
“自分の可能性を活かせる場所を見つけようとする努力”が逃げ・甘えであろうはずがありません。
【勉強習慣を手に入れやすい転職先を探すなら】業務・時間・文化の3視点で見極めよう
私は転職のプロではありません。
転職サイトやエージェントに詳しいわけでもありません。

でも、薬剤師として日々勉強し、年間50冊以上の医療書を読んで、自己学習を継続しています。
どうすれば勉強が続くか。どうすれば勉強の熱を保てるか。そのためにどのような職場が適しているのか。
その点については、なんとなく働いているだけの薬剤師よりも、少しだけ解像度高く語れる自信があります。
ここでは、自己研鑽(特に書籍での学習)を続けやすい職場を選ぶには、どんな条件を手がかりにすればいいのか。
その視点で、私の考えをお伝えします。
【業務】多くの診療科・多様な処方に触れられる職場かどうか/扱っている医薬品数が多いかどうか
いろいろな診療科の処方せんを扱う薬局や病院の方が、学びの“きっかけ”が多いです。

書籍による自己学習の強みのひとつは、「自分に足りない知識を、自分から取りに行けること」です。
でも、そもそも「足りない知識」に気づけないと、書籍も選べません。だからこそ、多様な処方に触れられる職場がオススメです。触れる疾患・薬が増えれば、「この病気知らない」「この作用機序、説明できない」という“学びの起点”が自然に生まれます。
仕事をしながらの勉強には、当然ながら時間の制約があります。そのなかで効率よく学びを得るには、ピンポイントで「何を勉強すべきか」を選定できることが非常に大切だと思います。
セミナーや勉強会もたくさん開催されていますが、そのテーマは基本的に開催する側が決めます。もちろん、興味のあるテーマがあれば積極的に参加すべきですが、業務中に「この疾患知らないな」「この領域、苦手だな」と気づいたタイミングで、ちょうどよく勉強会が開催されることはまずありません。

だからこそ、自分に足りない知識を、必要なときに、必要な分だけ取りに行ける。
そこに書籍での自己学習の強みがあると感じています。
私は、「勉強のための勉強」には意味がないと思っています。ここで言う「勉強のための勉強」とは、いわゆる“自己満足の勉強”のことです。勉強している自分に満足して、それで終わってしまうような勉強です。
強い言い方になりますが、たとえば、セミナーにたくさん参加して、それで満足して終わってしまうような勉強のことです。セミナーや講義はあくまで受動的な学びであって、それを能動的な学びにするには、復習や実務への応用といった“アウトプット”が必要です。
セミナーを受けて「なんとなく理解した気になる」。その段階で終わってしまっては、結局何も変わりません。はっきり言ってしまえば、セミナーをたくさん受けている薬剤師の中には「勉強した気になっているだけ」の人も少なくないと感じています。
もちろん、セミナーにすら出席しない薬剤師が多い中で、積極的に参加している時点で勉強に対する意識は非常に高いです。それ自体は本当に素晴らしいことです。ただ、それだけで終わってしまうのは、正直もったいないと思います。
「勉強のための勉強」「自己満足な勉強」にはあまり意味がありません。実務に活かして初めて、勉強には意味がある。学びと現場をリンクさせる環境があるかどうか、それは転職先選びで非常に重要なポイントです。
【時間】自己学習する“時間”を確保できるかどうか

私は、自己学習は「短い時間でもいいから、毎日続ける」ほうが絶対に効率がいいと思っています。
たとえば、毎日30分勉強する人と、週2日の休みに3時間ずつ勉強する人。週あたりの学習時間は前者が3.5時間、後者が6時間と、後者の方が多く見えます。でも、私の感覚では、圧倒的に前者の方が効率がいいし、習慣としても続きやすいです。
転職活動をする際、年間休日の多さに注目する人は多いと思います。もちろん、休みは多いに越したことはありません。ただ、「学びを継続する」ことを大切にするなら、年間休日よりも、“出勤日の余暇時間”をいかに確保できるかが重要だと思っています。

つまり、残業が少ないかどうか。通勤時間がどれくらいか。ここ大事です。
自己学習を続けるには、「毎日の継続」が何より大切です。
以前、私は片道1時間半の通勤をしていた時期がありましたが、そんな環境では勉強する気力は残っていませんでした。
現在は通勤15分の職場に転職し、ようやく勉強を習慣化できています。
この経験からも、休日の多さより「平日の余白」が重要だと実感しています。
残業や通勤時間の少なさは、勉強を続ける上で大きな支えになります。
加えて、自己学習でいちばん難しいのは、「勉強を始めるまでのハードルの高さ」だと思います。
でも不思議なもので、やり始めるまでは腰が重いのに、いざ始めてしまえば意外と集中できて、楽しくなってくる。

これは「作業興奮」と呼ばれる現象で、やる気があるから始めるのではなく、始めたからやる気が出てくると言う現象です。あなたも国家試験の勉強で経験したことがあるのではないでしょうか?
私自身も「5分だけやってみよう」と思って机に向かい、気づいたら30分、1時間と勉強に没頭していたことが何度もあります。
そして実感として、この“始める”という最初のハードルは、平日よりも休日の方が圧倒的に高いです。休日の勉強はほんと10倍くらいハードル高い気がします。休日は時間がたっぷりある分、「今日はまとまった時間でガッツリ勉強しよう」と意気込んでしまい、そのぶん始めるまでの腰が重くなる。
一方で、平日は時間が限られているからこそ、さっと始めやすいんですよね。だからこそ、勉強は“休日まとめて”よりも、“平日に少しずつ”の方が続けやすいし、結果的に効率もいいと私は思っています。
【文化】「勉強するのが当たり前」と言う空気がある職場かどうか
薬剤師が勉強を続けられるかどうかは、周囲の空気にかなり左右されると思います。
ですが、転職に関して、これは人間関係と似ていて、実際に働いてみないとわからない部分も多く、運の要素もつきまといます。
ただ、転職活動中に「勉強に対して前向きな職場かどうか」を判断するヒントは、いくつかあります。
私が大切だと思うのは以下の4点です。
①社内研修や勉強会がどれくらい実施されているか
②e-learningの費用や書籍代などに会社補助があるか
③正社員とパート薬剤師の割合
④同僚の年齢層
まず大前提として、日常的に勉強を習慣にしている薬剤師は、決して多くありません。

完全に私の主観ですが、「あなたは勉強を習慣化していますか?」と全薬剤師に聞いたら、9割以上が「していない」と答えるんじゃないかとすら思っています。
そんななかで、「勉強意欲が高い同僚」がいる職場をどう選ぶか。
「切磋琢磨できる仲間」が見つかる職場って、どんな環境なのか。
①②は、その会社に勉強の文化があるかどうかを見るための視点です。
③④は、実際に働くメンバーに「勉強している人」がいる確率を上げるための視点です。
ここからは完全に私の主観です。もし気分を害される方がいたら申し訳ありません。でも、あくまで「傾向」の話として聞いていただきたいのですが——
私は、パート薬剤師よりも正社員薬剤師の方が、勉強意欲が高い人が多いと感じています。また、ベテランよりも若手の方が、情報をアップデートする意識が強い傾向と思います。
もちろん、例外はあります。ママさんパート薬剤師でとても勉強熱心な方もいますし、逆に、将来のビジョンを持たず、まったく勉強しようとしない若手薬剤師もいます。

あくまで一個人の主観です。傾向のひとつとして、参考程度に捉えていただければと思います。
なお、職場の年齢層や正社員比率などは、エージェントに聞けば教えてくれます。勉強に前向きな人と出会える可能性を少しでも高めるために、意識しておいて損はないと思います。
【転職サイトは使い方次第】情報収集の入り口として活用しよう
私は転職エージェントのプロではありませんし、転職サイトを使いこなしていたわけでもありません。ただ、実際に転職を経験するなかで「知識が少なくても、うまく使えば強い味方になる」と感じました。

ここでは、私が考える“転職サイトとのちょうどよい距離感”と、参考にした動画をご紹介します。
転職サイトは「応募のため」だけではなく、情報収集ツールとして便利
「転職=すぐ応募」のイメージを持っている人も多いかもしれませんが、転職サイトは「求人のカタログ」です。
どんな職場が世の中にあるのか、どんな条件が一般的なのか。それらを比較して見ることで、自分に合う職場のイメージが明確になっていきます。
また、求人情報を読み比べていくうちに、「この条件って、自分に当てはまるのかな?」といった疑問が自然と湧いてきます。
そんな時こそ、エージェントを活用するチャンスです。エージェントは転職のプロ。求人のことだけでなく、今の自分の実力や市場での立ち位置についても客観的に教えてくれます。
プロの目線でアドバイスをもらうことで、自分では気づけなかった強みや課題にも気づけるかもしれません。
知識が少なくてもOK。迷ったらこの動画を見てみてください
転職サイトの仕組みや注意点について深く知りたい方は、私も参考にした【リベ大 両学長】のYouTube動画を見てみてください。
薬剤師に特化した内容ではありませんが、「どう使えば後悔しないか」が非常にわかりやすく解説されています。
専門的な知識がなくても、正しい考え方を知っていれば転職活動はぐっとラクになります。
「“転職”にはリスクがあるが、“転職活動”はノーリスク」
今の職場を辞めるかどうかは置いておいても、まずは情報収集を始めるだけで得られる気づきは多いです。
求人を見て、職場の条件や傾向を把握する。気になったことがあればエージェントに質問してみる。
それだけでも、「今の自分の働き方を見つめ直すきっかけ」になります。
最初は軽い気持ちでOKです。転職サイトは、“今の働き方をアップデートするためのツール”として、うまく活用していきましょう。
オススメ転職サイト【実際に使って安心できたサイト】
転職サイトはたくさんありますが、私がエージェントを利用したのは1回だけ。
いろいろなサイトを比較できるほど詳しいわけではありません。

それでも、実際に使って「安心して相談できた」と感じたサイトが2つあるので紹介します。
転職サイトは他にもたくさんありますが、私が実際に使ってよかったと感じたのはこの2つです。
どちらも安心して相談でき、サポートが丁寧だったので、自信をもってオススメできます。
「どれか1つに絞らなきゃ」と悩む必要はありません。
2〜3社に登録して話を聞いてみると、それぞれの強みや担当者の相性、自分の希望に合った提案が見えてくると思います。
ファルマスタッフ【求人数が多く、職場の選択肢が広がる】

私が実際に転職時に利用したサイトです。
担当者の対応がとても丁寧で、希望や不安をじっくりヒアリングした上で、条件に合う職場を一緒に考えてくれました。
何よりよかったのは、圧倒的な求人数。選択肢が多いからこそ、自分に合った職場を見つけやすいと感じました。
「とにかくたくさんの求人から選びたい」「まずは幅広く見てみたい」
そんな方にオススメのサイトです。
アイリード【薬剤師専門だからこその安心感と相談のしやすさ】

薬剤師に特化した転職サイトで、スタッフの方が業界への理解が深く、話がとてもスムーズでした。
私は電話面談を利用しましたが、面接のような堅苦しさはなく、気軽に相談できる雰囲気だったのが印象的でした。
「転職エージェントに相談するのは初めて」という方にも安心して使っていただけると思います。
比較して選び抜いたわけではありませんが、担当者の丁寧な対応と手厚いサポートに「登録してよかった」と心から思えました。
「いろいろ調べるのは面倒」「まずは1つ試したい」という方には、きっと参考になると思います。
登録=すぐ転職、ではありません。

まずは気軽に相談して、将来の選択肢を広げるきっかけにしてみてください。
【まとめ】勉強を習慣化するカギは“自分”と“環境”の両方にある
その職場、本当に“自分に合って”いますか?
勉強する気はあるのに続かない…その原因、もしかしたら“職場環境”かもしれません。今の職場で、本当に学び続けられそうか?一度立ち止まって考えてみましょう。
・業務内容はルーチン作業ばかりになっていないか
・疑問が湧くような処方や症例に触れられているか
・勉強しても現場で活かす機会がないと感じていないか
・周囲に学ぶ雰囲気や文化があるか
・そもそも、自分の将来像と今の仕事がつながっているか
勉強できる職場を選ぶには?見ておきたい3つの視点【業務・時間・文化】
転職で環境を変えるなら、「勉強しやすさ」を軸にした職場選びが重要です。私の経験をもとに、“外から見える条件”で判断する方法をまとめました。
・多くの診療科や多様な処方に触れられる職場か
→ 処方が偏らない現場の方が、自然と学びのきっかけが増える
・通勤や残業が少なく、平日の余白時間を確保できるか
→ 勉強の継続には「毎日のちょっとした時間」が大きな支えになる
・「勉強するのが当たり前」という文化があるか
→ 周囲の薬剤師が学んでいる職場では、自然と意識も引き上げられる
転職サイトは“情報収集の入り口”と捉えよう
転職サイト=すぐに転職する人が使うもの、というイメージがあるかもしれません。でも、考え方を変えるだけで、もっと気軽に活用できるようになります。
・転職活動はノーリスク。情報収集だけでも十分価値がある
・求人を比較するだけで、自分の「当たり前」が疑える
・エージェントは転職のプロ。条件だけでなく“自分の立ち位置”を見つめる手がかりにもなる
・登録は無料。気軽に始めて、不要なら途中でやめればOK
【オススメ】登録しておきたい転職サイト2選
私は転職サイトを使いこなせるタイプではありませんが、
実際に使って「安心して相談できた」と思えたのが以下の2社です。
いきなり1つに絞るのではなく、2社ほど登録して比較してみることで、
自分に合った担当者や働き方の方向性が見えてくると思います。

自己学習は、自分の意志と仕組み、そして“それを支える環境”があってこそ続けられます。
あなたの理想の薬剤師像があるなら、その未来にふさわしい場所を選びましょう。
勉強したい薬剤師ほど、環境にこだわるべきです。
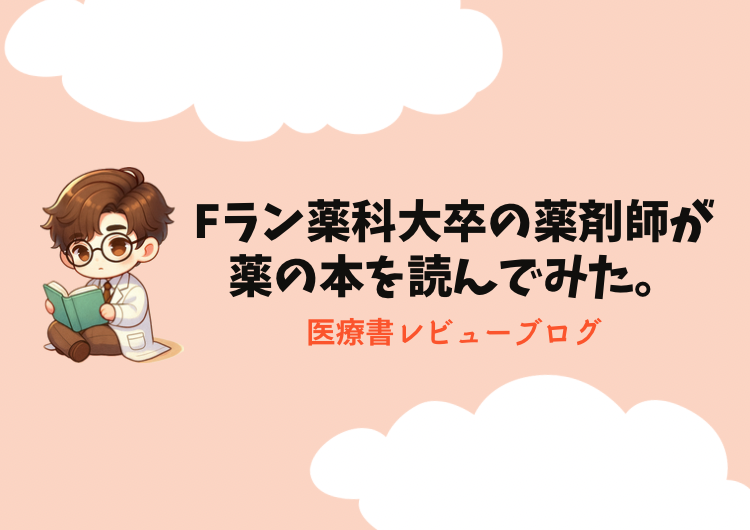
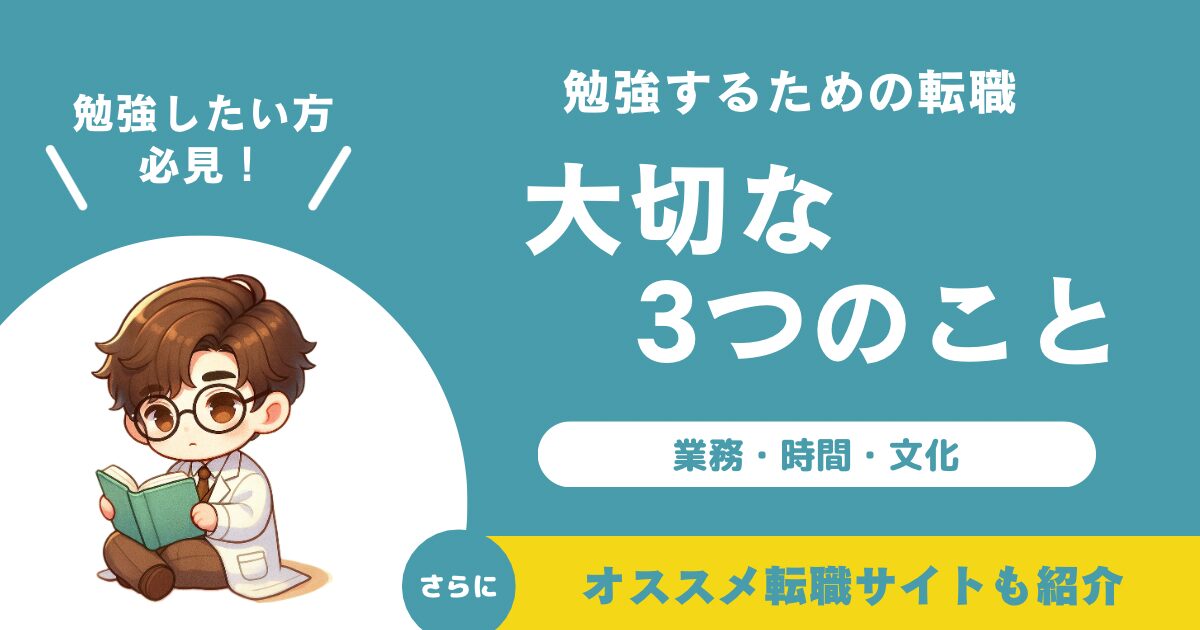


コメント