「心不全」や「心房細動」の患者さんに出会っても、正直いつも「なんとなく」対応している——。

薬は知っているけれど、状態とのつながりがよくわからない。処方の理由も曖昧なまま、聞かれたことだけに答えている気がする……。そんなモヤモヤを抱えたまま、循環器の処方に向き合っていませんか?
この記事では、そんな悩みを持つ薬剤師に向けて、『薬剤師力がぐんぐん伸びる 専門医がじっくり教える心不全・心房細動』という1冊を紹介します。
「心不全ってそういうことだったのか」「この薬はこういう目的で処方されているのか」が、理解できるようになる本です。
本書では、心不全や心房細動の基礎的な知識を、具体的な症例や処方薬と結びつけて解説してくれます。
「なぜその薬が選ばれているのか」「患者のどこを見ればいいのか」といった視点が、自然と身についていく構成です。
この記事では、本書の内容をもとに、薬剤師としてどんな場面でどう活かせるのかを整理しました。本書を参考に実際に提出したトレーシングレポートも紹介します。
読み終えたあとには、「これなら自分にもできそう」と思えるような気づきや実践のヒントがきっと見つかるはずです。
循環器が苦手なあなたにこそ、ぜひ手に取ってほしい1冊です。
| 評価項目 | 評価 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 循環器関連の勉強をしたい薬剤師はもちろん、「勉強したいけど、何から始めたらいいかわからない」という人にもオススメです。 | |
| 実務での活かしやすさ | 現場で本書を開くイメージはあまり湧きません。ただし、トレーシングレポートで伝えるべき内容が分かるようになります。 | |
| 自己学習への向き | 循環器の知識がまったくない状態からでも読める内容です。本書の内容を学べば、心不全の患者対応に自信が持てるようになると思います。 | |
| 読みやすさ | 内容もボリュームもちょうどよく、毎日1時間の読書時間で1週間ほどで読み切れる分量です。 | |
| コスパ | 税込4,950円。医療書としては標準的な価格で、内容も十分。価格に見合った価値があります。 |

『薬剤師力がぐんぐん伸びる 専門医がじっくり教える心不全・心房細動』はどのような本なのか

循環器が苦手な薬剤師に向けて、「心不全・心房細動って、結局どう考えればいいの?」という疑問に答えてくれる1冊です。
病態や薬の基本を整理しながら、処方の意図やトレーシングレポートにつなげる視点まで学ぶことができます。
循環器関連の病態・薬を自己学習で学ぶための本
循環器の分野は、どうしても苦手意識を持ちやすい領域です。
心不全の患者さんに対して「何を注意して見ればいいのか?」「それぞれの薬がどんな目的で使われているのか?」といったことが、曖昧なまま業務にあたっている方もいるのではないでしょうか。

本書は、そうした薬剤師に向けて、心不全の基礎から薬物治療の考え方までを段階的に学べる構成になっています。

心不全の病態、治療の総論、薬剤の各論と順序立てて進んでいくため、知識の整理と定着がしやすく、自己学習に最適です。
さらに特徴的なのが、各章末にある「フォローアップの勘所(かんどころ)」です。
これは、章で学んだ内容を一言でまとめた、実践的なコメントです。
読んだ内容を振り返りながら次の章へ進めるため、知識を定着させやすく、理解が深まりやすくなっています。
日々の業務と結びつけながら読み進められるため、学んだことを実務に活かすヒントが得られる構成です。
循環器の基礎を固めたい方や、何から手をつけていいか迷っている方にこそ、最初の1冊としてオススメしたい内容です。
心不全の患者さんや処方薬を、薬剤師がどう見ればいいのかがわかる
心不全の患者さんが来局したとき、処方薬だけを確認して「利尿薬が出ているな」「β遮断薬も入っているな」といった表面的なチェックだけで終わってしまっていないでしょうか。

本書を読むことで、「なぜこの薬が使われているのか」「患者さんの状態はどこに注意して見るべきなのか」といった視点が自然と持てるようになります。
たとえば利尿薬では、食事量や水分摂取量、体重の増減、労作時の息切れ、浮腫の有無や程度など、患者さんの背景のどこに注目すべきかが具体的に解説されています。
心不全の治療に用いられる利尿薬はループ利尿薬が基本です。さらにループ利尿薬にはフロセミド、アゾセミド、トラセミドの3種類があり、それぞれの特徴や使い分けなども学ぶことができます。
ただ処方を見るのではなく、「処方を通して患者の状態を見ていく」力を身につける。
本書は、その第一歩となるような1冊です。
循環器の薬を飲んでいる患者さんのトレーシングレポートの書き方がわかる
本書では、2024年の調剤報酬改定で新設された「調剤後薬剤管理指導料2」にも触れられており、慢性心不全患者に対する薬剤師のフォローアップについて、実践的な視点で解説されています。
心不全の患者さんに対して、どのような点に注目して経過観察を行えばいいのか、さらにそれをどのように医師へフィードバックすればよいのか——。
そうした一連の流れをしっかりと整理できる内容になっています。

何を書けばいいかわからない

判断材料が曖昧
といった悩みに対して、観察ポイントや薬剤の意味づけ、報告時の注意点などが丁寧に示されているため、トレーシングレポートに自信が持てない薬剤師にも参考になります。
単に薬の知識を増やすだけでなく、「どう活かすか」まで学べるのが本書の強みです。
『薬剤師力がぐんぐん伸びる 専門医がじっくり教える心不全・心房細動』の現場での活かし方
正直なところ、現場での患者対応中などに本書を開いて使うイメージはあまり湧きません。
即時性のある、辞書的な使い方には向いていないからです。
どちらかというと、“自宅でじっくり読み込む”タイプの参考書です。
とはいえ、内容自体は明日からの業務に活かせる、即戦力となる知識が詰まっています。

この章では、本書の学びを実務にどう活かせるのか、そして私自身がどう活かしているのかを紹介していきます。
心不全の患者さんへの対応マニュアルを自分なりに作ってみる
本書では、心不全の治療薬がそれぞれ数ページにわたって丁寧に解説されています。その分、情報量が多く、実際の現場ではすぐ本書を開いて確認するのは現実的に難しい場面もあります。
そのため、私は薬ごとの注意点をあらかじめ簡潔に整理しておくようにしています。本書を参考にして、自分なりのフォローアップ項目をまとめておくと、日々の投薬指導や副作用確認の際にもすぐに見返せて、実務に活かしやすくなります。
自分の薬局でよく処方される薬に絞ってまとめるだけでも十分です。
今までなんとなく交付していた心不全の薬の「抑えるべきポイント」が明確になり、患者対応中にサッと確認できます。

以下のマニュアルは、本書の内容をもとに、私自身が現場で活かすために再構成したものです。
【利尿薬(ループ利尿薬など)】
• 食欲や水分摂取は維持されているか
• 1週間以内に2kg以上の体重増減はないか
• 浮腫や呼吸苦の改善はみられるか
• 血圧低下や倦怠感、ふらつきが出ていないか
【ACE阻害薬・ARB】
• 過度の血圧低下に注意(立ちくらみ・ふらつき・視界が暗くなる感じの有無)
• 利尿薬、NSAIDsの併用がないか
• 高K血症の兆候(徐脈・めまい・だるさ・食欲低下など)がないか
• ACE阻害薬では、乾いた咳や味覚異常が出ていないか
【ARNI(エンレスト)】
• ACE阻害薬から切り替える場合は36時間の休薬が行われているか
• めまい・ふらつき・視界が暗くなるなどの血圧低下症状がないか
• 空咳の副作用が出ていないか(ブラジキニン関連)
• NSAIDsや利尿薬との併用時、脱水・腎機能悪化が起きていないか
【MRA(スピロノラクトン/エプレレノン)】
• 高K血症の症状(倦怠感・食欲不振・徐脈など)の有無
• 徐脈(50回/分以下)や倦怠感の出現がないか
• 脱水の有無(特に夏場は飲水指導も重要)
• スピロノラクトンでは、女性化乳房の有無に注意
• ロケルマなどK吸着薬との併用状況を確認
【β遮断薬(カルベジロール・ビソプロロールなど)】
• 初期投与・増量後の心不全増悪(体重増加・浮腫・息切れなど)の有無
• 徐脈(50回/分以下)や血圧低下が出ていないか
• 倦怠感・ふらつき・暗転などの低血圧症状がないか
• 服薬が継続できているか(中断していないか)
• BNPや症状悪化時は無理な増量を避ける
• 増量は2週間〜6ヶ月スパンで慎重に行う
【SGLT2阻害薬】
• 脱水症状(口渇・頻尿・めまい・立ちくらみなど)の有無
• 夏場は特に水分摂取指導を徹底
• シックデイ時には休薬を基本とする
• 初期にeGFRの一過性低下あり(継続的にモニター)
• 高K血症リスク(倦怠感・徐脈・嘔気など)に注意
• 尿路・性器感染の徴候(排尿痛・かゆみなど)に注意
• 体重・血圧・浮腫・呼吸苦など症状の変化を確認
【ベリキューボ】
• 投与開始・増量後1週間を目安に血圧の動きを確認
• ふらつき・めまい・血圧低下がないか
【ジゴキシン】
• 血中濃度の定期測定(2〜3ヶ月に1回、安定でも年1回)
• ジギタリス中毒の症状がないか(吐き気・食欲不振・視覚異常など)
• 過量投与に注意(実際は添付文書の常用量よりも低用量で十分なことが多い)
• 低カリウム血症がないか(低カリウム血症はジギタリス中毒のリスクを高めるため)
【アミオダロン】
• 血中濃度は徐々に上昇し、定常状態までに6〜9ヶ月かかり、活性のある代謝物になるまでには1年近くかかる
• 肺毒性(間質性肺炎)の早期発見が最重要(微熱・咳・息切れなど)
• 甲状腺機能障害(TSH上昇・甲状腺腫脹・頻脈・体重減少など)に注意
• TSH・FT4などの甲状腺機能検査を定期的に行う
• ジゴキシン・ワルファリン・DOACとの併用で相互作用に注意
• 呼吸器症状や体重変化、倦怠感などを本人にも説明し、早期申告を促す
フォローアップの実例

私の薬局でも本書を参考にフォローアップを行うようになりました。
具体的には、心不全に関わる薬の新規追加や増量があった際、交付後7〜10日を目安に患者さんへ電話で体調を聞き取る対応を行っています。
投薬時には、薬の変更点を説明するだけでなく、「後日お電話で体調を伺うこと」と「その内容を主治医へ報告してよいか」の2点を確認しています。
この見出しでは、実際に私が行ったフォローアップの実例をご紹介します。
処方変更後の体調が安定していることを報告をしたトレーシングレポート
処方変更後の経過を見守るフォローアップも、薬剤師にできる大切な支援のひとつです。
ここでは、フロセミド増量後の体調が安定していることを確認し、その内容を医師に報告した例をご紹介します。
【患者情報】
・70代女性
・慢性心不全
・ビソプロロール2.5mg、アムロジピン5mg、エナラプリル5mg、フロセミド40mg(今回増量)服用中
・浮腫が悪化したため、フロセミドが増量。
以下、トレーシングレポート全文です。
〇〇クリニック □□先生
【患者情報】
・患者ID:XXXXXX
・氏名:〇〇 〇〇
・生年月日:19XX年X月X日
・処方日:20XX年X月X日
・服薬後の体調確認および主治医への情報提供について、患者本人より同意取得済み
【報告】
心不全治療中で、フロセミド20→40mgに増量となった患者さまにフォローアップを行いました。増量後の体調変化・副作用の有無などを○月○日に電話にて聞き取りましたのでご報告いたします。
体調は安定しており、増量による体調不良は見られていません。
体重は前回測定より約1.2kg減少し、下腿の浮腫も改善がみられました。
口渇・ふらつき・倦怠感などの脱水症状はなく、水分摂取量は1日約1,500mLを維持されています。
排尿回数も適切で、食欲も良好です。日常生活に支障となるような症状はありませんでした。
引き続き、薬局でも体調変化に留意していきます。
ご確認のほどよろしくお願い致します。
『薬剤師力がぐんぐん伸びる 専門医がじっくり教える心不全・心房細動』の感想と気になった点
本書は、心不全に関連する薬の理解に不安がある薬剤師にとって、とても心強い1冊です。
ここでは、実際に読んで感じた本書の魅力と、気になった点を率直に紹介します。
読みやすさと内容のバランスがちょうどいい
専門書でありながら、説明はやさしめで文章もスラスラと読み進められました。
図表やまとめが適度に挿入されており、視覚的にもわかりやすく整理されています。
内容は専門的すぎず、かといって浅すぎない。

心不全・心房細動に苦手意識がある薬剤師でも、知識を積み上げながら読み進められるバランスのよさが印象的でした。
ページ数は200ページちょっとで、ちょうどよいボリューム感です。
毎日30分〜1時間のペースでも、1週間ほどで読み切れる内容でした。
時間をかけすぎずに読める一方で、実務に活かせる視点や知識はしっかり身につきます。

心不全や心房細動の勉強を始めたいという方の1冊目にオススメです。
(気になった点)現場で本書を開くイメージは湧かなかった【自己学習専用の本】
本書は調剤室に常備して辞書的に使うようなタイプの本ではありません。
自宅でじっくりと腰を据えて読み進める、自己学習向けの1冊です。

実際の現場対応中に開いて使うというイメージはあまり湧きませんでした。
とはいえ、学んだ内容は実務に直結するものばかりです。特に、心不全関連の薬の服薬指導や、フォローアップの視点は明日からでも現場で活かせます。
前述の通り、本書の内容を自分なりに整理・要約しておくことで、実務に活かしやすくなります。
患者対応中に本書を開いて確認するような使い方は現実的ではないため、事前に要点を自分の中で落とし込んでおく姿勢が大切です。
この本の知識をもとに別の循環器関連の本も読みたくなった
本書を読んで、心不全や心房細動についての知識が整理され、循環器領域へのハードルが少し下がったように感じました。
専門用語や治療薬の考え方もわかりやすく解説されており、「循環器って難しそう…」という印象がやわらいだように思います。

本書を読んだことで、「循環器関連の本をもっと読んでみたい」と思えるようになりました。
次の1冊に進むための土台作りとして、ちょうど良い内容でした。
『薬剤師力がぐんぐん伸びる 専門医がじっくり教える心不全・心房細動』をオススメできる人
本書は、循環器に苦手意識を持っている薬剤師や、心不全・心房細動の薬をなんとなくで捉えている方にこそ手に取ってほしい内容です。ここでは特に本書をオススメしたい方を挙げていきます。
循環器が苦手・避けてきた薬剤師
循環器領域は、専門用語も多く、治療薬の種類も豊富なため「なんとなく苦手」と感じてきた薬剤師は少なくないはずです。
心不全や心房細動の治療方針を正面から理解しようとすると、つい敬遠してしまう気持ちもよくわかります。

本書は、そうした“苦手意識”に寄り添ってくれる1冊です。
文章はやさしめで、図や表も適度に挿入されており、テンポよく読み進められます。
しかも、実際の業務にすぐに活かせる視点が豊富に盛り込まれているため、「知識が増える楽しさ」を実感しながら学べるのが大きな魅力です。
「今さら聞けない…」と感じていた基本的な知識も、本書を通じて自然と整理されていくはずです。
循環器に苦手意識がある方こそ、ぜひ手に取ってほしい内容です。
心不全患者のフォローアップ体制を整えたい管理薬剤師
2024年度の調剤報酬改定では、「調剤後薬剤管理指導料2」が新設され、慢性心不全患者への調剤後フォローアップが薬剤師の業務として明確に評価されるようになりました。
対象となるのは、心疾患による入院歴があり、複数の循環器官用薬を服用している慢性心不全患者です。急性心不全での入院歴に加え、心筋梗塞後に心不全と診断されたケースも含まれます。
この算定を目指して、フォローアップの体制を整えたいと考えている管理薬剤師の方も多いのではないでしょうか。
本書には、心不全治療薬ごとのフォローアップ項目や確認すべき症状が丁寧に整理されており、調剤後の観察ポイントをマニュアル化する際の参考になります。

制度への対応だけでなく、患者さんの安全を守る取り組みにもつながる内容です。算定に向けて体制を整えたい管理薬剤師に、ぜひ手に取っていただきたい1冊です。
トレーシングレポートを出したい薬剤師
トレーシングレポートを出したいけれど、どんな視点で書けばいいのか迷っている薬剤師にも、本書は大きなヒントを与えてくれます。
薬剤ごとにフォローアップ時の確認ポイントが整理されており、「何を観察し、どのように医師に伝えるか」がわかります。
また、著者は循環器領域の専門医であり、自身が実際に受け取った薬局からのトレーシングレポートも本書内で紹介されています。

医師の視点で「どういった情報がほしいのか」が具体的にわかるため、報告のハードルを下げてくれる内容です。
自己学習の取っかかりを探している人

自己学習の習慣はまだないけれど、「何か勉強を始めたい」と思っている薬剤師にとって、本書はまさに最初の1冊にピッタリです。
循環器という身近なテーマを扱っており、前提知識が少なくても読み進めやすい構成になっています。
心不全や心房細動は日常業務でも頻繁に目にする疾患であるため、学んだことをすぐに実務で活かせるのも魅力です。
「勉強したいけれど、どこから始めたらいいかわからない」という方の背中を押してくれる、そんな内容になっています。
著者紹介
志賀 剛(しが つよし)先生は、東京慈恵会医科大学の臨床薬理学講座教授です。
1988年に大分医科大学(現・大分大学)医学部を卒業後、内科を研修。
その後、自治医科大学大学院で臨床薬理学を専攻し、1993年に東京女子医科大学循環器内科に入局。
イギリス・ハーマスミス病院の臨床薬理学部門に留学し、重症心不全や不整脈の診療に長年従事されてきました。
東京女子医科大学循環器内科の准教授を経て、2019年より現職。
現在は、循環器臨床における臨床薬理学の立場から、研究・教育・啓蒙活動を幅広く行われています。
まとめ【心不全・心房細動を学び始めたい人にピッタリ】
本書は、循環器領域に苦手意識がある薬剤師でも読み進めやすく、実務に直結する視点が豊富に盛り込まれています。
服薬指導やフォローアップに自信をつけたい方にとって、確かな手応えが得られる内容です。
【本書で学べること】
• 心不全・心房細動の基本的な病態と治療薬の考え方
• 各薬剤ごとの副作用やフォローアップの視点
• トレーシングレポートやフォローアップの実例
【特にオススメできる人】
• 循環器が苦手、または避けてきた薬剤師
• 心不全・心房細動の薬を「なんとなく」で扱っていた人
• トレーシングレポートを積極的に出したいと考えている薬剤師
• 調剤後薬剤管理指導料2を薬局全体で算定していきたいと考えている管理薬剤師
• 自己学習のきっかけを探している方

循環器領域への一歩を踏み出したい薬剤師にとって、頼もしい道しるべとなる1冊です。
ぜひ、本書を通じて日々の業務に新たな視点と自信を取り入れてみてください。
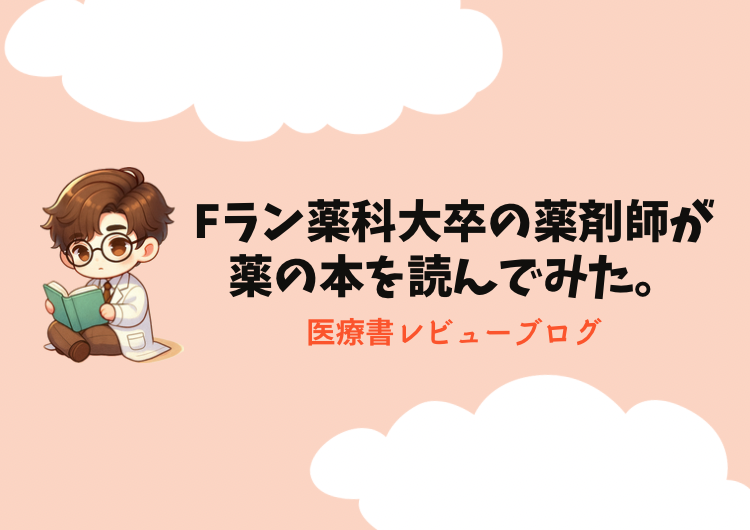
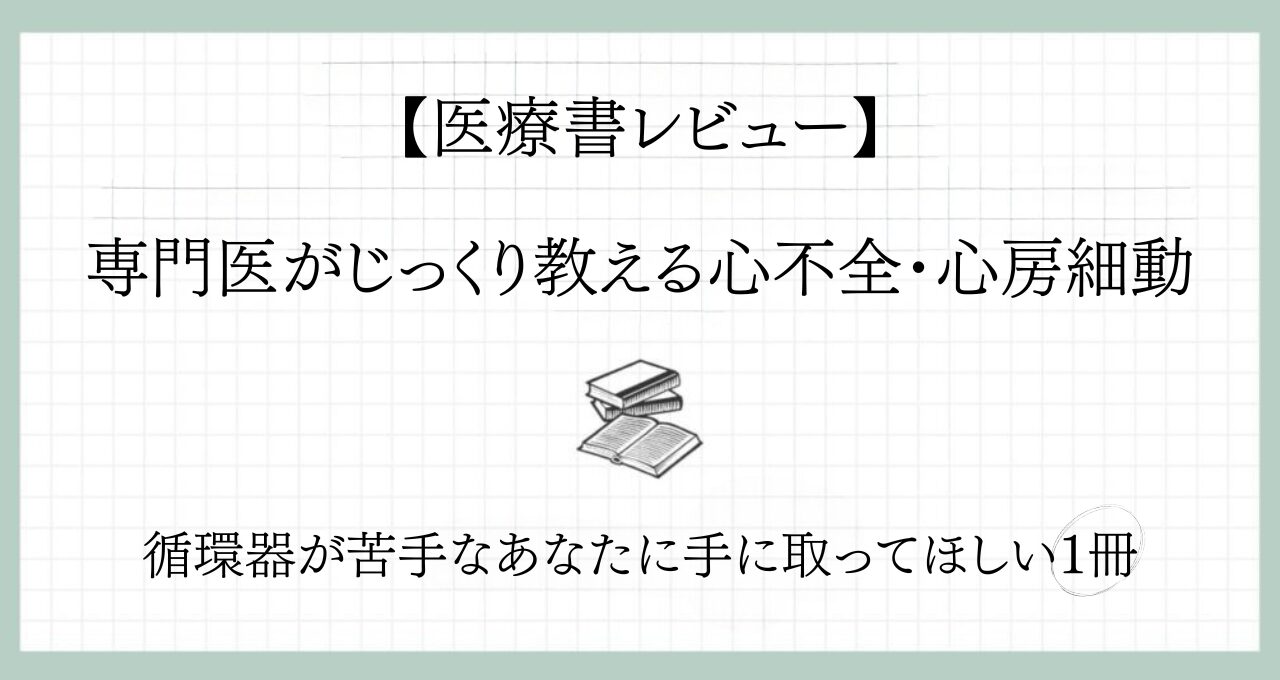


コメント