
妊娠中だけど、この薬飲んでも大丈夫ですか?

授乳中なんですが、いつもの薬はやめた方がいいですか?
薬剤師であれば、一度は経験したことのあるこの問い。
知識のアップデートが追いつかないまま現場に戻った復職組や、新人薬剤師にとっては、答えるのが難しいテーマの一つです。
そんな中、『妊娠・授乳と薬のガイドブック』は、愛知県薬剤師会が実際の相談事例をもとに作成した1冊。

妊婦・授乳婦への薬物療法に特化した実践的な知識が、症例形式+患者への説明例文付きで解説されています。
さらに、掲載薬は「質問の多かった薬」から順に選ばれており、現場でよくある質問にスムーズに対応できるように工夫されています。
本記事では、本書の特徴や活用方法、掲載されている薬の一覧、そして読んだ感想まで詳しく紹介します。
特に、現場対応に不安がある薬剤師や、これから妊婦・授乳婦の知識を学びたい方にとっては、学びと安心を与えてくれる内容です。

不安を抱えたまま現場に立ちたくない人に、最初に読んでほしい1冊です。
| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 実際の相談件数をもとに構成されており、症例解説や説明例文が充実。現場対応にも使えるが、特に自己学習用として強くオススメしたい1冊。 | |
| 実務での活かしやすさ | 一覧表や説明例は実務でも活用できるが、掲載されていない薬もある。構成上仕方がない部分もあるが、一覧表の即時対応には工夫が必要。 | |
| 自己学習への向き | 総論では妊婦・授乳婦の動態や胎児の発達に関する基礎知識や心構えが網羅され、各論では症例ベースで具体的に学べる構成。本書の内容を知識として身に着けてけば、妊婦・授乳婦対応に戸惑う場面も少なるはず。 | |
| 読みやすさ | レイアウトや見出しは整理されており読み進めやすい。一方で一定の専門用語が出てくる。初学者は調べながら読む必要がある。 | |
| コスパ | 税込3,080円で、現場対応にも学習にも使える実践的な内容。医療書としては非常にコスパが高く、新人薬剤師や復職者にも手に取りやすい価格帯。 |
『妊娠・授乳と薬のガイドブック』はどのような本なのか
妊婦・授乳婦の薬物治療について体系的に学べる1冊
本書は「第1部 妊娠と薬」「第2部 授乳と薬」の2部構成になっており、妊婦と授乳婦それぞれの薬物療法が独立して解説されています。
「妊婦に対してどう考えるか」「授乳婦にはどう対応するか」を混同せず、それぞれの立場で基礎から学べる構成です。
総論では妊婦と授乳婦、それぞれに必要な基礎知識を学べる
【妊婦】
・妊娠周期ごとの薬物影響と胎児へのリスク
・妊婦における薬物動態の変化と薬の吸収・分布・排泄
・薬を使うべきか迷ったときの判断軸
・情報源(添付文書以外の参照先)
【授乳婦】
・母乳分泌の仕組みと、乳児への健康効果
・母乳中への薬の移行性とリスク評価
・授乳を中断すべきかどうか判断する視点
・授乳中の相談に応じる際の考え方・態度
妊婦・授乳婦のどちらにおいても、薬を服用することで得られるベネフィットと、服用によって生じるリスクのバランスをどう考えるかが重要です。
ただし、そのリスクの影響を受けるのが、妊婦では胎児、授乳婦では乳児と異なるため、前提となる知識や判断軸にも違いがあります。

本書では、こうした違いを踏まえて学べる構成となっており、それぞれに適した視点を身につけることができます。
各論では薬効ごとに使える薬・注意すべき薬が症例ベースで学べる
各論では薬効ごとに分類されており、妊婦・授乳婦それぞれについて、「使ってよいかどうか」「使うなら何に注意すべきか」といったポイントが整理されています。
・解熱消炎鎮痛薬
・抗生物質・鎮咳薬
・抗ウイルス薬
・抗アレルギー薬
・喘息治療薬
・消化器官用薬
・抗うつ薬
・睡眠薬
・ステロイド外用薬
・飲酒・喫煙
・ワクチン(妊婦のみ)
後半にはQ&A形式の相談事例。現場対応の引き出しを増やせる
後半にはQ&A形式の相談事例集も収録されており、「市販薬を飲んでしまった」「授乳中に予防接種をしてもいい?」といった、実際の相談場面に近いケースからも学べます。
どのようにリスクを説明し、患者と信頼関係を築くかという視点も含まれており、服薬指導の質を高めたい薬剤師にとって実践的なヒントが得られます。
妊婦・授乳婦の薬物治療に関する知識を、基礎から段階的に身につけたい人にとって、勉強のスタートにちょうど良い1冊です。
薬剤師会が編集・発行した、現場の実例が詰まった実用書

本書は、愛知県薬剤師会が編集・発行した実用書です。
もともとは、妊婦や授乳婦の薬物療法に関する情報不足や不安の声を受けて、愛知県薬剤師会が調査・研究に乗り出したのが始まりでした。
取り組みの内容は、
・妊婦・授乳婦が薬を不安に思う背景を知ること
・医師による投与の実態を把握すること
・医療機関や薬局での情報の得られ方を調べること
など、薬剤師がどのように支援できるかを考えるための、基礎となる情報を集めるものでした。
こうした活動はすぐに形になったわけではなく、十分な情報や体制がない中で試行錯誤を繰り返しながら進められました。
事業は少しずつ発展し、手引書やQ&A集の作成、養成講座の開講へとつながっていきました。
そして12年にわたる積み重ねの成果として、現場の薬剤師が安心して使える実践的な知識を1冊にまとめたのが本書です。

本書は、薬剤師が妊婦・授乳婦への対応に自信を持てるようになるための、信頼できる実践書です。
実務にも活かせるが、じっくり学ぶ自己学習用として最適
本書には、実際の現場でそのまま使える一覧表や説明例文なども掲載されており、実務の中で活用できる場面も多くあります。
ただし、すべての薬が網羅されているわけではなく、掲載のない薬については別の情報源を調べる必要があります。

そのため、現場対応の“決定版”というよりは、薬剤師が妊婦・授乳婦への理解を深め、患者さんへの説明や判断の引き出しを増やすための「学び始めの1冊」として適していると感じました。
基礎から実践にかけて、無理なく読み進められる構成になっているので、これから妊婦・授乳婦の薬物療法について学びたい人にぴったりの1冊です。
妊婦・授乳婦対応の経験が豊富な方にとっても、新たな気づきが得られる内容になっています。
「よく聞かれる薬」から掲載。現場対応にすぐに役立つ構成
本書に掲載されている薬剤は、妊婦・授乳婦からの相談件数が多かった順に選ばれています。
これまでに集められた質問は、合計で8,000件以上にもおよび、その中から特に頻度の高い薬が優先的に取り上げられています。
そのため、「現場で実際によく聞かれる薬」が集中的に掲載されており、日々の対応に直結する構成となっています。

薬剤師が直面しやすい疑問や相談に対応できるよう、内容は絞り込まれつつも、的確で現実的な情報が選ばれており、実務の中での即戦力として役立ちます。
本書にない薬はどうする?妊婦・授乳婦に使える情報源も紹介
本書はよくある相談を中心に構成されているため、すべての薬剤が網羅されているわけではありません。

掲載されていない薬を調べる際は、信頼できる情報源を活用することが重要です。
本書では、参考として以下のような情報源が紹介されています。
書籍
・『薬物治療コンサルテーション 妊娠と授乳』
→ 妊娠・授乳期の症例ごとの対応を詳しく解説。薬剤の分類表もあり実践向き。
・『実践 妊娠と薬』
→ 1万件超の相談データをもとに安全性を数値評価。情報の質と量が明示されている。
・『Drugs in Pregnancy and Lactation』
→ 海外で広く使われている英語の専門書。推奨分類や文献レビューが充実。
ウェブサイト
・DART(米国):催奇形性や生殖毒性に関する文献データベース
・MotherToBaby:Q&A形式のファクトシートを多数掲載
・FDA分類:A~Xのリスク分類で世界的に使用
・TGA分類(豪州):ヒト・動物データに基づいた分類
それぞれに分類方法や収録範囲が異なるため、必要に応じて複数の情報を照らし合わせながら判断することが推奨されています。
本書では、すべての薬を網羅していないからこそ、掲載がないときにどう調べ、どう判断するかを学ぶことができます。
答えを探すだけでなく、根拠をもとに考える姿勢を育ててくれる1冊です。
『妊娠・授乳と薬のガイドブック』を現場で活かすには
本書は自己学習に適した構成ながら、実際の現場でも活用できる場面があります。
特に一覧表は、妊婦・授乳婦からの「この薬、大丈夫?」という問いに即時対応する際に便利です。
「この薬、大丈夫?」にすぐ答えたいときは一覧表が便利
妊婦・授乳婦からの「この薬、飲んでも大丈夫ですか?」という相談に対して、素早く根拠を持って答えるために、本書に掲載されている一覧表は非常に役立ちます。
一方で、一覧表は複数のページに分かれて掲載されており、妊婦用と授乳婦用が別構成になっているため、必要な情報にたどり着くまでにやや手間がかかります。
巻末の薬品名索引では、たとえば
・カルボシステイン(妊婦)……○○ページ
・カルボシステイン(授乳婦)……□□ページ
のように、対象ごとにページが分かれて記載されており、検索の助けにはなりますが、急いでいる場面ではやや探しにくさを感じることもあります。
そのため、即時対応をスムーズにするために、インデックスを貼る、一覧表をコピーしておくなど、事前のひと工夫があるとより活用しやすくなります。
一覧表をすぐに確認できるように本にインデックスを貼る
本にインデックス(付箋)を貼っておくと、索引を使わずにすぐ一覧表を開けるようになります。
準備は簡単で、よく使うページに目印を貼るだけ。現場でパッと確認したいときに便利です。
手軽に始められる工夫として、まず試してみるのにオススメです。
一覧表のページをコピーしておき、インデックス付きのファイルにまとめておく
一覧表をコピーしておき、妊婦用・授乳婦用の2つのファイルに分けてまとめておく方法は、現場での即時対応に特にオススメです。
インデックスをつけておけば、薬効ごとにすぐアクセスできるツールになります。
調剤室に置いておけば、誰でもすぐに確認できます。
コピーや印刷の手間はかかりますが、その分だけ使いやすいツールです。
掲載されている薬
本書に掲載されている薬剤は、妊婦・授乳婦からの質問が多かったものを中心に構成されています。
薬効ごとに分類されており、以下のような薬が掲載されています。
解熱消炎鎮痛薬
・アセトアミノフェン
・ロキソプロフェンナトリウム水和物
・イブプロフェン
抗生物質
・セフカペンピボキシル塩酸塩水和物
・セフジトレンピボキシル
・クラリスロマイシン
鎮咳去痰薬
・カルボシステイン
・デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
・ジメモルファンリン酸塩
抗ウイルス薬
・オセルタミビルリン酸塩
・ザナミビル水和物
・ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
抗ヘルペスウイルス薬
・バラシクロビル塩酸塩
・アシクロビル
・ビダラビン
抗アレルギー薬
・フェキソフェナジン塩酸塩
・ロラタジン
・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
花粉症外用剤
・モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物(点鼻)
・オロパタジン塩酸塩(点眼)
吸入ステロイド
・ブデソニド
・フルチカゾンプロピオン酸エステル
吸入β₂刺激薬
・プロカテロール塩酸塩水和物
・サルブタモール硫酸塩
・ホルモテロールフマル酸塩水和物
・サルメテロールキシナホ酸塩
消化器官用薬
・酸化マグネシウム
・ピコスルファートナトリウム水和物
・センノシド
・メトクロプラミド
・ファモチジン
抗うつ薬
・パロキセチン塩酸塩水和物
・セルトラリン塩酸塩
・フルボキサミンマレイン酸塩
・エスシタロプラムシュウ酸塩
・デュロキセチン塩酸塩
・ミルタザピン
睡眠薬
・ゾルピデム酒石酸塩
・エチゾラム
・フルニトラゼパム
外用ステロイド
・デルモベート
・アンテベート
・リンデロン-V
・リドメックスコーワ

いずれも薬局でよく扱う薬が中心に掲載されているため、日々の現場で受ける質問の多くに対応できると思います。
『妊娠・授乳と薬のガイドブック』を読んだ感想・気になった点
ここからは、実際に本書を読んで感じたことをまとめます。
良かった点と気になった点を率直にご紹介します。
読みやすい!妊婦・授乳婦に対する薬をこれから学ぶ人にピッタリ

文章が丁寧で、構成もシンプルにまとまっているため、専門書でありながらスラスラと読み進めることができました。
もちろん、専門書なので、必要に応じて用語を調べながら読む場面もあります。
ただ、それが負担に感じるほどの難しさではなく、調べることで自然と知識が定着していく感覚がありました。
「難しすぎず、でもちゃんと学べる」ちょうどいい難易度の1冊だと感じました。
(気になった点)掲載されていない薬では即時対応が難しい場面も
掲載されている薬はよく質問されるものに厳選されており、現場対応で出会う頻度も高いため非常に実用的です。

一方で、すべての薬剤が網羅されているわけではないため、「載っていない薬にどう対応するか」に悩む場面もあるかもしれません。
特に、薬の選択肢が多い領域や、新しい薬が処方されるケースでは、本書だけでは対応しきれないと感じることもあります。
その場合は、本書で紹介されている情報源(書籍やWebサイト)を活用して判断する必要があります。
本書は“完結型”の辞書ではなく、“基礎+調べ方の道筋”を教えてくれる本、と捉えておくとよいと思います。
自己学習用として特にオススメ。現場活用もできるが補助的に

本書の最大の強みは、体系的に学べる構成と丁寧な解説にあります。
妊婦・授乳婦の薬物療法をこれから学びたい方にとって、自己学習用の参考書として非常にオススメです。
もちろん現場でも活用できますが、即時対応のツールというよりは、知識の引き出しを増やす補助資料として使うのが向いています。
一覧表や症例の例文など、実務にもつながる要素は多く、「現場で使える勉強本」として位置づけるとしっくりきます。

たとえば、現場でそのまま使えると感じた具体例もありました。
授乳婦の方から

インターネットで調べたら、添付文書に“授乳を避けること”と書いてあった
と不安の声があった場面。
その際の説明として紹介されていた文章が非常にわかりやすく、テンプレートとしても活用できる内容でした。
おそらくインターネットで調べて出てきたのは製薬会社が作成している添付文書という医療従事者向けの資料に書かれていた文言ではないかと思います。これは,動物に薬を与えてわずかでも乳汁移行が認められるとそのように書かれることになっています。しかし,実際にこの薬を飲んだお母さんの母乳中の薬の量はわずかであることがわかっています。また,この薬には粉薬もあって,赤ちゃん自身が服用することもある薬です。母乳を介して赤ちゃんが飲む薬の量は,赤ちゃんの治療薬として飲む場合の薬の量と比べてとても少ないです。お母さんが健康で快適に過ごすことも,子育て中はとても大切です。授乳と両立できる薬は安心して服用していただいて,体調を整えていきましょう。
(引用:『妊娠・授乳と薬のガイドブック』愛知県薬剤師会 妊婦・授乳婦医薬品適正使用推進研究班編集、じほう、2019年、p.184)
このような説明だと、添付文書の記載の背景や科学的根拠の程度を伝えながら、患者さんの不安を和らげることができます。

専門的な説明になりすぎず、相手に安心感を与える言い回しとして非常に参考になります。
『妊娠・授乳と薬のガイドブック』をオススメできる人
妊婦さん・授乳婦さんへの対応は、薬剤師にとって迷いや不安の多い領域です。
本書は、これから学び始めたい人にも、しばらく現場を離れていた人にも、やさしく寄り添ってくれる構成になっています。

ここでは、実際に読んで「この人にはぜひ読んでほしい」と感じた対象を紹介します。
妊婦・授乳婦の勉強を始めたい人
妊婦さんや授乳中の方への薬の説明に不安を感じている方や、これからしっかりと勉強を始めたいと思っている方に、本書はまさにピッタリです。

基礎知識から具体的な症例までをカバーしており、「まずはこの1冊から」という入り口として最適な内容です。
薬の安全性だけでなく、どのように伝えるかという視点も盛り込まれているため、実務への応用もイメージしやすく、学んだことをそのまま活かしやすい構成になっています。
産休・育休から復帰する薬剤師。実体験が活きる1冊
妊娠・出産・授乳を経験した薬剤師にとって、本書は「自分の経験を知識として整理し直す」うえで非常に役立つ内容です。
実体験と照らし合わせながら読み進められるため、内容の理解がスムーズで、患者さんへの説明にも説得力が増します。
「自分が不安だったこと」「こう言ってもらえたら安心できた」などの記憶と重ねながら読むことで、単なる知識のインプットではなく、患者視点に立った学びにつながる1冊です。
妊婦・授乳婦への伝え方に自信がない薬剤師

薬の安全性はわかっていても、どう伝えれば安心してもらえるのか分からない
そんな悩みを抱えている薬剤師にとって、本書は心強い味方になります。
患者さんへの説明文が症例ごとに掲載されており、言葉の選び方や伝える順番など、実際の会話をイメージしながら学ぶことができます。

難しいことをやさしく伝える力は、現場で信頼を得るためにも欠かせません。
本書は、その練習台としても最適です。
妊婦・授乳婦と関わる看護師や助産師、他職種の方にもオススメ
本書は薬剤師向けに編集されていますが、妊婦さん・授乳中の方と日常的に関わる看護師や助産師などの他職種の方にも、ぜひ手に取っていただきたい内容です。
「この薬、大丈夫ですか?」という質問に対して、根拠を持って対応できる視点が得られますし、薬剤師との連携においても共通認識を持つ助けになります。
薬に詳しくない方でも読み進めやすい構成になっており、現場での不安を減らす1冊として活用できます。
編集・著者紹介
本書は、愛知県薬剤師会の研究班を中心に、薬剤師・医師・大学関係者・製薬企業など、多職種の専門家が協力して編集・執筆した一冊です。
薬剤師も編集に携わっているため、薬局・病院の実務に活かしやすい視点が随所に盛り込まれており、日常業務にすぐ役立つ内容となっています。
一方で、医師や研究者の視点も加わっているため、薬の安全性に関する解説にはエビデンスや根拠がしっかりと示されており、内容の信頼性も高く保たれています。
まとめ【妊婦・授乳婦領域の自己学習の1冊目】
妊婦・授乳婦への薬物療法は、薬剤師にとって判断や説明が難しい分野です。
本書は、基礎から実務までを丁寧にカバーしており、これから学びたい人にも、現場で迷いがちな場面でも、大きな支えになる内容です。
【本書の特徴】
・妊婦・授乳婦をそれぞれ独立して扱った構成
・症例ベースの各論+一覧表で即時対応にも応用できる
・患者への説明例文が豊富で、現場の言葉選びの参考になる
・信頼できる情報源も紹介されており、調べ方も学べる
【本書で学べること】
・妊娠・授乳期の医療に必要な幅広い基礎知識
・よく使われる薬の妊婦・授乳婦への使用可否と注意点
・患者さんに安心感を持ってもらうための伝え方
【オススメできる人】
・妊婦・授乳婦の薬物療法を初めて学ぶ薬剤師
・産休・育休から復帰し、感覚を取り戻したい薬剤師
・患者さんへの伝え方に自信がない医療職の方
・妊婦・授乳婦と関わる看護師、助産師、医師など他職種の方

正しい知識と伝え方を身につけることで、目の前の患者さんに安心を届けられるようになります。
不安を抱えたまま現場に立ちたくない人に、最初に読んでほしい1冊です。
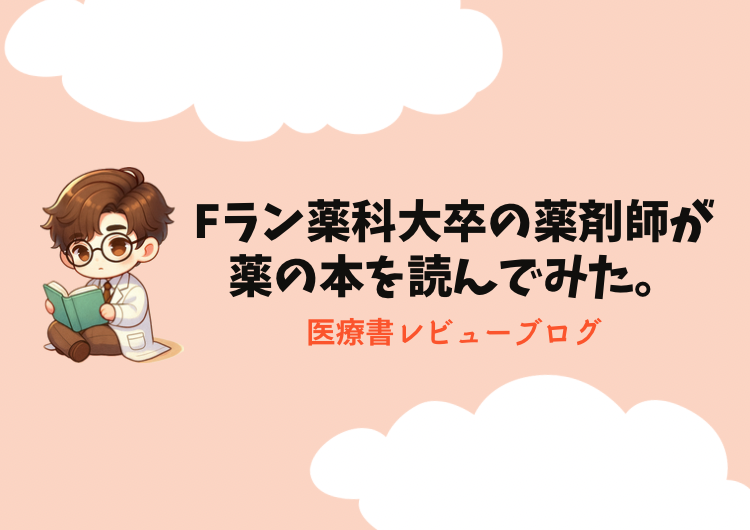
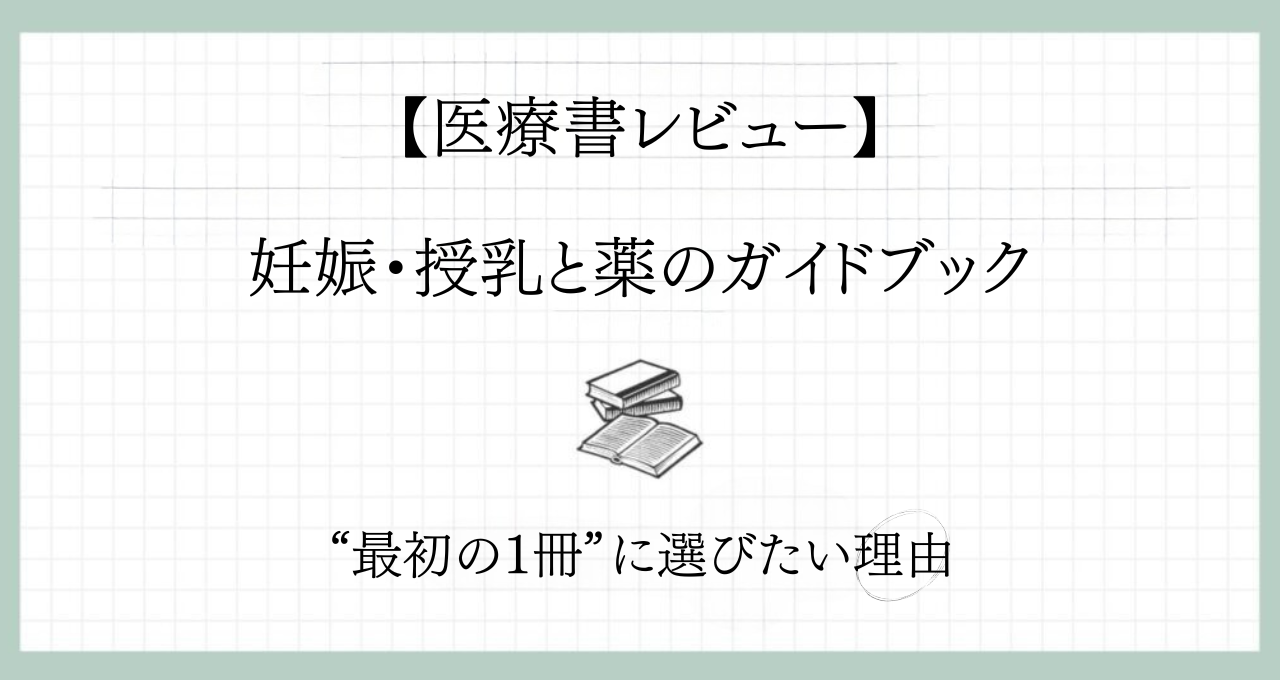


コメント