外来の処方せんを受け付ける薬剤師であれば、日々の業務の中で、精神科や心療内科の処方せんを目にする機会は少なくないと思います。
ですが、その薬を交付する際に——

もしこの患者さんが妊娠したら?
この薬は胎児にどんな影響を及ぼす可能性があるのか?
妊娠・出産にまつわる精神疾患には、どんなものがあるのか?
そんな想像ができる薬剤師は、どれほどいるでしょうか。
本記事では、精神科薬と妊娠・授乳に関わる実務的な判断や支援の考え方を学べる1冊、
『向精神薬と妊娠・授乳 改訂3版』をご紹介します。
薬の安全性を一方的に断言するのではなく、「どのように考えるべきか」「どう伝えるべきか」を薬剤師として身につける。
この本は、そんな“正解のない領域”に向き合うための、考え方を与えてくれる1冊です。
妊婦・授乳婦と接する機会が多い薬剤師にも、メンタルクリニック処方を多く扱う薬剤師にも、役立つ視点が詰まった本です。
妊娠適齢期の女性を前に「何を伝えるべきか」と悩んだことのある薬剤師にとって、きっと得られるものがあると思います。
| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 活用できる人にとっては星5をつけたくなるほどの良書です。 特に、メンタルクリニック門前や、妊婦・授乳婦と関わる薬剤師には強くオススメできます。 一方で、対象が限定的なため、総合評価は星3。 内科や一般処方が中心の薬剤師には、『妊娠と授乳 改訂4版』の方が汎用性が高いと感じました。 | |
| 実務での活かしやすさ | 患者対応や、トレーシングレポートを出す際の根拠としても活用しやすく、実務に直結する1冊です。 すぐにすべてを使いこなすのは難しいかもしれませんが、手元にあると安心できる本です。 | |
| 自己学習への向き | 全体として一読の価値はありますが、1回読んだだけで使える知識になるほど簡単な内容ではありません。 また、「じっくり学ぶパート」と「症例対応時に必要に応じて読み返すパート」に分かれています。通読よりも、実務と並行して繰り返し活用する読み方が合っています。 | |
| 読みやすさ | 専門用語が多く、読了には時間がかかります。ただし、文章は整理されており、しっかり読み込めば確かな知識が得られます。 | |
| コスパ | 税込3,960円。医療書としては標準的な価格帯です。内容の専門性・情報量を考えると、コスパの良い1冊と感じます。 |

『向精神薬と妊娠・授乳 改訂3版』とはどのような本なのか
妊娠適齢期の女性に向精神薬を交付する際に、押さえておきたいポイントが学べる

本書では、妊娠適齢期の女性に向精神薬を交付する際に必要な「伝え方」や「考え方」を学ぶことができます。
向精神薬には催奇形性の可能性がある薬もあり、妊娠後にインターネットで情報を調べた妊婦が、自己判断で服薬を中止してしまうことがあります。
その結果、精神疾患が悪化し、妊婦・胎児の両方に薬のリスクを上回る悪影響が出るケースも少なくありません。
こうした事態を未然に防ぐためには、薬剤師が妊娠適齢期の女性への対応で押さえておくべきポイントがあります。
たとえば、薬の“安全性”を単純に判断するのではなく、妊娠初期の胎児への影響(催奇形性)や、妊娠継続に与える影響、中止した場合の母体への精神的リスクなど、妊婦側に生じうるリスクを多面的に考える必要があります。

「この薬は安全です」と断定するのではなく、「こういう可能性があります」と中立的な立場で説明する姿勢が求められます。
また、治療を中断すること自体のリスクについても、忘れてはなりません。
薬の副作用を恐れるあまり、精神疾患そのものが悪化してしまうと、母体・胎児に大きな負担がかかります。
本書では、このような“薬を使わないリスク”にも触れており、服薬継続の判断に必要なバランス感覚を養うことができます。
さらに、患者が主体的に判断できるよう、薬剤師が情報提供や対話を通じて支援する姿勢も、本書を通して学べる重要な視点です。

あくまで薬の継続・中止の最終的な決定は、患者と主治医です。
薬剤師が判断を下すのではなく、患者自身が納得して選べるように情報を提供し、主治医との相談を促す——
そのプロセス全体を支える「伝え方」や「関わり方」を学べる構成になっています。
妊娠にまつわる精神疾患を学べる
本書では、妊娠・出産期に特有の精神疾患について、薬剤の使用とあわせて詳しく解説されています。

正直、私自身はほとんど知らない疾患ばかりでした。
普段、薬局で働いていてもこうした病名に触れる機会は少ないと思います。
妊娠が必ずしも“嬉しいこと”とは限らない現実や、こうした精神疾患と向き合っている妊婦さんが一定数いるのだと気づかされました。
たとえば、以下のような疾患が紹介されています。
• 周産期のうつ病(産前うつ・産後うつ)
• 妊娠悪阻に伴ううつ状態(にんしんおそ:重いつわりにより、気分の落ち込みなどが起きる状態)
• 妊娠中・産後の双極性障害
• 周産期の不安障害・パニック障害
• 妊娠中の統合失調症の再燃
• 強迫性障害や心気症(健康不安)
• PTSD(過去の流産・中絶・出産でのつらい経験が原因となる心の傷)
• 摂食障害
• ボンディング障害(赤ちゃんへの愛着が持てない状態)
• 周産期の希死念慮や自殺念慮
これらの疾患は、妊娠中のホルモン変化や環境変化が大きく影響することもあり、通常とは異なる対応が求められるケースが少なくありません。
本書を通じて、妊娠というライフイベントが精神状態にどのような影響を与えるか、その背景を深く知ることができます。
正解が1つではない問題に向き合うための考え方が学べる
同じ向精神薬を服用している妊婦さんでも、その薬を継続するのか中止するのか——最適な選択肢は人それぞれ異なります。
その判断に影響する要素は多岐にわたります。
• 精神疾患の重症度や既往歴
• 薬の用量や投与期間
• 薬に関するリスクデータの受け止め方(患者・家族の価値観)
• 妊娠の経過やタイミング(中止できる場合は妊娠する前に中止しておくのがベスト)
• 周囲の支援体制や家庭環境
• 主治医との信頼関係
• 「薬をやめたい」という希望の強さ、あるいは「再発への不安」の大きさ
本書では、そうした複雑な背景の中で薬剤師ができる関わり方や、断定せずに“考える材料”として情報を届ける姿勢が丁寧に解説されています。
「正解を伝える」のではなく、「一緒に考える」——
そのための視点や、複雑なケースにどう向き合うかの考え方を得られる1冊です。
『妊娠・授乳 改訂4版』との違いと使い分け
妊婦・授乳婦の薬物治療について書かれた本はたくさんありますが、薬局に置いておき、すぐに調べたい場面で役立つ1冊としてオススメなのが『妊娠・授乳 改訂4版』です。

妊娠中・授乳中に薬を使っていいかどうか、即時に判断が求められる場面で何度も助けられてきました。
当ブログでは、この本を別の記事でも紹介しています
今回ご紹介している『向精神薬と妊娠・授乳 改訂3版』と『妊娠・授乳 改訂4版』は、いずれも伊藤真也先生と村島温子先生が編者として関わっている本です。
伊藤真也先生はトロント小児病院名誉教授であり、WHOの薬剤評価担当アドバイザリーパネルメンバーも勤めた小児科領域の世界的な専門家です。
村島温子先生は、妊娠と薬の研究を長年リードしてきた「一般社団法人 妊娠と薬情報研究会」の理事長を務め、妊婦・授乳婦への医療支援に精通した内科医です。
どちらの本も薬剤師として学びの多い内容です。
ここでは、2冊の違いや、それぞれをどんな場面・どんな立場の薬剤師にオススメできるかを整理してご紹介します。
薬局でよく使うのは『妊娠と授乳』
薬局で働いていると、妊婦さんや授乳中の方から「この薬、大丈夫ですか?」と聞かれることがあります。
そんなとき、すぐに手に取りたくなるのが『妊娠・授乳 改訂4版』です。
この本の魅力は、なんといっても一覧表のわかりやすさ。

妊娠中・授乳中に使ってもいいかどうかが、薬効分類ごとにまとめられており、そのまま患者さんへの説明にも使えるほどシンプルで実用的です。
また、安全性に関するデータが少ない薬についても、胎盤や母乳への移行率、薬効、薬物動態などから理論的にどう考えるかが記載されており、判断の助けになります。
調べたいときにすぐ調べられる。薬局に1冊あると安心できる——
そんな「即時対応」に強いのが『妊娠と授乳』です。
精神科門前なら『向精神薬と妊娠・授乳』がオススメ
『妊娠・授乳 改訂4版』が即時対応に強い本だとすれば、
『向精神薬と妊娠・授乳 改訂3版』は、向精神薬を扱う薬局で、妊娠をめぐる判断に“立ち止まる場面”に寄り添ってくれる本です。
たとえば、若年女性の患者さんが向精神薬を服用中で、妊娠希望があるとき。
あるいは、将来の妊娠に備えて、あらかじめ薬のリスクとベネフィットについて話をしておきたいとき。
妊娠が判明した後に自己判断で中止してしまうケースを防ぐためにも、前もって正しい知識を伝えることが薬剤師に求められます。
また、患者本人だけでなく、医師や家族とも連携しながら、より良い選択肢を探っていくサポートが求められます。

本書には、服薬の継続・減量・中止といった選択肢に対し、どのような視点で整理し、患者とどう関わるかが丁寧に解説されています。
特に精神科門前では、患者との信頼関係や情報提供のあり方が、服薬継続の大きな分かれ道になることもあります。
「即答」ではなく「一緒に考える」——
そんな薬剤師の姿勢を支えてくれるのが、『向精神薬と妊娠・授乳 改訂3版』です。
使い分け表
| 比較項目 | 妊娠・授乳 改訂4版 | 向精神薬と妊娠・授乳 改訂3版 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 妊娠中・授乳中の薬の使用可否をすぐに確認する | 妊娠適齢期の女性に向精神薬を処方・交付する際の判断支援 |
| 向いている薬剤師 | 一般薬局、婦人科・小児科門前の薬剤師 | 精神科門前、向精神薬を扱う機会が多い薬剤師 |
| 特徴 | 一覧表が豊富で即時対応しやすい | 疾患背景やリスクベネフィットの考え方が詳しい |
| 使いどころ | 服薬指導前の即時確認、薬歴入力時 | 妊娠希望の患者や若年女性への中長期的な対応 |
| カバー範囲 | 診療科を問わず、全領域の薬に対応 | 精神科領域に特化、周産期精神医療の視点が充実 |
現場での活かし方
本書は知識を深めるだけでなく、現場での対応にもつながる内容が詰まっています。

実際に薬局でどのように活かせるか、私の実践例を交えてご紹介します。
妊婦・授乳婦からの質問・不安に“後日丁寧に答える”ために使う
実際の質問対応では、まず『妊娠と授乳 改訂4版』を使用します。
たとえば、妊娠中の女性から

この抗うつ薬、飲み続けても大丈夫ですか?
と聞かれたとき。
あるいは、授乳中の母親から

薬は母乳に出ませんか?
と質問を受けたとき。
その場で服用中の薬を一覧表から探し、妊娠期・授乳期それぞれの安全性を確認する——
こうした即時対応に非常に強いのが『妊娠と授乳 改訂4版』です。
一方で、『向精神薬と妊娠・授乳 改訂3版』はその場での対応には適していません。ですが、質問にすぐには答えず、後日あらためて説明する際に、根拠や背景を整理する目的で活用できます。
特に向精神薬は、「使っても大丈夫」という言葉だけでは不安を拭えない患者さんも多くいます。

特に、患者の不安の背景にある精神疾患の特性や、妊娠・出産期に起こりやすい心理的変化についても理解しておきたいときに、本書が役立ちます。
また、本書にはプレコンセプションケア(妊娠を希望する前の段階での支援)の実例も紹介されています。
向精神薬を服用している妊娠適齢期の女性に対して、どのような配慮が必要かを考えるヒントにもなります。
その場で即答するのではなく、いったん持ち帰って調べ、必要な情報を整理してから丁寧に説明する——そんな薬剤師の姿勢に、本書は応えてくれる1冊です。
予期せぬ妊娠や自己中断を防ぐために薬局単位で取り組んだこと
日常業務では『妊娠と授乳 改訂4版』を使う場面が多いものの、『向精神薬と妊娠・授乳改訂3版』を読むことで、新たな視点や気づきが得られました。
とくに強く印象に残ったのが、「プレコンセプションケア(妊娠を希望する前の段階からの支援)」の重要性です。

ここでは、その考え方を踏まえて、薬局で実際に行った取り組みをご紹介します。
将来の妊娠を見据え、向精神薬を服用している若年女性へのアプローチとして、薬局単位でできることを考えました。
10−20代女性の処方せんを抽出し、薬歴に聞き取り指示を入力
まず、薬局のレセコンからメンタルクリニックを指定し、年齢別に来局した患者を検索しました。
向精神薬を服用している10〜20代の女性患者を抽出し、対象者の薬歴に「次回来局時に妊娠希望の有無、妊娠の可能性について聞き取りを行う」といった申し送りを入力しました。
実施にあたっては、薬局内のスタッフ全員にプレコンセプションケアの概念を共有し、今回の取り組みの意義や目的をあらかじめ説明しました。
そのうえで、聞き取りの際には「立ち入ったことをお伺いして恐縮ですが……」といったクッション言葉を添えるように伝え、デリケートな話題であることに十分配慮した声かけをお願いしました。
現場が混乱しないよう、実施タイミングや対応方法についても事前に確認・指導を行いました。

なお、すべての患者に一律で聞き取りを行ったわけではありません。
処方内容が頻繁に変わっていたり、明らかに状態が不安定そうな方には声かけを控えました。
代わりに、処方内容が一定で、体調が安定していそうな患者さんに対して、聞き取りを行いました。
患者さんの立場に立って考えると、気持ちが不安定なときに将来の妊娠について尋ねられても、「そんなどうでもいいことを聞くな」と感じさせてしまう可能性があると考えたからです。
妊娠希望がある場合は、薬の影響と自己中断のリスクを説明
妊娠を希望していることがわかった患者さんには、現在服用している薬について、リスクと背景を丁寧に伝えるようにしました。
その際、「この薬は胎児に影響があります」と断定的に伝えるのではなく、「このような可能性がある」という表現にとどめ、判断は主治医と相談して行うようお話ししました。

薬剤師は、患者さんやご家族と「どうしていくのがベストか」を“一緒に考える”立場です。最終的な判断や決定は、患者本人と主治医にあります。
また、自己判断で薬を中止してしまうことのリスクについてもお伝えしました。精神疾患が再燃・悪化することで、妊娠中の体調や生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
加えて、本書では「ベースラインリスク(薬を使用していなくても、もともと胎児に先天異常が起こる確率)」についても解説されています。
一般的に、妊婦が薬を服用していなくても、2〜3%程度の割合で胎児に先天異常は発生するとされており、薬の安全性を考えるうえではこの基準と比較して考える必要があります。
妊娠を望む患者さんに対しては、薬の影響ばかりを強調するのではなく、もともとのリスクや病気そのものの影響にも目を向けながら、冷静に伝えるよう心がけました。
希望があれば、主治医へトレーシングレポートを提出
相談を続けていく中で、関係性が深まってくると、患者さんから「先生に薬剤師さんから伝えてほしい」と言われることがあります。
そのような場合には、患者さんの同意を得たうえで、主治医宛にトレーシングレポートを提出し、情報提供を行いました。
このような文書を作成する際に特に注意しているのは、次の3点です。
・処方内容を否定するような表現は避けること。
「妊婦に現在の処方薬は避けるべきです」といった断定的な言い方は良くありません。
・患者さんにどう説明したか、どんな不安がありそうだったかなど、薬剤師としての観察や対応を丁寧に伝えること
・感覚や主観ではなく、本書に記載されている情報や文献など、客観的な根拠に基づいて伝えること
特に精神科領域では、患者さんの不安に過敏に反応しすぎても、かえって混乱を招くことがあります。
薬剤師の立場として、慎重に・冷静に伝える姿勢を意識しています。
『向精神薬と妊娠・授乳 改訂3版』の感想と気になった点
読んでよかったと思える、確かな学びがあった
本書を通じて、妊娠にまつわる精神疾患について、学ぶことができました。

妊娠・授乳という行為が、身体的にも精神的にも非常に大きな負担を伴うことをあらためて考えさせられます。
ボンディング障害や産後うつ、パーソナリティ障害といった疾患は、私自身の業務ではほとんど触れる機会がなく、初めて知ったものもありました。
「妊娠=幸せな出来事」とは限らない。その現実に気づけたことも、大きな学びのひとつです。
こうした気づきを経て、妊娠や服薬に不安を抱える若年女性と向き合うとき、より丁寧に寄り添える薬剤師でありたいと考えるようになりました。
メンタルクリニックに受診している若年女性にアプローチする引き出しが増えた
これまで私は、メンタルクリニックの薬を交付する際に「妊娠の可能性があるか?」と尋ねたことはありませんでした。
しかし本書を通じて、薬局でもプレコンセプションケア(妊娠を考える前からの健康支援)に取り組めることを知り、妊娠前から関われる新たなアプローチがあると気づかされました。
今では、薬局単位でメンタルクリニックに通う若年女性への声かけを習慣化しつつあります。
これからも、プレコンセプションケアを薬局全体で継続的に実践していけるよう取り組んでいきます。
(気になった点)専門用語が多く、読むのに時間がかかった
本書は専門用語が多く、読み進めるのに時間がかかりました。
もちろん、専門書である以上、ある程度の難しさは避けられないのですが、それでも読み切るまでのハードルは高めです。

すべての薬剤師にとって「サクッと読める1冊」ではなく、途中で読むのを断念してしまう方も少なくないかもしれません。
内容は非常に有用です。だからこそ、少しずつでも読み進めることで、普段の業務では得られない視点や知識を身につけられる貴重な1冊だと思います。
(気になった点)全ての薬剤師に自己学習用としてオススメできるわけではない
すべての薬剤師に自己学習用としてオススメできるかというと、本書はやや対象が限られる印象です。
幅広い診療科に対応する薬剤師には『妊娠と授乳 改訂4版』の方が適していると感じます。
一方で、本書が特に力を発揮するのは、メンタルクリニックの門前薬局などで、日常的に向精神薬を取り扱う薬剤師です。

該当する方にとっては、自己学習の1冊として十分に価値があり、臨床での対応力を高める手助けになると思います。
『向精神薬と妊娠・授乳 改訂3版』どんな人にオススメか
本書は、すべての薬剤師にとって必須の1冊というわけではありません。
ですが、日常的に向精神薬を扱う方や、妊娠・授乳とメンタルの関わりに関心のある方には、特に学びが多い内容が盛り込まれています。

まさに“必要な人には強くオススメできる1冊”です。
メンタルクリニックの処方せんを扱う薬剤師
メンタルクリニックの処方せんを日常的に扱う薬剤師にとって、本書は非常に実用的です。

妊娠適齢期の女性に向精神薬を交付する際、どのような視点を持って接すればよいかが具体的に学べます。
また、妊娠が判明した後の自己中断リスクや、服薬継続の意義について、どのように伝えるべきかを考えるうえでも、本書の内容は大いに参考になります。
日々の業務の中で、プレコンセプションケア(妊娠を望む女性への事前支援)を実践したいと考える方にも、ぜひ手に取ってほしい1冊です。
婦人科、小児科の処方せんを扱う薬剤師にも
妊婦・授乳婦の来局が多い薬局では、婦人科や小児科の処方せんを扱う機会も多いはずです。
そうした場面では、「妊娠している可能性があるけれど、今飲んでいる薬は大丈夫なのか」といった不安を抱える患者さんからの相談が寄せられることもあります。
本書は、妊娠中や授乳期における精神疾患やその薬物治療についての基礎知識を整理できるため、妊婦・授乳婦と接する機会のある薬剤師にとっても、有用な1冊です。

たとえ日常的に精神科処方を扱っていなくても、「精神的な不調を訴える妊婦・授乳婦にどう寄り添えばいいか」を考えるうえで、本書から得られる視点は多いと感じました。
薬剤師として“伝える力”を磨きたい人
本書は、単に「妊娠中に使える薬・使えない薬」を学ぶための本ではありません。
どちらかといえば、「何を伝えるか」以上に、「どう伝えるか」に重きを置いた内容になっています。

妊娠を望む女性や、すでに妊娠中・授乳中の患者さんに対して、薬剤師がどのように寄り添い、どんな言葉で不安を和らげていくか。
その伝え方を考えるヒントが、症例を通じて学ぶことができます。
編者・執筆者紹介
本書は、妊娠と授乳期の薬物療法における専門家たちによって執筆・監修されています。
編者の伊藤真也先生は、トロント小児病院 名誉教授であり、WHOの薬剤評価担当アドバイザリーパネルメンバーも務めた小児科領域の世界的な専門家です。
村島温子先生は、妊娠と薬の研究を長年リードしてきた「一般社団法人 妊娠と薬情報研究会」の理事長を務め、妊婦・授乳婦への医療支援に精通した内科医です。
順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 院長の鈴木利人先生も監修に携わり、産婦人科領域の臨床現場を熟知した視点から本書の信頼性を高めています。
まとめ【薬剤師としての引き出しが1つ増える1冊】
妊娠適齢期の女性に向精神薬を交付する機会がある薬剤師にとって、本書は実務に直結する学びが得られる、非常に価値のある1冊です。
「自分には少し難しいかも…」と感じたとしても、読んでおくことで将来の選択肢や視点が確実に広がると感じました。
【本書で学べること】
• 妊娠にまつわる精神疾患の基礎知識
• 向精神薬の継続・中止の判断に影響する多角的な視点
• 妊婦・授乳婦との向き合い方(伝え方・支え方)
• プレコンセプションケアの実際(薬局でもできる妊娠前支援)
• 正解が1つでない問題への向き合い方
【本書をオススメできる人】
• メンタルクリニック門前の薬局で働く薬剤師
• 妊婦・授乳婦の処方せんに関わることが多い薬剤師
• プレコンセプションケアを業務に取り入れたい薬剤師
• 患者への“伝え方”をもっと磨きたいと考えている薬剤師

少しでも関心をもった方は、ぜひ実際にページを開いてみてください。
きっと、これまでになかった視点と出会えるはずです。
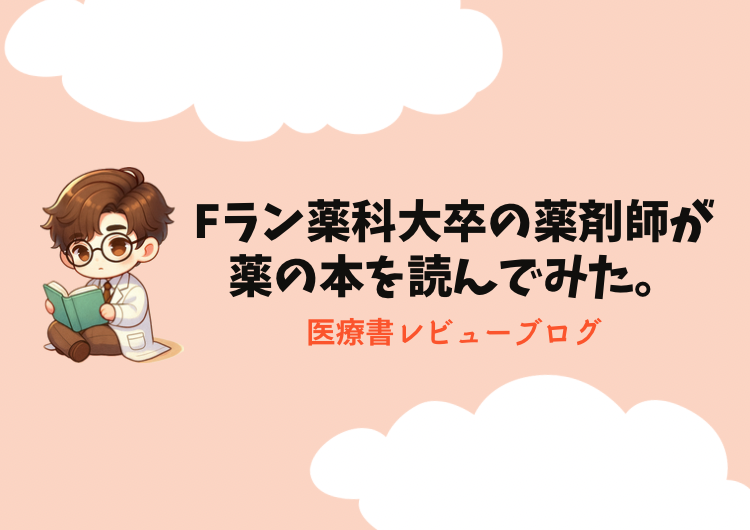
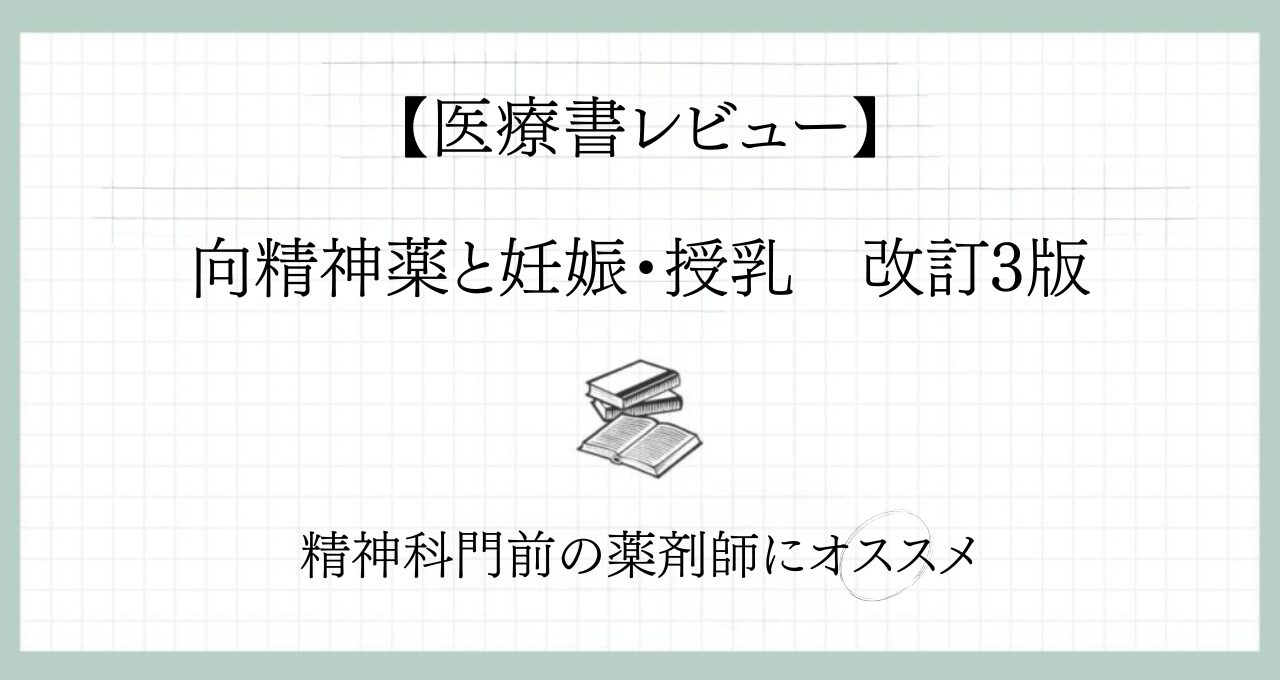



コメント