こんにちは!
Fラン薬科大卒で薬剤師やってます、のしんです。
このブログでは薬剤師や医療従事者向けに、医療本のレビューを書いていきます。
経歴と自己紹介
経歴って書くと大げさですが…

10数年前にFラン薬科大を卒業した、アラフォー薬剤師です。
実力はまだ足りていないと感じていますが、店舗に正社員の薬剤師が私しかいないため、消去法で管理薬剤師をしています。新卒で調剤薬局に3年、その後小規模の病院薬剤師を2年経験して、今は保険薬局で管理薬剤師をしています。
30歳過ぎるまでろくに本も読まなかった地頭悪男子です。
最近、焦りから自己啓発本に手を出してみたものの、難しくて途中で投げ出した本がたくさん…。
でも、勉強しないとまずい!と、手に取る本はたくさんあります。

意識高い系ですね。
そんな私が読みやすさを含めた医療本の感想を書いていこうと思います。

このブログに足を運んでくださった薬剤師の皆さんは私よりよっぽど頭がいいはずです。
私が理解できた本なら、きっと皆さんにも参考になるはず!
薬剤師としての悩み
日々、業務にあたる中で調剤、監査、投薬がルーチン化して、どうやって効率化しようかばかり考えている自分がいます。
薬学生の頃に抱いていた薬剤師像は、

「患者さんのために無くてはならない存在に」
とか

「医師や周りの薬剤師に一目置かれ、信頼される存在に」
とか。
だいぶ抽象的ですが、もっと人の役に立つような薬剤師になりたいという夢がありました。
でも管理薬剤師になると人件費の削減、残業の削減、加算、地域体制、GE率の向上、シフト作成など薬・患者さんとは関係ないことばかり求められます。

大事なことだとは思いますが、もっと薬剤師としての職能を発揮して患者さんのために働きたい!と思うことが多いです。
現場で感じる問題意識【勉強していない薬剤師多すぎない?】
実は、薬剤師として働いていて気になることがあります。

周りの薬剤師、勉強してなさすぎじゃないですか?
薬学部って偏差値の高い学部なので、みんな頭がいいんですよね。
特に4年制の薬学部にはFランなんてなかったと思います。
でも、現場に出てからの勉強量って、あんまり多くない気がしませんか?
それなのに、なんとなく「薬剤師だから、薬のことは詳しい」っていうプライドがあるような…。
正直、私も新人の頃は「薬剤師免許持ってるんだから」って、根拠のないプライドがありました。
でも、患者さんに質問されて答えられなかったり、病院薬剤師の頃に医師から抗生剤について質問されてもまったく分からず、上司にそのまま質問を投げていたり。そういう経験を重ねるうちに、もっと勉強しないとダメだなと思うようになりました。

若くして管理職になると部下が年上ばかりで大変なんですよね。
特に大変と感じるのが、あまり勉強をしていない、正直、薬剤師としての基礎知識が乏しいパート薬剤師さんへの指導の仕方です。
そして、勉強していない薬剤師ほど自分には経験があるからと、根拠のないプライドが高い傾向がある気がします。指導どころが提案もしづらい場面があります。
20-30代の若手管理薬剤師って結構多いと思うんです。
きっと私と同じような悩みを抱えている人も少なくないんじゃないかな。

経験は大切だけど、やっぱり基礎からの学び直しも必要だよなぁ…
って、日々悩んでます。
さらに困るのが、患者さんから「薬剤師に話すことなんてないよ。先生に全部伝えてるから」って言われること。確かに、薬剤師って自分の意見を持たずに「先生に聞いてください」って言いがちですよね。自分でものを考えないから信頼されないんじゃないかなって。
なぜ本で勉強するのか【能動的な学びが重要】
よく「医療従事者は生涯、勉強し続けないとならない」とか「医療の世界は日進月歩で、常に新しい薬が開発されるので、常に知識をアップデートしなくてはならない」って言われますよね。
「生涯勉強し続けないとならない」という言葉にはとても共感できます。
でも私、「常に新しい薬が開発されるので、常に知識をアップデートしなくてはならない」という言葉にはずっと違和感があるんです。
だって…

「必要な既存の医療の知識だけでも、無限にあるんですけど!」

「自分の薬局に置いてある薬だけでも、知らないことたくさんあるんですけど!」
と感じているからです。
患者さんや医師から信頼される薬剤師になるには、新薬の情報ももちろん大切です。
でも、それ以前に基本的な薬の知識、疾患の知識をしっかり身につけないと、結局は表面的な対応しかできないですよね。
勉強会やセミナーって「最新の糖尿病治療」とか「高血圧治療の未来」とか、先進的な内容が多くないですか?もちろんそれも大切なんですけど、私みたいに基礎から学び直したい人には、ちょっと難しすぎるんですよね。
それに対して、本での勉強には大きな魅力があります。
一番の利点は、自分に足りない知識を“能動的に”取りに行けることです。
私は、学生時代の勉強も社会人になってからの勉強も、”能動的な学び”こそが一番知識に定着すると感じています。
授業やセミナー、e-Learningは、基本的に”受け身の学び”です。もちろん、そこで得た内容を後から復習して実務に活かせば、能動的な学びに変えることはできます。
逆に、本も“ただ読むだけ”では知識として定着しません。
重要なのは、自分から疑問を持ち、答えを探し、理解しようとする姿勢です。
そのうえで、自分のレベルや関心に合わせてテーマを選び、自分のペースで深掘りできるという、本での学習は“能動的な学び”になりやすいと考えています。
このブログの目指すもの【勉強習慣のある薬剤師仲間を増やしたい!】
このブログを通じて、以下のような方々の学習をサポートできたらと思っています。
- オススメの参考書を探している方
- 医療書を購入する前に、その本でどんなことが学べるのか知りたい方
- 通勤時間などの隙間時間を有効活用して勉強したい方
- 新人さんなどで、そもそもどうやって勉強すればいいのか分からない方
- 家事、育児が忙しく、勉強する時間を確保しづらい主婦薬剤師、主婦医療者の方
- 産休・育休で現場から離れている方

「勉強はしたいけど、なかなかできない!」
という方に、少しでも役立つ情報を届けたいと考えています。

そして、このブログをきっかけに、一緒に学び続けられる薬剤師仲間が少しずつ増えていったら嬉しいです。
著作権に関する重要なお知らせ
本ブログの運営にあたり、著作権について以下の点を謹んでご説明申し上げます。
医療書の著者、出版社の皆様へ
本ブログでは、書籍の要約ではなく、一読者としての感想や学びを中心に記事を執筆させていただきます。著作物の価値を最大限尊重し、以下の方針で運営してまいります
- 書籍の内容を逐語的に引用することは極力避け、私個人の気づきや学びを中心に記載いたします
- 引用が必要な場合は、著作権法に基づき適切な範囲での引用に留めます
- 出典は必ず明記いたします
- 書籍の価値を損なうことのないよう、十分な配慮をいたします
なお、掲載記事につきまして、著作者・出版社様より修正や削除のご要望がございましたら、速やかに対応させていただきます。お気づきの点がございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
さいごに

最近、こんなことを考えています。
薬剤師の市場価値って、仕事が早いだけじゃダメなんじゃないかって。
添付文書見て、併用薬見て、禁忌がなくて常用量なら交付OK…それだけじゃなくて、もっと薬学的な観点で患者さんや処方内容を見られる薬剤師になりたい。「この患者さんにこの薬を渡して本当に大丈夫?」という癖をつけて、常に疑いを持って監査をする。
そのためにはやっぱり、勉強するしかないですよね!
このブログが、私と同じように「もっと成長したい」と思っている薬剤師の皆さんの、ほんの少しでも力になれたら嬉しいです。

一緒に学んでいきましょう!
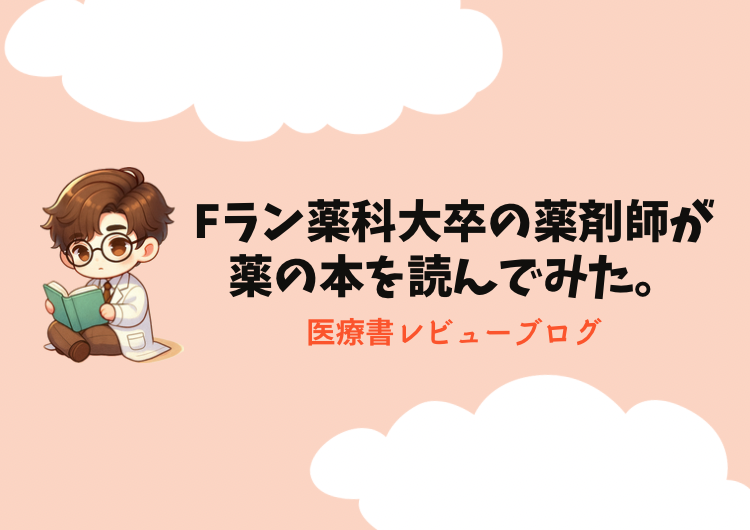


コメント