糖尿病の患者さんへの投薬時──

「HbA1cはどれくらいでしたか?」

「低血糖起こしてないですか?」
──以上!!
という薬剤師、多くないですか?
薬歴を見ても、横で同僚の投薬指導を聞いていても、そんな光景ばかり。
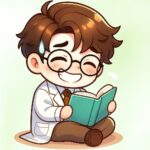
そして何より、自分がそれしか聞くことができない薬剤師だったということは内緒です。
今回紹介する『薬剤師力がぐんぐん伸びる 糖尿病フォローアップの勘所』を読めば、そんな投薬指導から必ず卒業できます。
糖尿病の基礎から薬剤の特徴、患者フォローアップの視点まで幅広く学べる内容で、しかも現場ですぐに活かせる工夫が豊富に盛り込まれています。
この記事では、
・本書はどのような本なのか
・私が本書で学んだこと
・実務での本書の活用方法
を紹介します。
読み終えたときには、あなたも「投薬時に何を聞けばいいかわからない」という悩みから一歩前に進めるはずです。
| 評価項目 | 評価 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 多くの薬剤師にオススメできます。糖尿病の基礎から実務での活用まで学べる内容で、新人から管理薬剤師まで役立ちます。「まず1冊持つならコレ」と言える本です。 | |
| 実務での活かしやすさ | 現場ですぐ確認できる表が多いです。本書に付箋を貼る、特定のページをあらかじめコピーしておけば、実務に直結します。 | |
| 自己学習への向き | とても学びが多いです。ただしアウトプットするパートがないので、自ら能動的に知識をとりにいかないと「読んで満足」で終わる恐れがあります。 | |
| 読みやすさ | とても読みやすい文章でした。200ページちょっとのボリュームで、読み切るには5〜6時間程度必要です。 | |
| コスパ | 税込4,950円。医療書としては標準〜やや高価の価格帯ですが、内容は充実しており、多くの薬剤師にとってコスパが良いと感じられる1冊です。 |
『薬剤師力がぐんぐん伸びる 糖尿病 フォローアップの勘所』はどのような本なのか
自己学習にも現場にも活用できる“二刀流”の1冊

本書の大きな魅力は、勉強と実務のどちらにも活かせる点です。
糖尿病の基礎知識や薬剤ごとの特徴を整理しながら学べるので、自己学習の教材として十分な内容を備えています。
同時に、目標値や薬剤フォローのポイントが表で整理されており、投薬時やトレーシングレポートなど現場でもすぐに参照できます。
「勉強のために読む本」と「実務で使う本」が1冊にまとまっているため、個人のスキルアップはもちろん、薬局全体で患者フォローの体制を整えるときにも頼りになる存在です。
糖尿病の基礎から実務まで学べる入門〜中級書
著者自身が薬剤師であるため、薬剤師の視点で必要な知識が整理されています。

糖尿病の基礎から薬剤ごとの特徴、患者フォローアップの実際までが一通り学べる内容で、入門〜中級レベルの学習書として位置づけられると感じました。
さらに、マンジャロやツイミーグなどの新しい作用機序の薬も網羅されており、知識のアップデートにも役立ちます。
そのため新人薬剤師やブランク明けの薬剤師にとって導入書として使いやすいだけでなく、経験を積んだ薬剤師にとっても学びのある1冊です。
糖尿病患者をどのようにフォローアップすべきかがわかる

Do処方の糖尿病薬を交付する際に「HbA1cはどうですか?」「低血糖は起こしていませんか?」と、ルーティンのように毎回同じ質問をしている薬剤師はいないでしょうか。私自身もまさにその一人でした。
本書では、それに加えて「どんな視点で患者を見ていけばよいか」「漫然と続く処方をどう捉えるか」といった、現場で迷いがちな部分に踏み込んで解説されています。
フォローアップの切り口が整理されることで、自信を持って患者に向き合えるようになるだけでなく、薬局全体での体制づくりにも応用できます。
実践的なヒントが得られる内容です。
目標数値や薬剤の特徴を整理した“使える表”が豊富
本書の大きな強みのひとつが、すぐに現場で活用できる“表”の充実です。
血糖コントロールの目標値や薬剤ごとの特徴、副作用やフォローアップのポイントが整理されており、投薬指導や薬歴記載にそのまま活かせます。
「この患者さんのHbA1c目標はどう考えるべきか」「この薬ではどんな副作用に注意するか」といった、日常業務で頻繁に直面する疑問に対応できる内容がまとまっています。

こうした表は、業務の効率を高めるだけでなく、患者さん一人ひとりに合わせた薬物治療の最適化にもつながります。
自己学習と実務の両面で活用できる、実用性の高い1冊です。
『薬剤師力がぐんぐん伸びる 糖尿病 フォローアップの勘所』で学んだこと

本書を読んでみて、これまで自分がいかに知識不足で糖尿病患者と向き合っていたかを痛感しました。
血糖目標値の考え方から薬剤選択の流れ、シックデイの対応、SGLT2阻害薬の特徴まで、多くの発見がありました。
血糖目標値を具体的に知らなかった

私はこれまでHbA1cを「体温」と同じ感覚で覚えていました。
36.0℃なら平熱で理想、37.0℃なら微熱で少し高め、38.0℃なら高熱で早く下げたい。
──そんなイメージで、HbA1c6.0%・7.0%・8.0%を並べて理解していました。
しかし本書を読んで、実際の血糖コントロールの目標はもっと具体的で、患者さんの年齢や状態によって変わることを知りました。
例えば65歳未満では合併症予防を意識した基準があり、65歳以上では認知機能や日常生活動作(ADL)なども考慮して、より緩やかな目標が設定されています。
さらに重要なのは、インスリンやスルホニル尿素薬(SU薬)を使っている患者さんには“下限値”も設けられていることです。
漫然と「低いほど良い」と考えるのではなく、低血糖を避けるためにどこまで下げないようにするかを意識する必要があると学びました。

これまで漠然と「HbA1c7%未満なら大丈夫」と捉えていた自分にとって、血糖目標値を年齢層や薬剤ごとに細かく調整する考え方は大きな学びでした。
医師の薬剤選択の考え方に触れるきっかけになった
これまで私は、医師がどのような基準で糖尿病薬を選んでいるのか、あまり意識したことがありませんでした。
本書を通じて初めて「アルゴリズム」という形で整理された医師の思考プロセスに触れることができました。
薬剤の選択は単に「血糖を下げる力」だけで決まるのではなく、
・まずインスリン治療が必要かどうかの判断
・肥満の有無やインスリン抵抗性の評価
・腎機能・心不全・肝機能など安全性の考慮
・CKDや心血管疾患など併存症への効果
・服薬継続率やコスト
こうした要素を段階的に積み重ねて決まっていくことを知りました。
「血糖を下げる力」だけではなく、患者の体格・生活背景・併存症などを踏まえて薬が選ばれているようです。
このアルゴリズムを知ることで、例えば「なぜこの患者さんにSGLT2阻害薬が選ばれているのか?」や「なぜ高齢の患者さんにはSU剤が控えられているのか?」といった背景を推測できるようになります。
単に「この薬はこの効果がある」ではなく、患者ごとの状況に合わせて薬が組み合わされていることを学びました。
本書を通して「どの薬が効くか」だけではなく、「どんな理由でこの薬が処方されたのか」という医師の思考プロセスに触れることができ、処方の意図を理解する視点を少し持てるようになったと思います。
シックデイで注意すべきことをしっかり理解できた
「シックデイ」とは、糖尿病の患者さんが発熱や下痢、食欲不振などで普段どおり食事や水分がとれず、血糖コントロールが乱れやすくなる状態を指します。
体調不良のときは通常とは異なる対応が必要となり、薬の使い方や生活上の注意点を患者さんに伝えることが欠かせません。

私はこれまで「シックデイ=食事が摂れないときに血糖降下薬を飲むと低血糖になる」という程度の認識しかありませんでした。
実際にはそれだけでは不十分で、病気や体調不良によってインスリンの分泌や作用が乱れ、高血糖に傾くこともあると知ったのは大きな気づきでした。
体調が悪くなると、発熱や感染症によるストレスで体内のホルモンが増え、インスリンの働きが弱まります。
その結果、血糖が下がりにくくなり、さらに脱水が加わると血糖値は一気に上昇。
最悪の場合はケトアシドーシスや高浸透圧高血糖症候群といった緊急事態に進展する危険もあります。
こうした仕組みを理解できたことで、投薬時に「体調を崩したときの薬の使い方」について、こちらから具体的に説明できるようになりました。

以前の私は「低血糖に注意してください」くらいしか伝えられませんでしたが、今では高血糖のリスクも含めて伝えられるようになり、患者さんにとってより実践的なサポートができると感じています。
SGLT2阻害薬による尿量増加は一時的なものと初めて知った

SGLT2阻害薬を使うと尿量が増えることは知っていましたが、私はそれがずっと続くものだと思い込んでいました。
ところが本書を読んで、尿量増加は投与初期の一時的な現象であることを初めて知りました。
薬の作用でブドウ糖とナトリウムが尿中に排泄されると、浸透圧の影響で水も一緒に流れ出るため、初期には尿量が増えます。
しかし、体は恒常性を保つために、遠位尿細管や集合管でナトリウムと水を再吸収するようになります。
その結果、尿量は徐々に通常のレベルに戻っていくとのことです。
一方でブドウ糖の排泄は続いているため、血糖コントロールや体重減少、心腎保護といった薬効は、服用している限り維持されます。

この仕組みを理解したことで、患者さんに「飲み始めはトイレが近くなるかもしれませんが、徐々に落ち着いてきますよ」と説明できるようになりました。
私は本書を現場でこのように活用しています

本書は自己学習で学ぶだけではなく、現場ですぐに活用できる内容も含まれています。
ここでは私自身が実際の業務でどのように本書を取り入れたのか、具体的な活用例を紹介します。
シックデイカードをお薬手帳に貼り、患者さんへの注意喚起に活用
本書で初めて「シックデイカード」の存在を知りました。
このカードを活用することで、患者さんにシックデイ時の対応を具体的に伝えやすくなります。
私は、カードをお薬手帳に貼り付けたうえで、

「体調を崩したときにどのように対応すれば良いのか、あらかじめ主治医に確認しておきましょう」
と説明しています。
また、患者さんへの説明だけでなく、トレーシングレポートを通じて主治医にもカードの存在を共有しています。
これは「次回受診時に患者さんが聞き忘れることを防ぐ」だけでなく、「主治医が突然質問されて場当たり的に答えるのではなく、普段の服用状況など患者の情報をあらかじめ主治医に伝えて、その上で対応を検討していただくようにする」という目的があります。
結果として、患者さん・医師・薬剤師の三者でより安心できる連携につながるのではと考えています。

このカードは日本くすりと糖尿病学会のホームページから誰でも無料でダウンロード可能です。
薬局で準備しておけば、必要なときにすぐ配布できる便利なツールです。
👇一般社団法人 日本薬と糖尿病学会のリンクはこちら
一般社団法人 日本くすりと糖尿病学会https://jpds.or.jp
自動車運転者への低血糖指導をより具体的にできるようになった

自動車運転と低血糖は、患者さん自身だけでなく他者を巻き込む交通事故に直結しかねない重要な因子です。
本書では「運転者にどのように質問し、どのように指導するのか」が具体的に示されており、実務での指導に直結する内容だと感じました。
私は本書の内容を参考に、患者さんへ低血糖指導を行うと同時に、自分自身が「どのように質問・説明を積み重ねるか」を意識するようになりました。
血糖降下薬が新規で処方された際の指導では、まず、低血糖について説明します。
運転とは関係なく、低血糖リスク自体をしっかりと説明します。
その上で自動車運転の有無をだけを確認します。そして、薬歴にその内容を記載しておきます。
2回目以降の投薬時には、さらに踏み込んで 「運転はどのくらいの頻度か」など、生活に即した具体的な質問を重ねて、運転者に交通事故を起こさせないように指導を繰り返していきます。
このように、1回で全てを伝えきるのではなく、薬歴を活用して質問と説明を段階的に重ねていくことで、患者さんにとっても理解しやすく、薬剤師としてもより実効性のある指導につながると感じています。
薬歴に「eGFR〇〇以下で疑義照会!」と記載し、全薬剤師で共有
血糖降下薬で腎機能に配慮すべき薬剤は少なくありません。

本書を読んで「腎機能を意識して投薬することの重要性」を改めて学びましたが、それを自分ひとりの知識で終わらせてはいけないと感じました。
そこで実践しているのが、本書にも記されている、薬歴に「〇〇を飲んでいるので、eGFR〇〇以下で疑義照会!」と具体的に記載することです。
こうすることで、誰がその患者さんに投薬しても同じ視点で対応でき、漫然と処方を続けてしまうリスクを防ぐことができます。

つまり、本書を読んだ薬剤師だけがフォローできる状態ではなく、薬局全体で腎機能に配慮した体制を構築することが大切だと実感しました。
SU剤服用患者を洗い出し、目標HbA1cを薬歴に共有
ひとつ前の見出しで紹介したとおり、本書では「腎機能のフォローについて薬歴に記載し、薬剤師全員で共有すること」の大切さが示されていました。

その考え方にヒントを得て、私は目標HbA1cについても共有した方が良いのではないかと考えるようになりました。
そこで実際に、薬歴からSU剤を服用している患者さんを洗い出し、それぞれの目標HbA1cを申し送りに記載する取り組みを始めました。
こうしておけば、誰が投薬しても「この患者さんはどれくらいの血糖コントロールを目指しているのか」を把握でき、過度な投薬や不適切な継続を避けやすくなります。

本書の学びをきっかけに、自分なりに応用して薬局全体で情報を共有する仕組みに発展させられたことは、大きな成果だったと感じています。
各薬剤フォローアップ表を印刷し、監査台に常備して即参照できるようにした
本書では、薬剤ごとの特徴やフォローアップのポイントが整理されており、表にもまとめられています。

私はこれを読んで「実際の監査の場でこそ役立つ」と感じ、必要なページを印刷してラミネートし、監査台に常備するようにしました。
監査中に「この薬を使っている患者さんには何を確認すべきか」と迷ったとき、すぐに参照できるのは大きな安心感につながります。
特に糖尿病薬は種類が多く、それぞれに確認すべき副作用やモニタリング項目が異なるため、表を見ながら投薬できるのは非常に効率的です。
この取り組みを薬局内で共有することで、誰が監査しても同じ視点で患者さんをフォローできるようになりました。
個人の知識を仕組み化して全員で使える形にすることが、患者さんへの安全で一貫した対応につながると実感しています。
『薬剤師力がぐんぐん伸びる 糖尿病 フォローアップの勘所』の感想【良かった点と気になった点】

本書を通じて「糖尿病患者をどうフォローすればいいのか」という疑問に、数多くのヒントを得ることができました。
自己学習から薬局全体での活用まで幅広く役立つ一方で、いくつか改善してほしいと感じた点もあります。
ここでは、実際に読んでみて強く印象に残った良い点と気になった点を紹介します。
自己学習からチーム共有まで活用でき、幅広い薬剤師にオススメできる1冊
本書の魅力は、個人の自己学習から薬局全体での情報共有まで幅広く使える点にあります。
糖尿病の基礎知識を整理したい新人薬剤師にも、日々の投薬で患者フォローを強化したい管理薬剤師にも、それぞれに得られるものがある内容です。
前述のとおり、私は本書で学んだことを薬歴の申し送りやシックデイカードの配布といった形に落とし込み、薬局全体で共有するようにしました。
こうすることで、「本を読んだ人だけが実践できる」ではなく「誰が患者に対応しても一定の質を保てる」という仕組みをつくることができます。

このように、自己学習を通じて個人のスキルアップに直結するだけでなく、学びを仕組み化してチームで活かせるのは、本書ならではの大きな強みだと感じました。
総論→各論→症例の流れで“理解が深まる”構成
本書は、総論(糖尿病の基礎知識)→各論(各薬剤の特徴やフォローアップの仕方)→症例(総論と各論の復習)という流れで構成されています。
最初に糖尿病治療の全体像を整理し、次に各薬剤の特徴やフォローアップのポイントを学び、最後に症例を通して知識を実践に結びつけるという流れです。
この構成のおかげで、「知識として理解したこと」が症例に当てはめられるため、学んだ内容が復習できると感じました。
ただ同時に、1周読んで内容を暗記することは多くの方で不可能だと思いました。
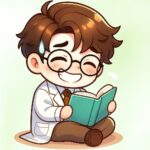
ちょっと前に読んだ内容が記憶から抜けているということを、症例パートを読んでいるときに実感しました。
学んだ知識を定着させるには、本書を実務に取り入れ、繰り返し学んでいく必要があります。
(気になった点)アウトプットの場がなく、読んで満足してしまう可能性がある

本書で感じたのは、アウトプットの機会が用意されていないということです。
症例を読むことで知識を復習できる構成にはなっていますが、読者自身が手を動かして考える「練習問題」や「確認テスト」はありません。
とてもわかりやすい文章でまとめられているため、スムーズに読み進められます。
ですが、そのわかりやすさゆえに「理解したつもり」で満足してしまう可能性もあるのではと感じました。
何度も読み返し、実務に活かし続けることで、本書の内容を自分のものにしていくことが大切だと思います。

読者側でアウトプットの工夫が必要です。
ずっとDo処方の患者をどうフォローすれば良いかがわかる
糖尿病患者の中には、何年も同じ薬が処方され続けている、いわゆる「Do処方」の方が少なくありません。

こうした患者さんに対して「薬剤師として何を確認すればいいのか」「どのように声をかければいいのか」と迷う場面は多いのではないでしょうか。
本書では、そうした日常的な疑問にヒントを与えてくれます。
たとえば、血糖コントロールが維持できているか、副作用リスクが高まっていないか、生活習慣や合併症のフォローは十分か──といった視点を持つことで、患者さんを継続的に支える薬剤師の役割を果たせるようになります。

私は本書を読み、「ただ処方を確認して渡す」のではなく、「漫然とした継続の中にどんなリスクや改善点が潜んでいるのか」を意識するようになりました。
これは薬剤師誰もが日常で直面する場面に直結する内容であり、非常に実務的な学びだと感じます。
(気になった点)インスリン手技の説明が文章のみでイメージしにくい
本書ではインスリンの手技についても触れられていますが、説明が文章のみで写真や図がありません。
そのため、実際にデバイスを操作した経験が少ない薬剤師にとっては、イメージをつかみにくい部分だと感じました。

私自身、薬局でインスリンを使っている患者さんはごくわずかで、日常業務でデバイスに触れる機会はほとんどありません。
そのため、本書を読むだけで「針の装着方法」「注射の操作手順」などを正しく理解するのは難しいと感じました。
今後は、本書を参考にしつつ、メーカーに依頼して練習用キットを取り寄せ、実際に手を動かして学ぶ必要があると思います。

とはいえ、文章のみの説明であっても、注意点など必要なことはしっかりと記載されています。
だからこそ、実際のデバイスを用意して、本書を片手に学んでいきたいと思います。
『薬剤師力がぐんぐん伸びる 糖尿病 フォローアップの勘所』をオススメできる人

本書は糖尿病に関わる薬剤師なら誰が読んでも学びはありますが、その中でも「これは特に読んでほしい!」と思える層があります。
ここでは、本書を強くオススメしたい薬剤師を紹介します。
新人薬剤師・ブランク明けで復職する薬剤師

糖尿病治療の基礎から実務までを体系的に学べる本書は、まず新人薬剤師に強くオススメできます。
国家試験の勉強だけの知識では投薬指導や処方意図の理解につながりにくい部分を、本書が現場目線で埋めてくれます。

また、産休・育休などで現場を離れた後に復職する薬剤師にもピッタリです。
最近発売された新しい薬の情報やフォローアップのポイントが整理されているため、ブランクを感じることなく投薬に臨めるようになります。
特に「血糖目標値の考え方」や「薬剤選択の流れ」などは、自己学習だけではイメージしづらい部分。
こうした知識をまとめてキャッチアップできる点は、復職直後の不安を和らげる助けになるはずです。
糖尿病患者のフォローアップに苦手意識がある薬剤師
糖尿病の患者さんに投薬するとき、「何を聞けばいいのかわからない」と感じたことはないでしょうか。

私自身も以前は「HbA1cはどうですか?」「低血糖は起きていませんか?」といった定型的な質問しかできず、それ以上の指導につなげられませんでした。
本書には、漫然と処方が続いている患者さんをどのようにフォローすればよいのか、具体的に整理されています。
血糖コントロールの状態、副作用リスク、合併症や生活習慣など、確認すべきポイントが明確になるため、指導に自信を持って臨めます。

フォローアップに苦手意識を持っている薬剤師ほど、本書を読むことで「何を聞けばよいのか」「どこに注意を向ければよいのか」が整理され、投薬時の引き出しが増えるはずです。
薬局全体で糖尿病患者への対応力を高めたい管理薬剤師
管理薬剤師として働いていると、「薬局全体で患者対応の質をどう底上げするか」という課題に直面します。
本書は、その具体的なヒントを与えてくれる1冊だと感じました。
目標値の一覧表や薬剤フォローアップの表は、そのまま薬局内で共有できるツールです。

私は実際に、これらを印刷して監査台に常備したり、薬歴の申し送りに活用したりすることで、誰が投薬しても同じ視点で糖尿病患者をフォローできる仕組みづくりに役立てました。
また、シックデイカードを導入すれば、患者説明だけでなくトレーシングレポートの件数を増やすことも可能です。トレーシングレポートが増えることで、薬局全体の医師との連携強化にもつながります。
つまり本書は、個人の学びにとどまらず、薬局単位での対応力強化につなげられる本です。

糖尿病患者のフォロー体制を整えたい管理薬剤師にとって、非常にオススメできます。
著者紹介
本書の著者・阿部真也先生は、2007年に北里大学薬学部を卒業後、同大学院を修了し、北里研究所病院で内科・外科病棟を担当されました。
その後、在宅医療に力を入れる薬局に勤務し、地域に根ざした医療に携わっています。
現在も薬局で勤務される傍ら、帝京大学薬学部で教育活動にも従事。
日本糖尿病療養指導士や糖尿病薬物療法認定薬剤師などの資格を持ち、糖尿病を中心に実践的な薬学教育・地域薬学ケアに取り組まれています。
まとめ【自己学習と現場対応の二刀流】
本書『薬剤師力がぐんぐん伸びる 糖尿病 フォローアップの勘所』は、自己学習から実務まで幅広く活用できる1冊です。
ここでは、本記事の内容を簡単に振り返ります。
【本書の特徴】
・糖尿病の基礎から実務まで体系的に学べる
・患者フォローアップの視点が豊富に盛り込まれている
・目標値や薬剤の特徴を整理した“使える表”が多数掲載
【私が本書で学んだこと】
・HbA1c目標値の具体的な基準と下限の存在
・医師が薬剤を選択する際の考え方のアルゴリズム
・シックデイでの注意点と対応の重要性
・SGLT2阻害薬による尿量増加は一時的であること
【本書の現場での活かし方】
・シックデイカードを活用して患者と主治医の連携を強化
・自動車運転者に対する低血糖指導を具体的に実施
・薬歴に「eGFR〇〇以下で疑義照会」と記載して全員で共有
・SU剤服用患者の目標HbA1cを薬歴に残して情報共有
・フォローアップ表をラミネートして監査台に常備
【本書をオススメできる人】
・新人薬剤師やブランク明けで復職する薬剤師
・糖尿病患者のフォローアップが苦手な薬剤師
・薬局全体で糖尿病患者対応を強化したい管理薬剤師

私自身、まだ糖尿病患者さんのフォローアップに完璧な自信があるわけではありません。
それでも、本書を繰り返し読み返しながら、少しずつ実務に活かしていこうと思っています。

もしあなたが投薬時に迷いを感じているなら、この本はきっと背中を押してくれるはずです。
本書を一緒に活用していきましょう。
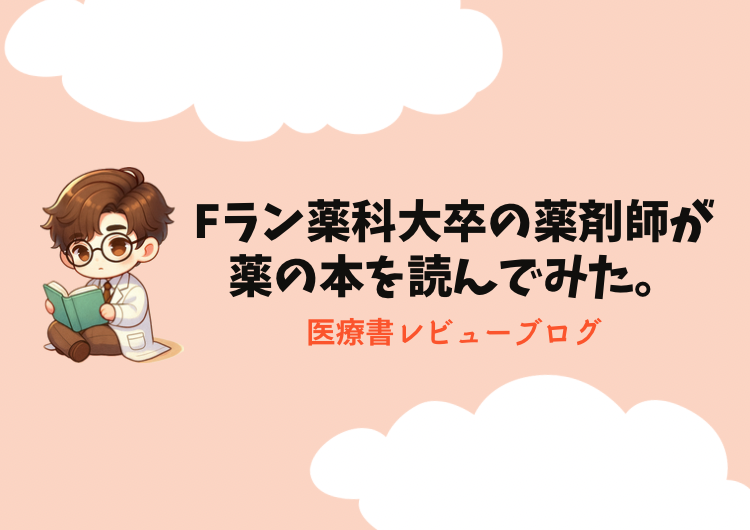
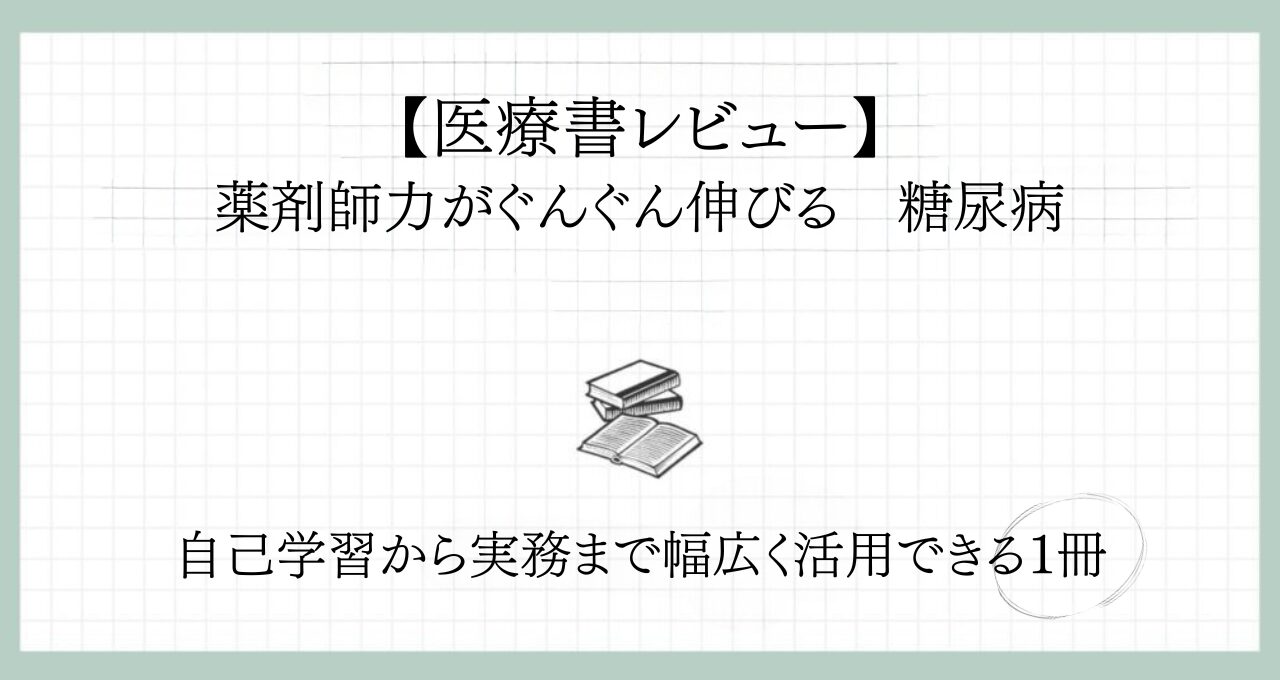
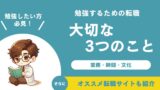


コメント