
薬を見れば心不全の薬だということはわかるけど、それ以上のことは…

循環器の薬をどうやって勉強すればいいのかわからなくて…
薬剤師として働く中で、同僚の薬剤師からこんな声をよく耳にします。
循環器の薬は種類も多く、患者ごとに対応が異なるうえ、処方せんから読み取れる情報に限りがあり、薬剤師にとって判断が難しい領域。
しかも高齢化が進む日本では、心不全の患者は今後も増え続けるとされており、循環器は薬剤師にとって“避けては通れない分野”になっています。
とはいえ、循環器に関する本は専門性が高く、「どれから読めばいいの?」と感じている方も多いはず。
決して安くない医療書だからこそ、「せっかく買ったのに合わなかった…」という失敗も避けたいところ。

そんな方に向けた【医療書比較シリーズ】です。
薬局・病院で実務経験のある、Fラン薬剤師のしんが循環器の薬を学ぶための本4冊を比較・レビューしました。
難易度や学び方が異なる4冊を、目的別・読者別に解説します。
この記事を読めば、「自分に合った循環器の本」がきっと見つかります。
まずは1冊、あなたにとっての“入口”になる本を選んでみませんか?
【薬剤師向け】レビュー本紹介

まずは、循環器領域に関する医療書4冊の特徴や活かし方を紹介します。
『薬剤師力がぐんぐん伸びる 専門医がじっくり教える 心不全・心房細動』
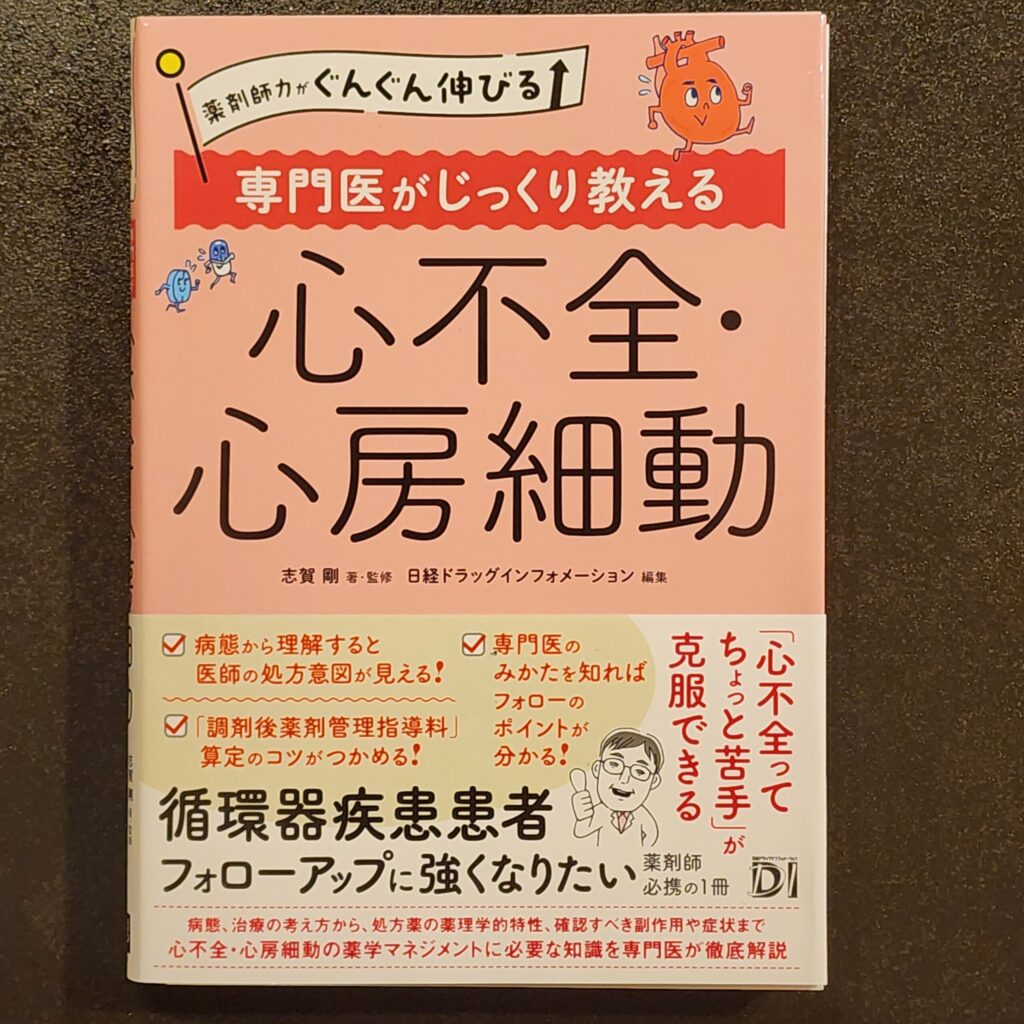
心不全・心房細動に強くなりたい薬剤師へ向けた、自己学習に最適な1冊です。
専門医による丁寧な解説で、循環器に苦手意識がある薬剤師でも安心して読み進められる構成。
心不全と心房細動の“基礎〜応用”までをカバーし、トレーシングレポートやフォローアップに活かせる視点が得られます。
→詳しく知りたい方は、下記のレビュー記事をご覧ください。
| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価・オススメ度 | 循環器の自己学習用にピッタリ。初心者にもオススメできる1冊。 | |
| 実務での活かしやすさ | 現場で本書を開いて使うイメージは湧かない。 | |
| 自己学習への向き | 循環器の知識がなくても読める。実務に活きる知識が得られる。 | |
| 読みやすさ | 文章が丁寧で、内容もわかりやすい。 | |
| コスパ | 税込4,950円。医療書としては標準的で、内容にも見合っている。 |
循環器関連の病態・薬を自己学習で学ぶための本

本書は循環器に苦手意識のある薬剤師に向けて、心不全の基礎から薬物治療の考え方までを段階的に学べる構成になっています。
心不全の病態、治療の総論、薬剤の各論と順序立てて進んでいくため、知識の整理と定着がしやすく、自己学習に最適です。
心不全の患者さんや処方薬を、薬剤師がどう見ればいいのかがわかる
本書を読むことで、「なぜこの薬が使われているのか」「患者さんの状態はどこに注意してみるべきなのか」といった視点が持てるようになります。
たとえば、利尿薬では、食事量や水分摂取量、体重の増減、労作時の息切れ、浮腫の有無や程度など、患者さんの背景のどこに注目すべきかが具体的に解説されています。

ただ処方を見るのではなく、「処方を通して患者の状態を見ていく力」を身につけることができます。
読みやすさと内容のバランスがちょうどいい
文章は読みやすく、内容もわかりやすく、スラスラと読み進められました。
ページ数は200ページちょっとでちょうどよいボリューム感です。
毎日30分〜1時間のペースでも、1週間ほどで読み切れる内容でした。

時間をかけすぎずに読める一方で、実務に活かせる視点や知識はしっかり身につきます。
(気になった点)現場で本書を開くイメージは湧かなかった(自己学習専用の本)
本書は調剤室に常備して辞書的に使うようなタイプの本ではありません。
自宅でじっくりと読み進める、自己学習向けの1冊です。
実際の現場対応中に本書を開いて使うというイメージは湧きませんでした。

現場対応中に本書を開くことはないため、事前に要点を自分の中で落とし込んでおく姿勢が大切です。
『循環器疾患にかかわる薬剤師の思考・視点がわかる 循薬ドリル』
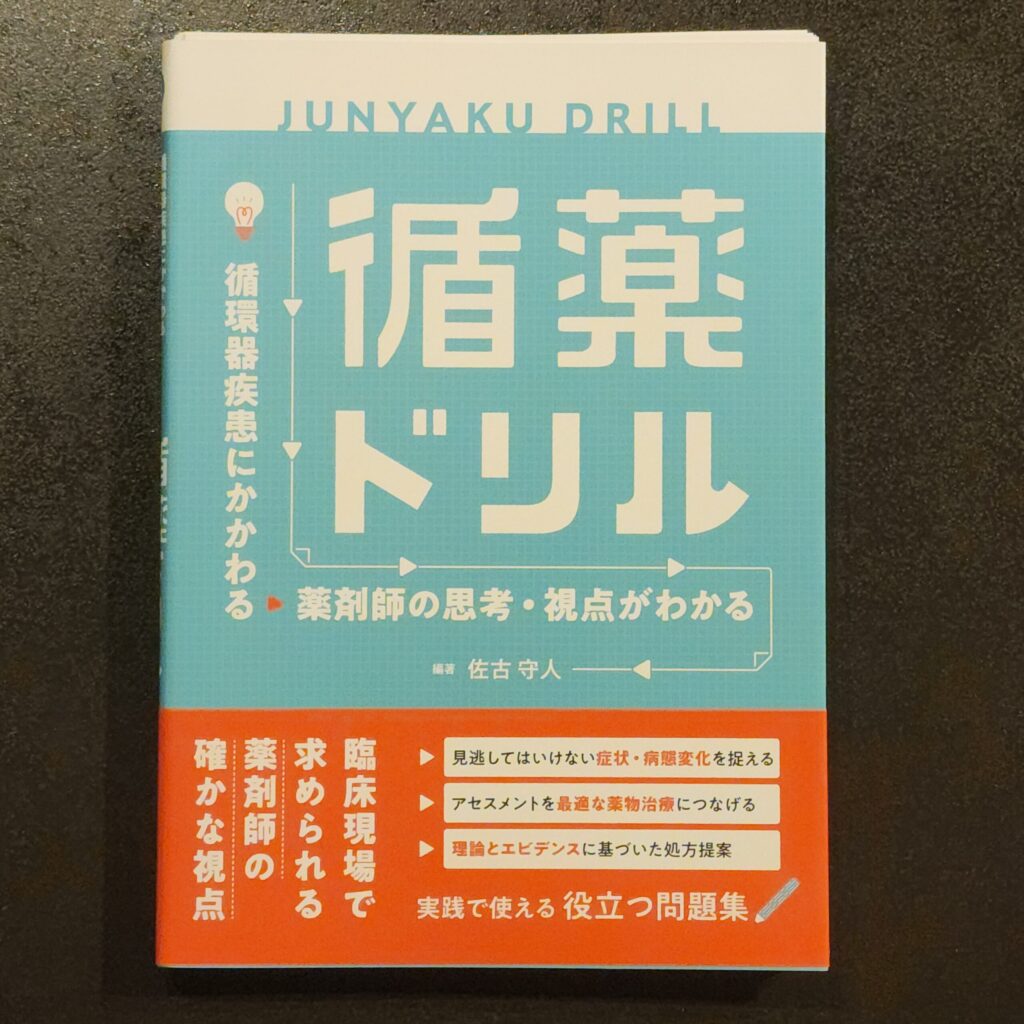
“心不全の基本のキ”からスタートし、最終的には医師と同じ目線でディスカッションできるレベルまで引き上げてくれる、まさに“本気の1冊”。
カルテが見られない薬局薬剤師でも、「この人はどんなタイプの心不全か?」と自分の頭で考え、そこから必要な薬物治療を逆算できる思考力が身につきます。

読み切るには気合いと集中力が必要ですが、それに見合うだけの確かな学びがあります。
→詳しく知りたい方は、下記のレビュー記事をご覧ください。
| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価・オススメ度 | すべての薬剤師に読んでほしいが、難易度が高く挫折のリスクも。評価は控えめ。 | |
| 実務での活かしやすさ | 現場で直接使う本ではないが、知識があれば医療の質は確実に上がる。 | |
| 自己学習への向き | 自己学習専用。集中して読み切る価値のある1冊。 | |
| 読みやすさ | 難しい内容だが、文章自体は丁寧でわかりやすい。 | |
| コスパ | 税込4,180円。読み切れれば十分すぎるリターンが得られる。 |
薬剤師視点で循環器疾患にどのようにアプローチするのかを学べる本

心不全、不整脈、冠動脈疾患などの循環器疾患をはじめ、それに関連する薬物治療について、薬剤師に必要な知識が症例ベースで体系的に整理されています。
どの章も「薬剤師として、何を考え、どう行動するか」が軸になっており、単なる解説にとどまらず、症例をもとにした実践的な思考のプロセスを学べる構成です。
エビデンスに基づいた情報はもちろん、現場でそのまま活かせる視点が詰まった1冊です。
ドリルという名にふさわしい、紙とペン必須の“本気の問題集”
本書は各章の冒頭にケーススタディ(症例)と問いが提示され、それに対する思考プロセスが本文で解説されます。さらに章末には確認問題が用意されており、まさに「読むドリル」という構成です。
問題を解くため、自分の理解を定着させるためには、ノートとペンが必須。
電車の中でパラパラ読むような本ではなく、机の上で集中して取り組む必要があります。

まさに“本気で向き合う人”のための1冊です。
内容は高難易度だが、文章・構成は読みやすい

内容は高度ですが、専門書にありがちな堅さや読みにくさはありません。
文章や構成は整っており、説明の流れも自然で読みやすさがあります。
専門用語は多めですが、「難しいことを難しく書いている」のではなく、「難しいことを丁寧に書いている」という印象。
調べながら、自分の理解を整理しながら読み込めば、必ず自分の力になる内容です。
(気になった点)調剤薬局では想像しにくい症例も多く、病院薬剤師向けと感じた

本書に登場する症例の多くは、救急搬送された患者さんや入院中の心不全患者さんなど、病棟でしか出会えないような症例です。
内容としては非常に勉強になるのですが、調剤薬局で日常的に出会う患者さんと比べると、どうしても現実味を持ってイメージするのが難しいと感じました。
特に、検査値や画像所見をもとにした評価、点滴や急性期の処方設計などは、カルテを見れない薬局薬剤師にとっては、やや距離を感じる部分かもしれません。
『薬剤師のための ここからはじめる循環器』
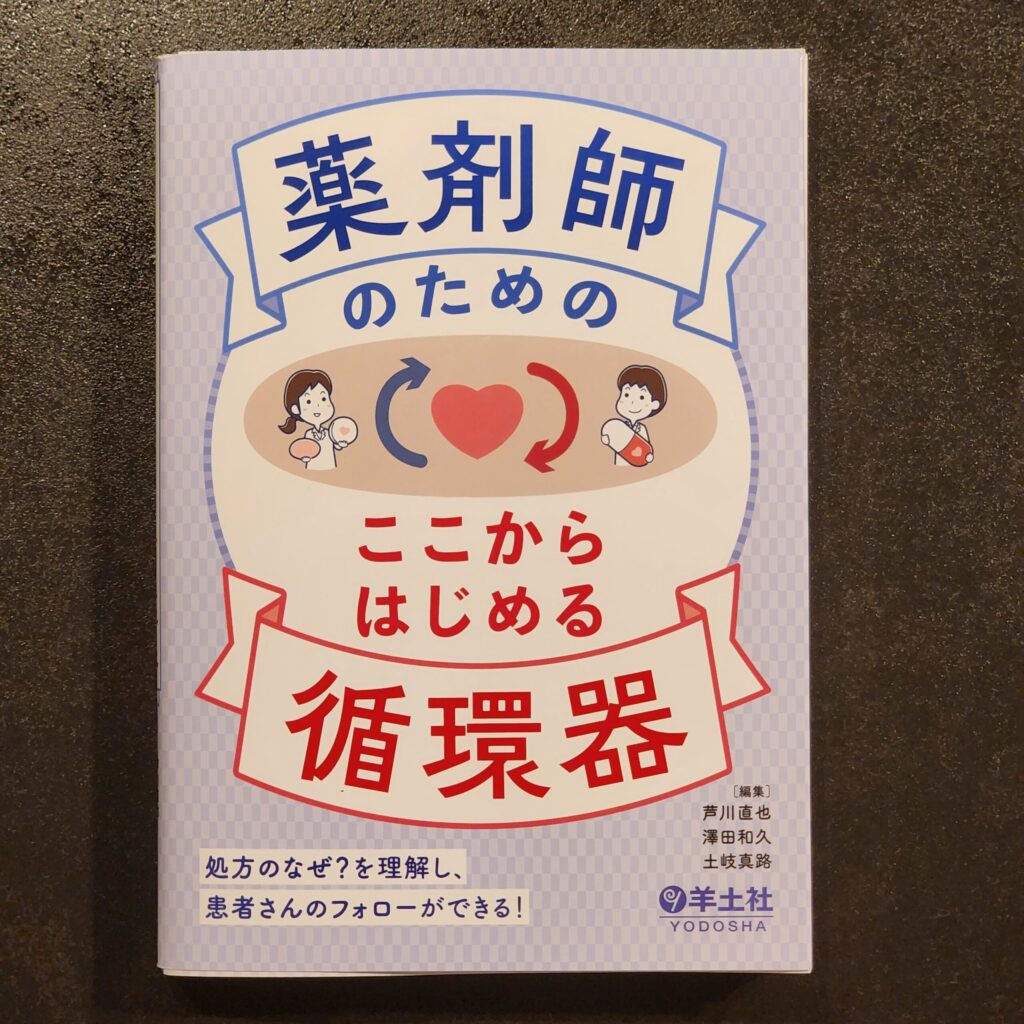
循環器に苦手意識がある薬剤師や、ブランク明けで学び直したい方にピッタリです。
やさしい言葉づかいと丁寧な構成で、心不全・不整脈・高血圧といった基本的な疾患を“薬剤師の視点”で学べます。
これから循環器と関わるすべての薬剤師に、最初の1冊目としてオススメです。
→詳しく知りたい方は、下記のレビュー記事をご覧ください。
| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価・オススメ度 | 私自身とても学びが多く、「読んでよかった!」と素直に思える1冊でした。 | |
| 実務での活かしやすさ | 基本は自己学習向けですが、表やガイドラインの要点整理など、現場でも役立つ場面はあります。 | |
| 自己学習への向き | 読みやすい一方、“ただ読んだだけ”にならないよう能動的な姿勢が求められます。 | |
| 読みやすさ | 専門用語にもきちんと解説がついており、循環器が苦手な方でも安心して読み進められます。 | |
| コスパ | 税込4,180円。医療書としては標準的な価格ながら、内容は充実。コスパ高いです! |
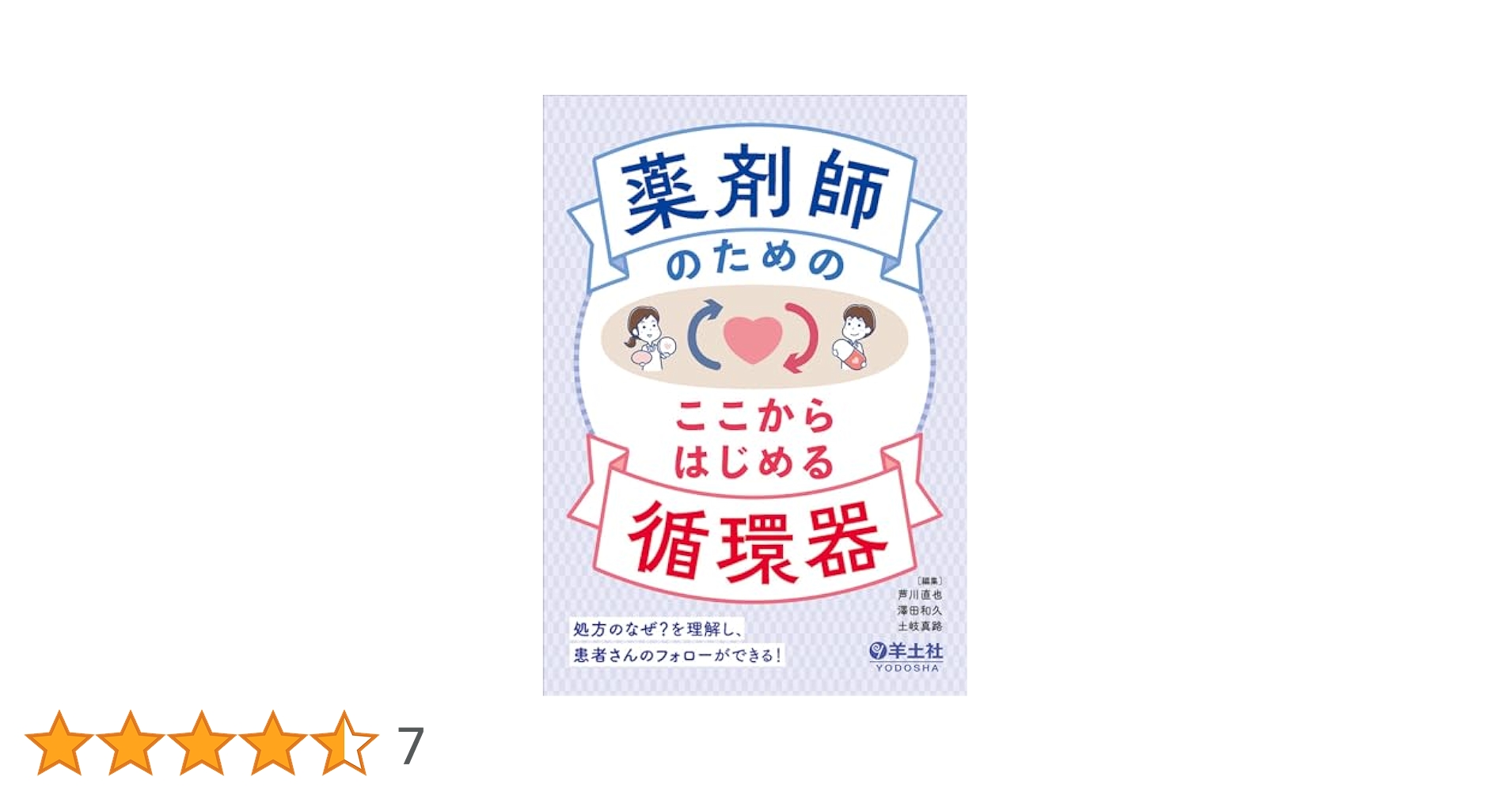
薬剤師の、薬剤師による、薬剤師のための循環器学習本

編者・著者も薬剤師であるため、薬剤師に必要な知識が厳選されており、安心して読み進められます。
「医師の視点」ではなく、「薬剤師としてどう考えるか」に重きを置いた構成で、現場に立つ薬剤師にとって実践的な学びが得られる1冊です。
【難易度は易しめ】対象は循環器が苦手な薬剤師・これから関わる薬剤師
専門用語には補足説明がついており、初学者でも読みやすい構成です。
疾患ごとの章立てで、心不全・高血圧・不整脈などを無理なく学べます。

循環器に苦手意識がある方や、ブランク明けで学び直したい薬剤師にこそ読んでほしい“導入書”です。
ガイドラインや表を活用し、現場で“調べる本”としても活躍
本書は「読み物」としてだけでなく、「調べる本」としても優秀です。
薬剤選択のフローチャートや疾患別の確認ポイントなどが、表や図で視覚的に整理されており、現場での判断にも役立ちます。
電子書籍で持ち歩けば、調剤室や在宅訪問先でもサッと確認できます。
病院薬剤師と薬局薬剤師をつなぐ“橋渡し”の視点が得られる本

病棟と薬局、それぞれの立場にいる薬剤師がどう連携すべきか、という視点が特徴的です。
服薬情報提供書やトレーシングレポートを書く際のヒントが得られるなど、実務にも直結する内容です。
「病院ではこうする」「薬局ではこう考える」といった視点の違いを自然に理解できる構成になっています。
(気になった点)読みやすい分、「読んだつもり」にもなりやすい
文章がやさしく、サクサク読めてしまうぶん、「なんとなく理解したつもり」になってしまうリスクもあります。
読み終えた後に自分の中で知識を整理し直したり、実務での活用方法をイメージするなど、一歩踏み込んだ学習姿勢が求められると感じました。

インプットした知識をアウトプットにつなげる意識が大切です。
『循環器薬ドリル 薬剤選択と投与後のフォローも身につく症例問題集』
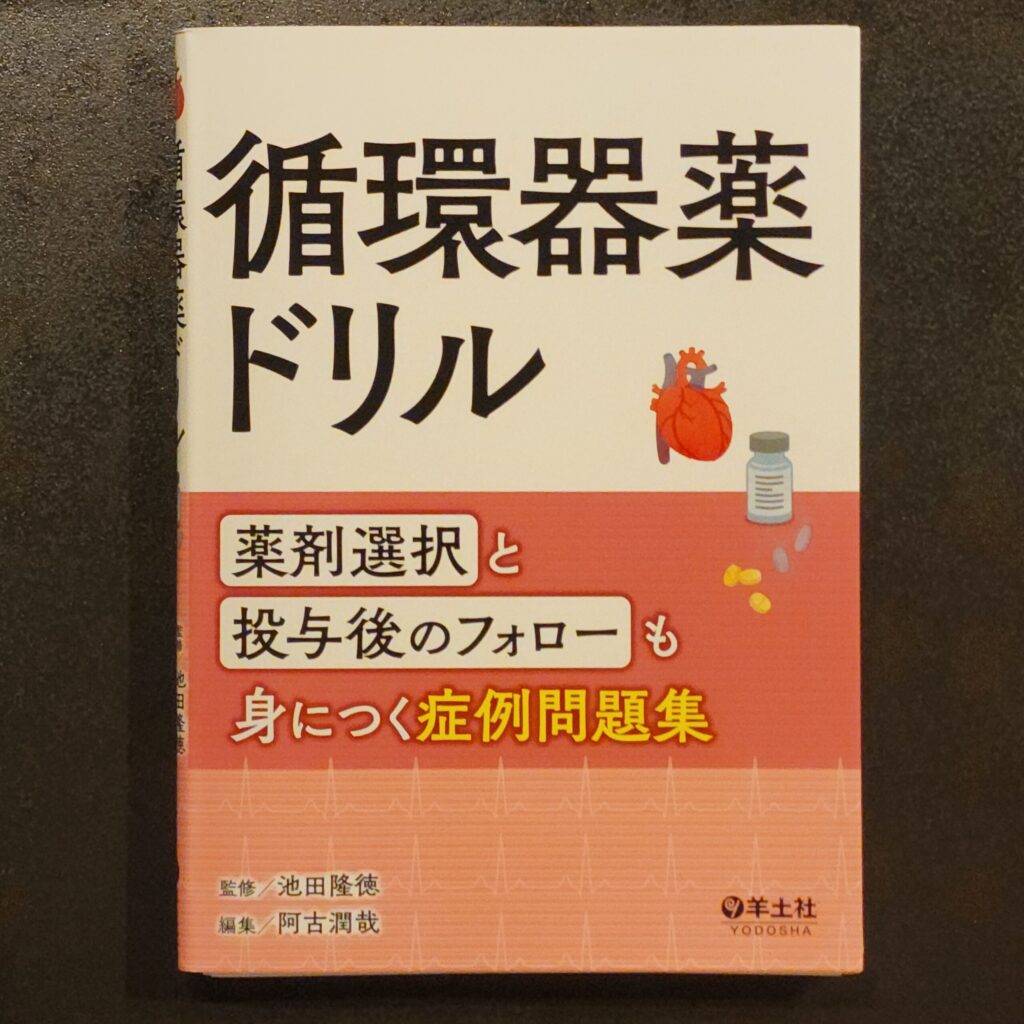
循環器領域にある程度慣れていて、「もう一歩レベルアップしたい」と感じている薬剤師にオススメなのがこの1冊。

『循環器薬ドリル』は、循環器を専門とする医師が研修医向けに執筆した症例ベースの問題集です。
薬剤選択から投与後のフォローまで、知識を現場でどう活かすかを徹底的に考えさせられる内容で、薬剤師にとっても非常に実践的な学びがあります。
循環器の基本をひと通り学んだ方の“次のステップ”として、ぜひ挑戦してみてほしい1冊です。
→詳しく知りたい方は、下記のレビュー記事をご覧ください。
| 評価項目 | 星 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価・オススメ度 | 医師向けの問題・解説集なので、薬剤師全体にオススメできる本ではありません。ただし、循環器を本気で学びたい方にとっては、間違いなく良書です。 | |
| 実務での活かしやすさ | 自己学習用の問題・解説集なので、業務中に本書を開くイメージはありません。 | |
| 自己学習への向き | 難易度が高く、調べながら読むことが前提です。自宅などでしっかり学べる環境で読むことをオススメします。 | |
| 読みやすさ | 文章構成や日本語は丁寧ですが、内容の専門性が高く、スラスラ読める本ではありません。 | |
| コスパ | 税込4,950円。医療書としては標準〜やや高めの価格帯です。オススメできる人が限られるため、コスパの評価も控えめです。 |

研修医向けの循環器領域の問題・解説集【自己学習用】
本書は、研修医向けに書かれた循環器領域の問題・解説集です。
抗血小板薬や降圧薬、心不全治療薬などについて、「なぜこの薬が選ばれるのか?」を症例ベースで学べる構成となっています。
薬剤師にとっても、「この患者背景なら、どんな薬が選ばれ、なぜそうなるのか?」という視点で学ぶことができ、処方意図を読み解くトレーニングとして非常に有効です。

知識を“覚える”のではなく、“考える”力をつけたい薬剤師にこそオススメしたい自己学習書です。
「病態→薬」ではなく、「薬→病態」という構成なので薬剤師にも学びが多い

本書は「病態別」ではなく、「薬剤の分類別」に章立てされており、薬を起点に症例を読み解いていく構成になっています。
「この薬が使われているということは、どんな病態があると考えられるか?」「他の薬ではダメな理由は何か?」といった視点で読み進めることで、処方の背景や薬の選択理由を深く理解できるのが特徴です。
薬剤師にとっても、普段の業務で感じる「なぜこの薬が選ばれているのか?」という疑問に対し、答えのヒントが詰まっている1冊。
また、薬の分類ごとに読みたいところから始められるため、関心のある分野から学べる点も魅力です。
(気になった点)あくまで医師向けの本

構成・視点ともに、やはり診断や治療方針を決定する立場の医師向けに書かれた本です。
症例の捉え方や設問の切り口も、「薬剤師としてどう関わるか」ではなく、「医師としてどう判断するか」が中心です。
薬剤師でも読み込めば十分学びがありますが、循環器が苦手な方や初心者には難易度が高いと感じる場面も多く、最初の1冊には適しません。
本書は、すでに循環器領域の基礎があり、「もっと深く処方の背景まで理解したい」と考えている中級者以上の薬剤師向けです。

循環器の3冊目・4冊目として位置づけるとちょうどよい印象です。
【星評価まとめ】
| 書籍タイトル | 総合評価・オススメ度 | 実務での活かしやすさ | 自己学習への活かしやすさ | 読みやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|
| 『ぐんぐん 心不全・心房細動』 | |||||
| 『循薬ドリル』 | |||||
| 『ここからはじめる循環器』 | |||||
| 『循環器薬ドリル』 |
総合評価
どの本も対象となる読者が異なりますが、多くの薬剤師に自信を持ってオススメできるのは『ここからはじめる循環器』です。
薬剤師の視点に特化した構成で、循環器に苦手意識のある方だけでなく、ある程度経験を積んだ方にとっても新たな学びが得られる1冊です。
実務での活かしやすさ

今回紹介した4冊はいずれも自己学習を目的とした本であり、業務中に本を開いて調べる場面は少ないかもしれません。
その中でも『ここからはじめる循環器』には、ガイドラインの要点や表が整理されており、必要な情報をパッと調べやすい工夫がされています。
患者さんへの説明にも活用できそうです。
自己学習への向き

今回紹介した本はすべて、自己学習に役立つ良書ばかりです。
読者のレベルに応じて選ぶのがポイントで、
・初学者・新人の方には『ぐんぐん 心不全・心房細動』と『ここからはじめる循環器』
・アウトプットを重視したい方には『循薬ドリル』
・上級者には医師向けの『循環器薬ドリル』
がおすすめです。
読みやすさ
4冊の中で、最も読みやすいと感じたのは『ここからはじめる循環器』です。

ふだん本を読む習慣がない方でも、無理なく読み進められるやさしい語り口で構成されており、「これなら読めそう」と思わせてくれる1冊です。
コスパ
どの本も4,000円台で購入でき、価格に大きな差はありません。

そのため、「自分に合った1冊を選ぶこと」こそが、最もコスパの良い選び方だと思います。
内容・レベル感・目的に合わせて、納得のいく1冊を手に取りましょう。
読者別オススメランキング
今回紹介する4冊は、内容や難易度がそれぞれ異なります。

「どの本が自分に合うのか分からない…」
という方のために、読者の立場や目的別にオススメの本をランキング形式でまとめました。

このランキングが、あなたの本選びや学びのヒントになればうれしいです。
新人・ブランク明けの薬剤師向け
第1位:『ここからはじめる循環器』

循環器関連の疾患を網羅的に学べる、まさに学び始めにふさわしい1冊です。
内容も文章もやさしく、循環器が苦手な方やブランク明けで知識を整理し直したい方に最適です。
扱う疾患は心不全と心房細動に絞られていますが、学び始めの方にも十分オススメできる内容とボリュームです。
ページ数は『ここからはじめる循環器』が約300ページ、『ぐんぐん 心不全』が約200ページ。

普段あまり本を読まない方や、まずは軽めの分量から始めたい方には『ぐんぐん 心不全』が向いているかもしれません。
管理薬剤師・ベテラン薬剤師向け
第1位:『循環器疾患にかかわる薬剤師の思考・視点がわかる 循薬ドリル』
症例をもとにしたドリル形式で、「薬剤師としてどう考え、どう判断するか」を実践的に学べる1冊です。
新人・ブランク明け向けの2冊に比べると難易度は高めですが、対象は薬剤師であり、得られる学びが非常に多い1冊です。

ドリル形式なので、能動的にアウトプットすることで知識の定着がしやすい点も魅力です。
心不全患者へのフォローアップ方法を、薬剤ごとに整理して学べます。
個人の自己学習はもちろん、薬局のフォローアップ体制やマニュアル構築にも活用できます。
特に、処方変更時の観察ポイントや注意点をまとめたマニュアルを作れば、心不全フォローに強い薬局になるでしょう。
管理薬剤師の方にとっては、薬局運営に役立つ実用的な1冊になります。
薬局・ドラッグストア勤務の薬剤師向け
カルテが見られない外来対応の薬剤師は、患者さんの病名の把握がしづらいです。
本書は薬ごとのフォローアップ方法を学べるため、病名がわからない場面でも「この薬が処方されているなら、ここを確認しよう」という視点が身につきます。

外来薬剤師にとって、心強い1冊です。
第2位:『循環器疾患にかかわる薬剤師の思考・視点がわかる 循薬ドリル』
症例をもとにアウトプット中心で学べる構成は、薬局・病院といった勤務先に関係なく、薬剤師としての総合力を高めるのに最適です。
特に循環器領域を深く学びたい方にとって、本書は知識の整理と臨床的思考の強化につながる良書です。

多くの薬剤師に、本書で学んでほしいです。
病院薬剤師向け
第1位:『循環器疾患にかかわる薬剤師の思考・視点がわかる 循薬ドリル』

心不全患者に対する輸液管理の考え方など、病院ならではの症例が多く収録されています。
病棟業務やカンファレンスで活かせる知識が多く、病院薬剤師にとって大きな学びになる1冊です。
2位 『循環器薬ドリル 薬剤選択と投与後のフォローも身につく症例問題集』
医師向けに作られた参考書のため難易度は高めですが、医師がどのように症例を捉え、治療方針を決めているのかを学べます。
医師とチームで働く病院薬剤師にとって、視野を広げるのに最適です。
ぜひ本書でレベルアップしてください。
トレーシングレポートを書きたい薬剤師向け
本書では、心不全患者のフォローアップ方法を薬剤ごとに学べます。

処方変更があった患者に対して、フォローアップの電話をする許可や、医師への情報提供の許可をあらかじめ得ておけば、多くの患者でトレーシングレポートを作成できるはずです。
心不全領域でレポート作成の機会を増やしたい薬剤師に、特に役立つ1冊です。
まとめ【薬剤師向け循環器本4冊を徹底比較】

本記事では、薬剤師向けに循環器関連の書籍4冊をレビューし、それぞれの特徴や難易度、自己学習への適性を比較しました。
それぞれのレビュー記事では、各書籍の詳細な感想や活用ポイントも解説していますので、気になる本があればぜひチェックしてください。
→詳しく知りたい方は、下記のレビュー記事をご覧ください。
高齢化が進むにつれて、心不全患者は今後さらに増えていくと予想されます。
それに伴い、循環器領域の知識はますます重要性を増していきます。
今回紹介した4冊の中から、あなたの立場や目的に合った1冊を選び、日々の学びに取り入れてみてください。

私も皆さんと一緒に、少しずつ知識を積み重ねていけたらうれしいです。
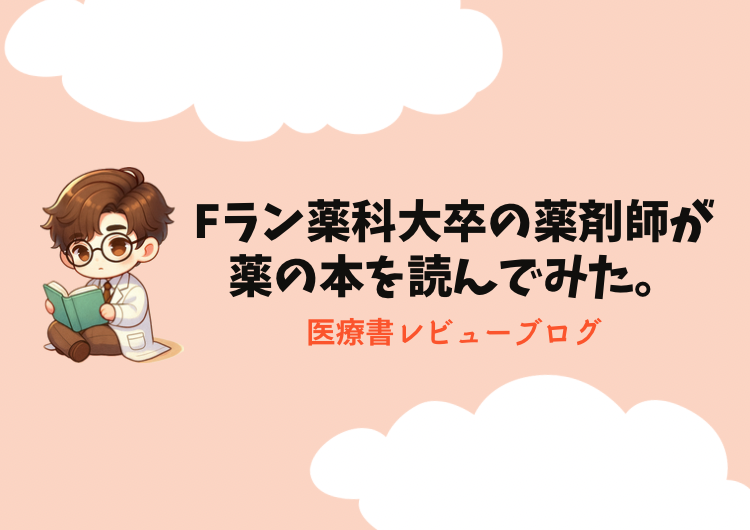
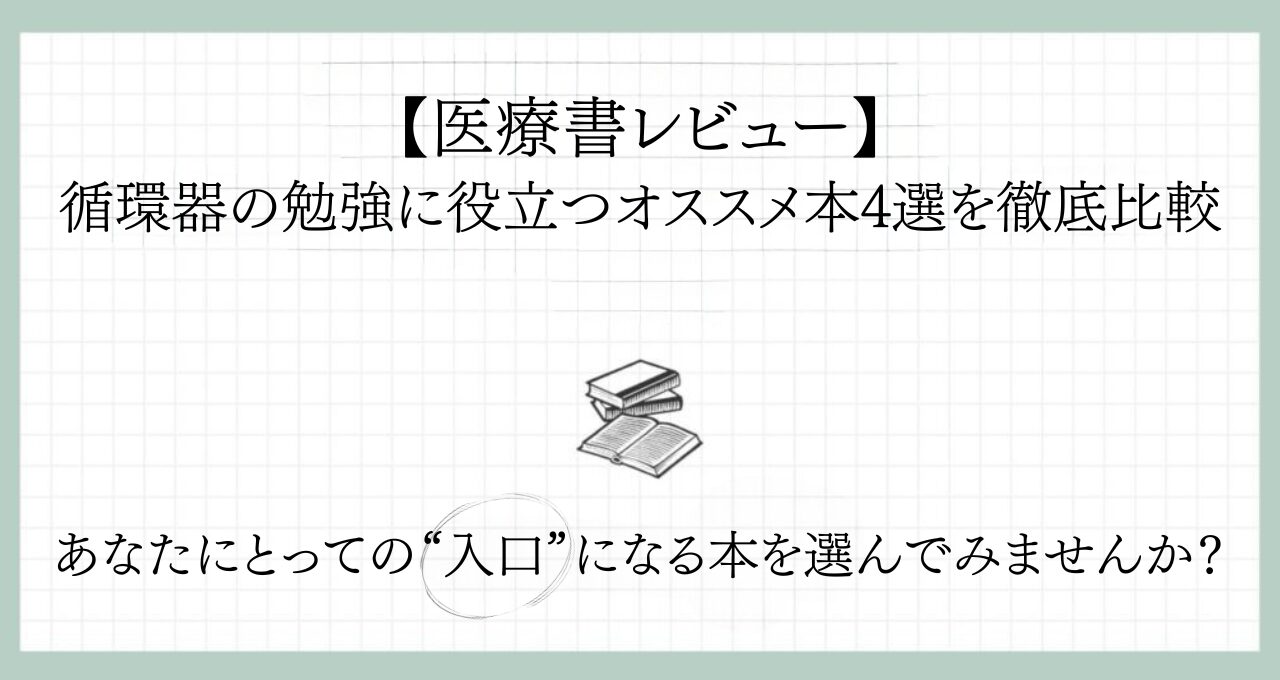
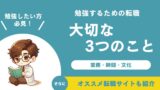






コメント