
「循環器って、どうやって勉強すればいいの?」

「心不全、狭心症、不整脈…もちろん聞いたことはあるけど、説明しろと言われたらできない…」

「そもそも、循環器の何が分からないのか分からない!」
そんなふうに感じながら、循環器の処方に対応している薬剤師の方、多いのではないでしょうか。

私自身も、苦手意識はあるのにどこから手をつければいいかわからず、「わかったフリ」で患者対応をしている時期が長かったです。
今回ご紹介する『薬剤師のためのここからはじめる循環器』は、そんな循環器へのモヤモヤに、薬剤師目線で向き合ってくれる本です。
病態・薬物治療・患者対応がどうつながるかをやさしい言葉で解説してくれます。

この記事では、本書の構成や現場での活かし方、読んで得られた学びや注意点などを、循環器が苦手な私目線でご紹介します。
本書は循環器に苦手意識のある薬剤師にとって、安心して読み進められる1冊です。
「循環器、少しわかってきたかも」——
そんな一歩を踏み出すきっかけになればうれしいです。
| 評価項目 | 星評価 | ポイント |
|---|---|---|
| 総合評価 | 私自身とても学びが多く、「読んでよかった!」と素直に思える1冊でした。多くの薬剤師の方にとっても、患者対応で“どこに注目すべきか”が明確になる内容だと思います。 | |
| 実務での 活かしやすさ | 基本は自己学習向けですが、あらかじめ付箋などを活用しておけば、現場でも「このときにこのページを見ればいい」といった使い方が可能です。 | |
| 自己学習 への向き | 文章がとてもやさしく、スラスラ読めるぶん「読んだだけ」で満足してしまう可能性も。学びを定着させるには、メモやアウトプットなど“能動的な姿勢”があると効果的です。 | |
| 読みやすさ | 専門用語にもきちんと解説がついており、循環器が苦手な方でも安心して読み進められます。電車の中などでも、これ1冊でスムーズに学べる構成です。 | |
| コスパ | 税込4,180円。医療書としては標準的な価格帯です。内容の充実度を考えると、「この価格でここまで学べるのか」と感じられる、満足度の高い1冊です。 |
『薬剤師のためのここからはじめる循環器』とはどのような本なのか
薬剤師の、薬剤師による、薬剤師のための循環器学習本
本書は、薬剤師である編者らの「循環器をどうやって勉強すればいいのか分からなかった」という自身の悩みと経験をもとに作られた、薬剤師のための循環器入門書です。
難解な専門用語や一方的な解説ではなく、「薬剤師がどこでつまずきやすいのか」「どんな場面で困るのか」といった、現場感覚に寄り添った構成が特徴です。

処方内容から患者の病態を推定する視点や、患者からどのような情報を聞き取るべきかといった“考える力”が身につきます。
循環器領域に苦手意識のある薬剤師でも無理なく読み進められます。
患者対応の場面で「何を確認すればいいか」を自分で判断できるようになりたい薬剤師にオススメの1冊です。
【難易度は易しめ】対象は循環器が苦手な薬剤師・これから関わる薬剤師
本書は、循環器領域に苦手意識のある薬剤師や、これから循環器の勉強を始める薬剤師にとって、最初の1冊として手に取りやすい構成になっています。
専門用語には丁寧な解説が添えられており、他の専門書のように調べながらでないと読めない…ということはありません。

本書だけでもスムーズに読み進められるパートが多く、通勤中などのスキマ時間でも安心して学べます。
とはいえ内容は決して浅くなく、「なぜこの薬が選ばれるのか」「どんな情報を患者から確認すべきか」といった判断の土台となる知識がしっかり詰まっています。
循環器を基礎から学び直したい新人薬剤師やブランク明けの方にも、オススメできます。
ガイドラインや表を活用し、現場で“調べる本”としても活躍
本書は基本的に自己学習用として構成されていますが、実務のなかで「ちょっと確認したい」と思ったときにも活用できる1冊です。
たとえば、血圧やLDLコレステロールの目標値は、年齢や既往歴といった患者背景によって異なります。こうした基準値をすべて暗記しておくのは現実的ではありませんが、本書にはガイドラインに準拠した表や目安が多数掲載されており、必要なときにすぐに参照できます。

あらかじめ付箋などを活用して、よく使うページをマークしておけば、現場での確認に役立ちます。
「調べやすさ」という観点でも、実務に寄り添った設計が感じられる構成です。
病院薬剤師と薬局薬剤師をつなぐ“橋渡し”の視点が得られる本

本書の大きな特徴のひとつが、すべての病態ごとに設けられている「病院と保険薬局で情報をつなぐポイント」という項目です。
ここでは、病院薬剤師・薬局薬剤師それぞれの立場から、どのように情報を共有し、連携を深めていくべきかが具体的に示されています。
病院薬剤師にとっては、その疾患においてお薬手帳や退院時サマリーにどんな情報を記載すればよいか、整理されています。一方、薬局薬剤師にとっては、単に情報を「受け取る側」にとどまらず、不足している点や不明な点をどのように問い合わせるべきかといった、能動的な視点が得られます。
分断されがちな病院と薬局の薬剤師が、互いにどのような役割を担い、どこで情報をバトンパスすべきか。その“橋渡し”の視点を養うことができる、実務に根ざした構成になっています。
【この患者には何を確認すべき?】患者対応に役立つ表が充実

私自身、本書は基本的に自己学習用として考えていますが、実際の現場でも大いに活用できます。
特に、「この患者には何を確認すべきか」が明確になるような表やフローチャートが充実しており、患者対応の場面ですぐに確認できる実用性があります。
私自身、日々の業務で本書を手に取ることがあり、すぐに見返せるように付箋を貼っているページがいくつもあります。以下は、実際に私が現場で活用している表の一覧です。
• 脳心血管病リスク評価
• 高圧薬の適応表・禁忌表
• 高血圧患者の生活習慣の修正項目
• CKD患者への降圧目標と推奨度
• CKD患者への推奨降圧薬
• レニン・アンジオテンシン系のカスケード
• 妊娠高血圧症候群で推奨されている降圧薬
• DAPTの基本
• 心房細動に対する除細動施行のフローチャート
• Vaughan WilliamsとSicilian Gambitを統合した分類表
• 心房細動における抗凝固療法の推奨
• 器質的心疾患に合併する再発性/反復性の心室頻拍に対して使用される薬物の選択
• 二次性QT延長の主な原因
• ペースメーカ植込み術における抗血栓薬の管理
• LEAD(下肢閉塞性動脈疾患)に適応のある薬剤
• LEADにおけるリスクファクター管理の優先順位
• エンパワーメントアプローチの5ステップ
• LEADのリスクファクター
• 抗血栓療法の思考と実践の5ステップ
• HAS-BLED(高出血リスク)スコアの危険因子の評価項目
• 日本版高出血リスク(HBR)評価基準
• 服薬アドヒアランス不良の要因
• 心不全治療のアルゴリズム
• 心不全の標準治療薬の特徴と注意事項
• 頻脈性心房細動に対する心拍数調節療法の治療方針
• 肥大型心筋症の治療フローチャート • 新機能障害を起こしうる薬剤
上記以外にも、本書にはまだまだ多くの図表やフローチャートが掲載されています。

すべてを暗記するのではなく、自分にとって必要な表に付箋をつけておくことで、業務中に素早く確認できる“頼れる1冊”として活用できます。
【『薬剤師のためのここからはじめる循環器』で学んだこと】個人的に印象に残った学びや発見
本書を通して、

あ、そこを見ればよかったのか!

そんな視点があったのか!
と気づかされる場面が何度もありました。
循環器が苦手な私でも理解しやすい言葉で書かれており、納得感がありました。
これまでなんとなく聞き流していた言葉や、自信がなかった知識に対して、「そういう背景があったのか」と納得できる説明が多く、学びとしてしっかり残る印象です。

ここでは、私が特に印象に残ったポイントを5つ紹介します。
循環器に苦手意識のある方が、どんな視点を持てるようになるのかをイメージしていただけたらと思います。
脳梗塞の状態によって目標血圧が異なる【低すぎてもダメ】
脳梗塞の患者では至適血圧があり、すべての患者に一律で「血圧は低いほどいい」とは限りません。

私はこれまで、血圧はできるだけ下げるべきだと考えていましたが、本書を通じて“患者の背景に応じて目標値が変わる”ことを知りました。
本書では、脳梗塞の状態やその時期(急性期/亜急性期/慢性期)によって、適切な血圧目標が異なることが丁寧に解説されています。特に、両側頸動脈の狭窄や脳主幹動脈の閉塞がある場合には、血流をある程度保つために、目標血圧をあえて“やや高め”に設定する必要があります。
また、「ペナンブラ」と呼ばれる脳梗塞周辺の虚血部分の回復を目指す時期では、血圧が下がりすぎるとかえって細胞障害を悪化させてしまうため、この時期の降圧には特に注意が必要であることも理解できました。
RAAS阻害薬は「腎保護作用」があるが、状況によっては腎機能を低下させるリスクもある

RAAS阻害薬には「腎保護作用」があるとは知っていましたが、なんとなく「腎臓にやさしい薬なんだな」という程度の認識でした。
本書を通じて、ようやく“なぜ腎臓にやさしいのか”という仕組みを理解することができました。
RAAS阻害薬(ACE阻害薬・ARB)は、糸球体内圧を下げることで腎臓への負担を軽減し、過剰な濾過を抑える作用があります。これは、輸出細動脈を拡張させるというメカニズムによるもので、結果として糸球体が傷つきにくくなるため「腎保護作用がある」とされています。

一方で、どんな患者にも使えるわけではありません。
両側性の腎動脈狭窄がある場合や、動脈硬化が進行している患者では、RAAS阻害薬によって腎血流がさらに減少し、かえって腎機能を悪化させてしまうリスクがあります。
腎保護作用があるからといって、何も考えずに腎機能低下の患者に使えばよい薬ではない。使うかどうか、どのように使うかは、患者背景を踏まえた上で慎重に判断する必要がある——
そのことを、本書を通じて学ぶことができました。
心不全の既往を確認するための便利な言葉「入院したことある?」
心不全の既往を確認する場面で、本書を通じて「これは使えそうだ」と思った問いかけがあります。
それが、

「入院したこと、ありますか?」
というシンプルな一言です。
本書によると、心不全の患者さんの多くは急性増悪をきっかけに入院治療を経験しているとのこと。
そのため、直接「心不全の既往がありますか?」と尋ねるよりも、入院歴の有無や手術の内容をきっかけに、過去の治療や病状を自然に引き出すことができます。
薬局では、患者さんが自分の病名を正確に覚えていないことも少なくありません。
そんなとき、「入院したことはありますか?」「どんな手術をしましたか?」と聞いてみることで、心不全の既往に限らず、循環器疾患やその他の重要な病歴にも気づける可能性があると感じました。
今後、服薬指導の際にはぜひ活用していきたい一言です。
心不全と心房細動は“ニワトリ・卵”の関係性
私はこれまで、「心不全は心疾患の最終段階」というイメージを持っていました。
そのため、「心房細動の悪化が進んで、結果的に心不全を発症する」という一方向の流れを、なんとなく前提として考えていました。
しかし本書では、心不全と心房細動の関係性を「ニワトリと卵」と表現しています。

どちらが先でどちらが後という明確な順序はなく、互いが原因にも結果にもなりうる関係性であることを示す、面白い例えだと感じました。
たとえば、心不全の進行によって心房への負荷が増し、心房細動を誘発することがあります。
逆に、心房細動により心拍が不規則になれば、拍出量が低下し、心不全の症状を悪化させることもあります。
心不全と心房細動の両者は、片方の疾患がもう一方のリスク因子になるという点で密接に関係しており、どちらかの既往があれば、もう一方の存在にも目を向ける必要があることを学びました。
傾聴とは?正論を伝えるだけでは伝わらない
本書では、患者対応において「傾聴」の重要性が繰り返し強調されています。

その中でも印象に残ったのが、エンパワーメントアプローチという考え方です。
これは、もともと糖尿病の自己管理支援として用いられてきた手法ですが、患者の主体性を尊重しながら、行動変容を支援するという点で、さまざまな生活習慣の改善にも応用できます。
医療者が一方的に「こうしてください」と指導するのではなく、患者自身が「なぜできないのか」「何に困っているのか」を整理し、自分で行動目標を立てて取り組めるようにサポートするというのが基本的な姿勢です。
本書で紹介されているエンパワーメントアプローチの5つのステップは以下の通りです:
1. 問題や課題を特定する
2. 感情とその理由を明らかにする
3. 行動目標を設定する
4. 計画を立てる
5. 計画を実行し、評価する
この中でも特に大切なのがステップ2の「感情の明確化」です。
たとえば患者が「食事療法がしんどい」と言ったとき、すぐに「頑張りましょう」と返すのではなく、「なぜしんどいのか」をしっかり聞き出し、その気持ちに共感することが大切だと本書は伝えています。
「正論を言えば患者は動くわけではない」
“伝える”よりも“聴く”ことが行動変容の出発点になります。

薬剤師はつい「正しい情報をしっかり伝えなければ」と考えてしまいがちですが、患者さんのつぶやきに耳を傾けることは重要です。
そして、その背景を一緒に考えることこそが、本当の意味での支援につながるのだと感じました。
『薬剤師のためのここからはじめる循環器』の良かった点・気になった点
本書の内容はとても充実していて、学びの多い1冊でした。

ただ、読みやすいからこそ、意識せずに読み進めてしまうと知識がうまく定着しないかもしれない——そんな印象も受けました。
ここでは、実際に読んでみて感じた良い点と、読むうえで意識しておきたいポイントを紹介します。
文章読みやすく、誰にでも学びがある
本書は文章が非常に読みやすく、専門書にありがちな「難解さ」や「とっつきにくさ」がありません。

説明はわかりやすく、専門用語もていねいな解説があり、循環器に苦手意識がある薬剤師でもスムーズに読み進められます。
もちろん、読む人の元々の知識量にもよりますが、本書の内容の7〜8割程度は「読めば理解できる」と感じられるくらいの難易度です。
ただしこれは「内容が自分の知識として定着する」という意味ではありません。あくまで、「文章として理解できる」「流れとしてついていける」というレベルの話です。
そのため、循環器を基礎から学び直したい薬剤師にとっては、無理なく読み進められ、かつ理解の土台を築くのにちょうどいい1冊だと感じました。
(気になった点)読みやすいぶん、「読んだつもり」にもなりやすい
本書は非常に読みやすく、内容の多くも「読めば理解できる」レベルに設計されています。

ただし、これは大きなメリットである一方、意識して読み進めないと、“ただ読んだだけ”で終わってしまうおそれがあると感じました。
各章末には練習問題が用意されていますが、難易度は比較的やさしめで、本文を読んでいれば自然と解ける内容が中心です。
だからこそ、「読めた=理解できた=身についた」と錯覚しやすいとも言えます。
たとえば、本書を読みながら実際の処方を処方解析してみる、患者対応の中で本書の知識を使ってみるなど、自ら課題を立ててアウトプットする意識がないと、知識として定着しにくい——そんな印象を受けました。
本書は非常に優れた入門書ですが、「受け身の読書」で得られる学びには限界があるということを、あらかじめ意識しておくとより効果的に活用できるはずです。
内容が興味深く、楽しく読み進められた

単純に、読むのが楽しい1冊でした。
苦手意識のある循環器という領域だったからこそ、「そういうことだったのか!」「なるほど!」という気づきが次々とありました。
「次はどんなことが書いてあるんだろう?」とワクワクしながら読み進めることができました。
日常業務に直結する内容が多く、“明日から使える知識”として読める点が、学びとしての楽しさにつながっていたのだと思います。

「勉強しよう」と気負わず、「知りたいから読む」という自然な姿勢で読み進められる——そんな1冊でした。
『薬剤師のためのここからはじめる循環器』をオススメできる人
本書は循環器の基礎から丁寧に解説されており、特に「これから循環器に関わる」という立場の薬剤師にとって、最初の1冊として非常に心強い存在です。
現場でよく出会う病態を中心に、薬剤師としてどのように考えるべきかがわかりやすく整理されています。そのため、読む人の立場や経験に応じて、さまざまな気づきや学びが得られる構成になっています。

以下のような方には、特にオススメです。
新人薬剤師・ブランク明けで復職する薬剤師
循環器は疾患数も用語も多く、最初につまずきやすい領域のひとつです。
本書では、そうした“とっつきにくさ”を感じる部分が丁寧に言語化されており、専門用語や疾患の背景を薬剤師の視点でやさしく解説してくれています。

そのため、まだ実務経験の浅い新人薬剤師や、ブランク明けで復職した薬剤師にとってわかりやすい参考書です。
「なぜこの薬が使われているのか」「患者対応で何を確認すればいいのか」が理解しやすく、自信を持って現場に立つためのベースづくりにぴったりの1冊です。
循環器に苦手意識のある薬剤師
循環器領域に対して、「なんとなく苦手なまま放置している…」という薬剤師にこそ、本書は強くオススメできます。
病名や治療薬は知っているけれど、実際の患者を前にすると、

どの薬が優先されるのか?

何を確認すべきなのか?
がモヤモヤしたまま——
そんな感覚を、本書が一つひとつ整理してくれるはずです。
現場の視点から「この病態のときは、こう考える」という道筋が明確に示されており、自分の知識の穴に気づき、ピンポイントで補うことができる構成になっています。

苦手意識のある分野だからこそ、「学び直しのスタートを切る1冊」として、ぜひ手に取ってほしい本です。
実務実習を受け入れる薬局の指導薬剤師

本書は、「循環器のことを人に教える立場」の薬剤師にとっても、大いに参考になる内容です。
実務実習では、現場経験のない薬学生に循環器領域の処方や病態を説明する必要があります。
そんなとき、専門用語や病態を学生にもわかる言葉でどう説明すればよいかに悩む場面もあるのではないでしょうか。
本書では、複雑な病態や薬物治療について、薬剤師の言葉でわかりやすく言語化されています。
学生への説明のヒントとして活用できるだけでなく、指導する側の理解も深まります。

「教えることで自分も学ぶ」——そんな実習指導の場において、本書は心強い1冊になると思います。
編者紹介
本書の編者は心不全薬物療法や循環器薬学に精通した3名の薬剤師です。
いずれも病院現場での豊富な実務経験を持ち、現場視点に立った薬剤師教育・チーム医療への貢献を重視しています。
・芦川直也 氏(豊橋ハートセンター薬局 薬局長)
循環器病棟薬剤師ネットワークの活動など、若手薬剤師の育成にも尽力。
心不全薬物療法に精通し、プレイングマネージャーとして現場と教育の両輪で活躍。
・澤田和久 氏(安城更生病院 薬剤部)
循環器病棟・集中治療病棟に十数年従事し、チーム医療・ICTにおいても中心的役割を担う。
心不全療養指導士の資格を持ち、患者の在宅復帰後の支援に取り組む。
・土岐真路 氏(聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室 主任)
心不全や循環器疾患に強い関心をもち、川崎市で心不全地域連携プロジェクトの代表を勤めるなど、地域医療連携を展開。
心不全療養指導士として、医療従事者向け教育にも注力。
現場経験に裏打ちされた知見と、薬剤師の教育に対する熱意が詰まった1冊です。
まとめ【循環器が苦手な薬剤師にぴったり】

循環器って、どこから勉強すればいいの?
そんな悩みに真正面から応えてくれる、薬剤師のための入門書でした。
“やさしさ”に全振りしているわけではなく、実務で活かせる知識や考え方もしっかり詰まっている1冊です。
読み進めるだけで「なるほど!」「明日からこう聞いてみよう」が自然と増えていく感覚がありました。
【どのような本なのか】
・薬剤師の、薬剤師による、薬剤師のための循環器入門書
・専門用語も丁寧に解説され、調べながらでなく読み進められる
・ガイドラインや図表も豊富で、現場で“調べる本”としても活用可
・病院と薬局をつなぐ「情報共有の視点」も学べる
【私が本書で学んだこと】
・脳梗塞患者の血圧目標は一律ではないと初めて知った
・「RAAS阻害薬=腎にやさしい」だけではない!正しい理解ができた
・心不全の既往確認には「入院したことある?」が便利
・心不全と心房細動は“ニワトリ・卵”のような関係性
・傾聴の姿勢が、患者の行動変容を支える鍵
【本書をオススメできる人】
・復職を目指すブランク明け薬剤師、新人薬剤師
・循環器に苦手意識のある薬剤師
・実務実習を担当する薬局の指導薬剤師

循環器を学び始めたい・学び直したいと思ったとき、「まずはこの1冊から」と自信を持って勧められる内容でした。
読んで終わりにせず、自分の業務や患者対応にどう活かすかを意識して読めば、本書の価値は何倍にも広がります。
読み終えたあとはきっと、循環器の知識に対して少しだけ前向きになれているはずです。
そんな“自分の変化”が感じられる、頼れる1冊でした。
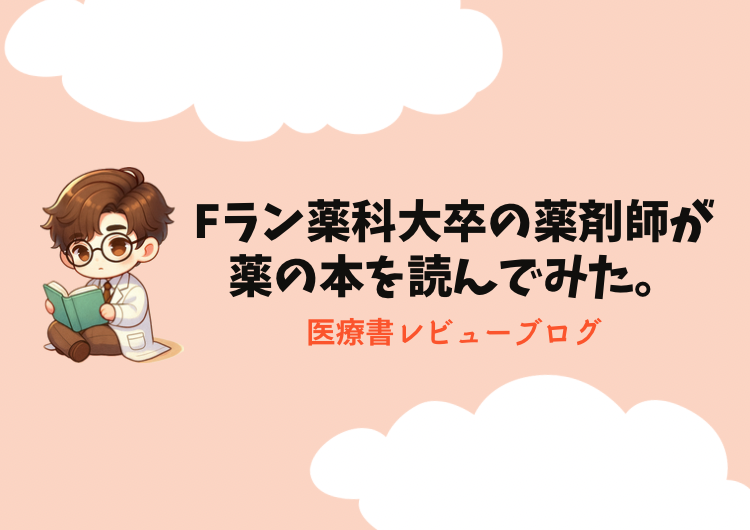
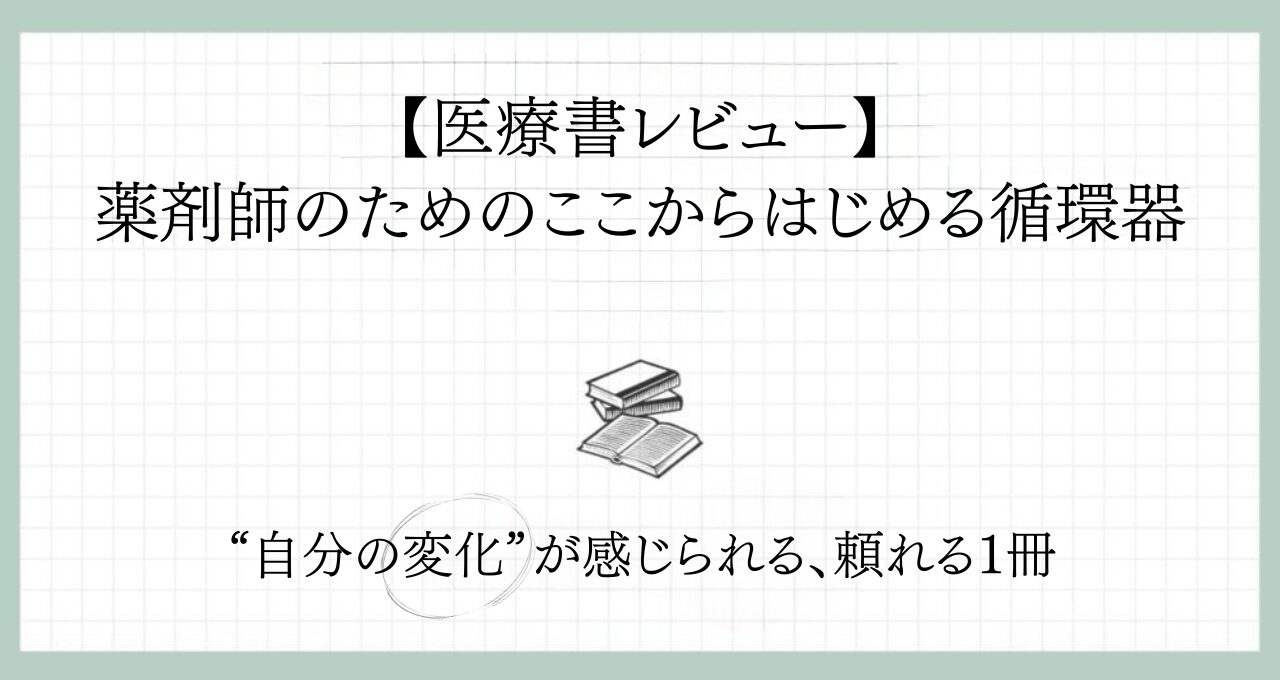


コメント